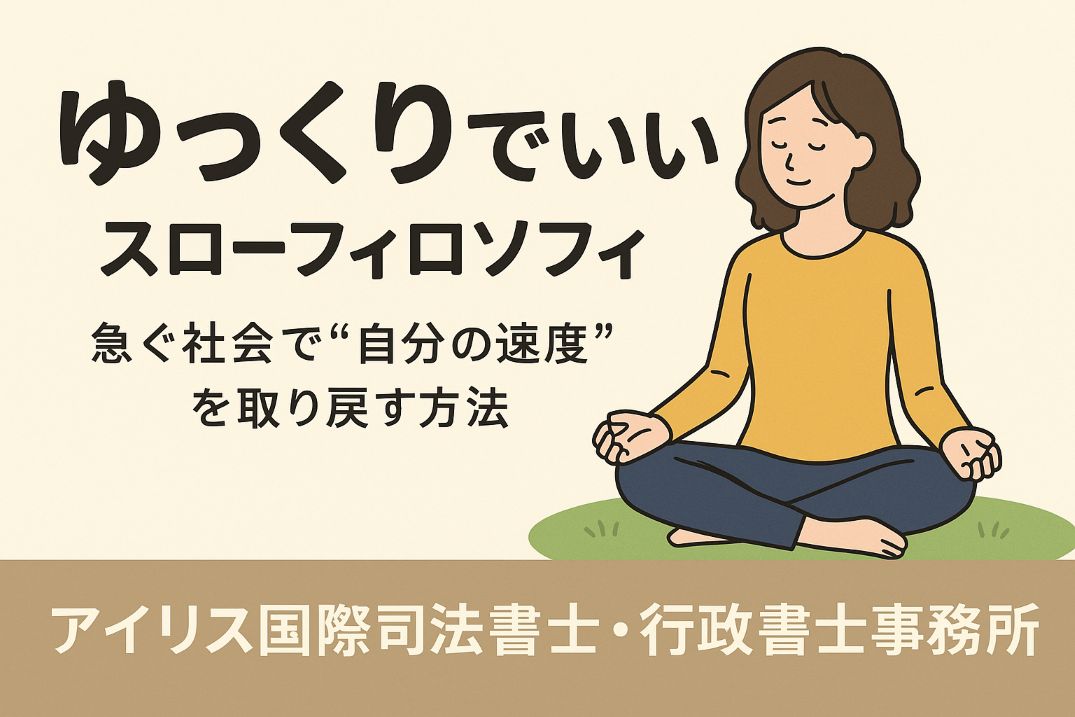相続した空き家を放置するとどうなる?固定資産税・行政指導・法的リスクを司法書士が徹底解説
相続した空き家を「とりあえず放置」すると、固定資産税の増額・行政指導・法的責任が一気に現実化します。
特に近年は、空き家対策特別措置法の運用強化と相続登記義務化が連動し、「登記していない」「管理していない」状態は許されません。
本記事では、相続空き家を放置した場合に生じる金銭的・法的・社会的リスクを体系的に整理し、今すぐ取るべき対策まで解説します。