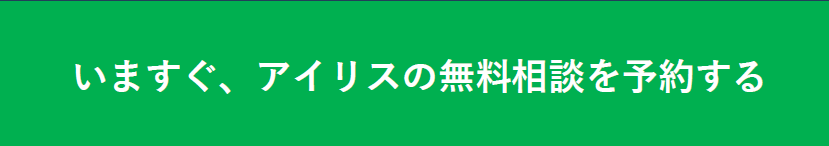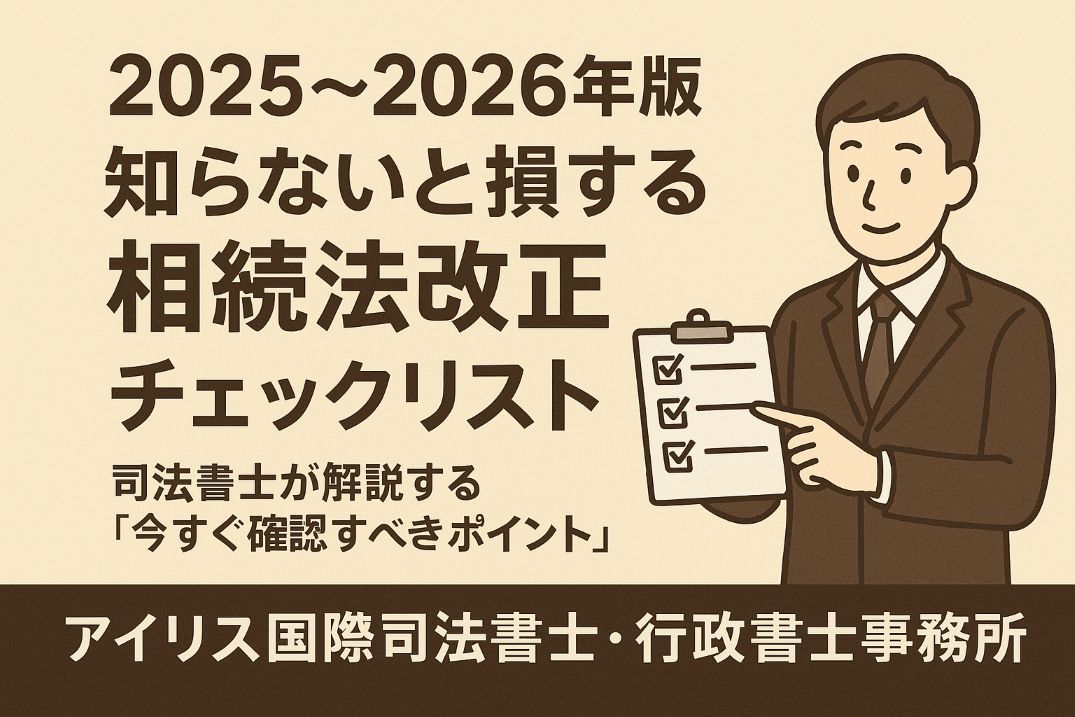相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
第3回:「相続放棄」だけが解決策ではない ─ “マイナスの遺産”との向き合い方

「借金があるから相続放棄をすれば安心」と思っていませんか?
しかし、実際の相続では"放棄すればすべて終わる"わけではありません。特に不動産が絡むと、思わぬトラブルや管理責任が残るケースもあります。本記事では、相続放棄の誤解と正しい判断の仕方を司法書士が解説します。
【目次】
- 相続放棄とは? ─ 「財産を一切受け取らない」手続きの基本
- 「放棄したのに残る責任」とは?
- 負動産を放棄しても安心できない理由
- 相続放棄と「遺産分割協議」の違い
- 放棄すべきかどうか判断するための3つの視点
- 相続放棄以外の選択肢(限定承認・名義変更・寄付など)
- 実際の相談事例:高松市での"放棄トラブル"から学ぶ
- 専門家と一緒に"負動産の出口"を探す
1. 相続放棄とは? ─ 「財産を一切受け取らない」手続きの基本

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け継がないという法的手続きです。
借金が多い、使えない山林がある、老朽化した家屋を維持できない──そんな場合に「放棄すれば全部なかったことに」と考える方も多いでしょう。
しかし、実際の相続放棄は「家庭裁判所に申述(しんじゅつ)」という正式な手続きを行う必要があり、亡くなったことを知ってから原則3か月以内という期限もあります。
そのため、「とりあえず様子を見よう」としているうちに期限を過ぎてしまうケースが少なくありません。
2. 「放棄したのに残る責任」とは?

多くの方が誤解されているのが、「相続放棄=もう何も関係ない」という考え方です。
確かに法的には相続人でなくなりますが、現実問題として"管理責任"が完全に消えるわけではありません。
たとえば、放棄した不動産が放置され、倒壊や雑草、害虫被害などが発生した場合、近隣トラブルとして行政から連絡が来ることがあります。
特に**誰も登記名義を引き取らない「空き家」や「山林」**は、次の相続人にも放棄が続き、最終的には行政が処理に困る"負動産連鎖"を引き起こすことも。
3. 負動産を放棄しても安心できない理由

「相続放棄したのに、不動産の管理をお願いされた」といった声は珍しくありません。
理由はシンプルで、相続放棄をしても、すぐに所有権が国や他人に移るわけではないからです。
民法上では、相続放棄者以外の相続人がいなくなると、「相続財産管理人」という専門職が選任されます。
しかし、この申立てにも費用と時間がかかるため、現実には手続きが進まず、放置されてしまうことが多いのです。
4. 相続放棄と「遺産分割協議」の違い

相続放棄は"相続人の地位を失う"制度。
一方で、遺産分割協議は「相続人として財産をどう分けるか」を話し合う制度です。
つまり、「自分は現金だけをもらい、不動産は放棄したい」といった調整は、相続放棄ではなく遺産分割協議で対応すべきです。
誤った判断で放棄してしまうと、他の財産(預金や保険金)までも受け取れなくなることがあるため注意が必要です。
5. 放棄すべきかどうか判断するための3つの視点
相続放棄を検討する際には、次の3つの視点で判断することをおすすめします。
- 財産と負債の全体像を把握すること
→ 亡くなった方の通帳、登記簿、借入先の資料を確認。 - 管理コストの見通しを立てること
→ 固定資産税、維持費、売却の難易度を試算。 - 他の相続人との話し合いができるかどうか
→ 分割協議で解決できる余地があるか確認。
司法書士や税理士に相談すれば、財産調査や評価も含めて「放棄が最適かどうか」のアドバイスを受けられます。
6. 相続放棄以外の選択肢(限定承認・名義変更・寄付など)

相続放棄以外にも、次のような手段で"負動産"を整理できる場合があります。
- 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスを引き受ける制度。
- 共有解消・売却:相続人間で不動産を整理・換価して現金化。
- 自治体やNPOへの寄付:条件付きで引き取ってくれる制度もあり。
いずれの方法も一長一短がありますが、「放棄=唯一の答え」ではないという認識が大切です。
7. 実際の相談事例:高松市での"放棄トラブル"から学ぶ
香川県高松市内のご相談で、「築60年の空き家を相続放棄したが、近隣から苦情が来て困っている」というケースがありました。
放棄後に誰も管理せず、草木が伸び放題になった結果、行政から改善指導が入りました。
司法書士が介入し、相続財産管理人を選任して整理を進め、最終的に取り壊し・土地売却へ。
結果的に、放棄の前に専門家へ相談していれば、もっとスムーズに処理できたケースでした。
8. 専門家と一緒に"負動産の出口"を探す
「放棄したい」と思った時点で、すでに"手放したい財産"を抱えている証拠です。
しかし、放棄だけでは"出口"にならないケースが多くあります。
相続財産の性質を見極め、「譲渡」「共有整理」「登記変更」など複数の方法を比較検討することが大切です。
香川県では、司法書士が中心となって自治体や税理士と連携し、こうした"負動産対策"を支援しています。
一人で悩まず、専門家に相談することで、最適な解決策が見つかります。

【無料相談会のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
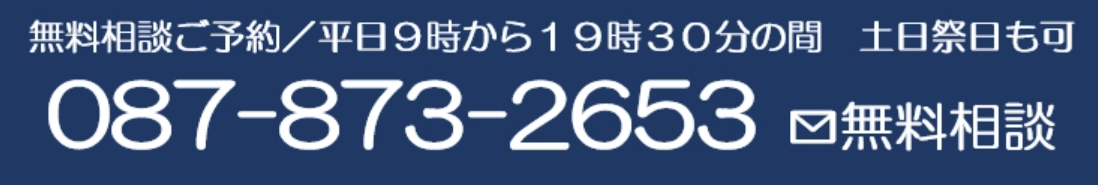
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
最新のブログ記事
個人間の組織心理学とは何か?人間関係を壊さず主導権を守る思考と実践
人間関係の悩みの多くは、「性格が合わない」からではなく、「関係の構造」を知らないことから生まれます。個人間であっても、人は無意識のうちに役割を作り、力関係や期待値を固定していきます。結論から言えば、個人間の組織心理学とは、相手を操作する学問ではなく、自分を守りながら健全な関係を続けるための"構造理解"です。本記事では、組織に限らず一対一の関係で起こる心理構造を整理し、誠実さを保ったまま主導権を失わないための考え方と実践方法を解説します。
テイカーとは何者か?定義・種類・見抜き方と消耗しない対処法【団体・組織編】
人間関係には、大きく分けて3つのタイプがあるとされています。それが、「ギバー(Giver)」「テイカー(Taker)」「マッチャー(Matcher)」です。これは、組織心理学者アダム・グラント氏が提唱した概念で、職場・団体・地域組織など、あらゆる集団で観察されてきました。
2026年を見据えた「生前対策」総点検 ― 相続法改正時代のチェックリスト完全版 ―
相続法改正の影響は、「亡くなった後」よりも「元気なうち」にこそ現れます。相続登記や住所・氏名変更登記の義務化、遺言ルールの見直し、デジタル財産の増加など、2026年を見据えて確認すべき項目は多岐にわたります。本記事では、相続・登記・遺言・財産管理を一気に点検できる総合チェックリストとして整理します。