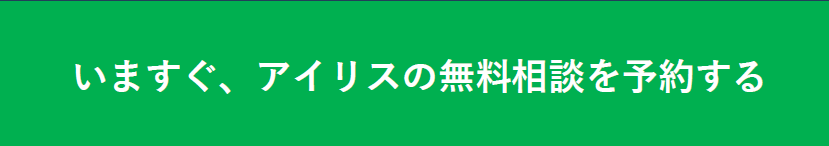相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
第2回:「遺産分割協議」で負動産を整理する方法 ─ 現場で増える“集中コース”の実態

「もらって困る相続財産」を前回解説しましたが、今回はその中でも特に厄介な"負動産"を、どのように整理していくかを詳しく見ていきます。
実務では、遺産分割協議によって特定の相続人に負動産を集中させる"整理型相続"が増加中。香川県の現場から、その実情と注意点を解説します。
■目次
- 遺産分割協議でできること・できないこと
- "負動産集中コース"とは?現場で増えている背景
- 協議書を作るときの実務上の注意点
- 引き受ける相続人のリスクと合意形成の工夫
- 相続登記義務化との関係──「名義を決めない」はもう通用しない
- まとめ:遺産分割協議を"争わない整理"の場にするために
- 無料相談のご案内(CTA)
1. 遺産分割協議でできること・できないこと

相続財産が不動産を含む場合、相続人全員で話し合い、その分け方を決める手続きが「遺産分割協議」です。
この協議によって、不動産を誰が所有するのか、どのように処分するのかを定めることができます。
ただし、遺産分割協議で決められるのは**"相続人間での配分"**に限られます。
不動産の「売却先」や「管理の委託先」など、相続人以外との契約内容までは協議の範囲外です。
また、相続人全員の同意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。
※親しい間柄の相続人間の協議は問題ないですが、前婚の時の配偶者との間の子で、別れてからあっていないなど、関係性が希薄ですと難航する場合があります。そのため、遺言書の作成を勧めております。
2. "負動産集中コース"とは?現場で増えている背景

実務では、「古い実家」「利用価値のない山林」など、誰も引き取りたがらない不動産の処理が問題化しています。
このようなケースでは、相続人のうち比較的管理可能な立場の人(近くに住む人など)に、負動産をまとめる方法が採られることが多くなっています。
これを便宜的に「負動産集中コース」と呼びます。
この方法が増えている理由:
- 相続登記義務化(2024年4月施行)により、放置できなくなった
- 共有名義では管理や売却が難しい
- 「放棄」よりも柔軟に話し合いで調整できる
- 相続税や管理費を分散させずに済む
たとえば、長男が実家の土地建物を相続し、他の兄弟には預貯金でバランスを取るような形です。
このようにして、「相続人全員が"何かを少しずつ背負う"」のではなく、整理を優先して集約させる方向が選ばれています。
※遺産の実家の土地を近所にもらってもらおうとしても、周りが空き家だらけでだれも住んでいないなんてざらにあります。早めの対応こそが突破口を開けるかもしれません。
3. 協議書を作るときの実務上の注意点
遺産分割協議書を作成する際には、単に「誰がもらうか」を書くだけでなく、次の点を明確にしておくことが重要です。

(1)負担の所在を明記する
「固定資産税・管理費・修繕費などは、引き受けた相続人が負担する」など、将来の紛争を防ぐ文言を入れます。
(2)処分予定がある場合は「合意書形式」にも対応
将来的に売却・解体を予定している場合は、「処分時の方針」を併記しておくと、後のトラブル回避につながります。
(3)書式・押印・添付資料の整備
- 相続人全員の署名・実印押印
・印鑑証明書 添付※相続登記に使用する印鑑証明書には期限はありません。しかし、金融機関の手続きの際には、期限がある場合があります。
・登記申請時に使用するため、正本と副本を作成
司法書士に依頼することで、登記に直結する形式での協議書作成が可能になります。
4. 引き受ける相続人のリスクと合意形成の工夫

負動産を引き受ける側は、単に名義をもらうだけでなく、将来の維持管理責任を負うことになります。
そのため、引き受け手の理解と合意形成が何より大切です。
例:兄弟3人の相続
- 長男:実家を相続(固定資産税を負担)
- 次男・三男:現金をそれぞれ100万円ずつ相続
このように「経済的バランスを取る」ことが、公平性と納得感を保つ鍵となります。
また、相続人の一部が遠方に住んでいる場合や意見が分かれる場合は、オンラインでの協議や専門家の立会いを活用することが有効です。
※アイリスでは、オンラインを使いご家族間で話し合いをしていただけるような部屋をご用意しております。(話し合いの際、司法書士は立ち合いをいたしません。)
5. 相続登記義務化との関係──「名義を決めない」はもう通用しない

これまで、「とりあえず登記は後で」というケースも多く見られましたが、
2024年4月以降は、相続発生から3年以内に相続登記を行う義務が課されました。
登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
さらに、登記がなされていない土地は「所有者不明土地」として扱われ、売却・活用が極めて難しくなります。
したがって、遺産分割協議書を作成したら、そのまま登記手続きまで一貫して行うことが非常に重要です。
司法書士に依頼すれば、まとまった協議内容の協議書作成から登記申請までをスムーズにサポートできます。
6. まとめ:遺産分割協議を"争わない整理"の場にするために
遺産分割協議は、「誰がどれだけもらうか」を決める場ではなく、
「次世代に負担を残さないための整理をどうするか」を話し合う場でもあります。
負動産をめぐる相続は、感情的な対立を招きやすい問題です。
しかし、早期に冷静な協議を行い、必要に応じて専門家がサポートすることで、円満な解決が可能になります。
香川県でも、空き家や利用価値の低い土地をどう処理するか悩むご家族が増えています。
「話し合いのタイミングを逃さないこと」こそが、負動産問題の第一歩です。

■(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
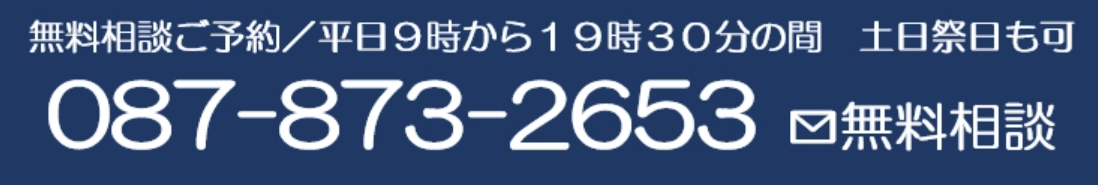
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続登記・放棄相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


最新のブログ記事
家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】
「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」
最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】
「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味
司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。
この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。
本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。