【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
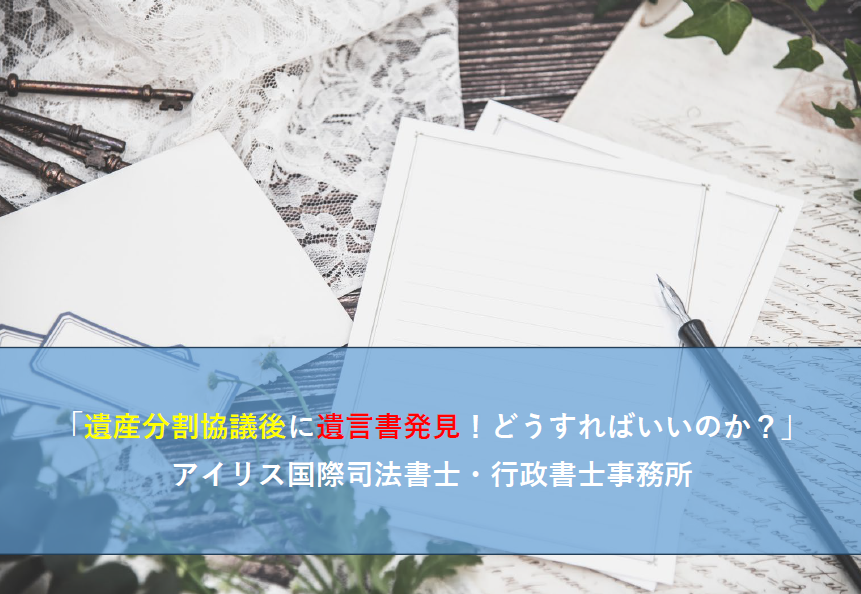
遺産分割協議をした後に遺言書を発見した場合、どうすればいいのでしょうか?「見なかったことにする」で済むのでしょうか?わかりやすく解説したいと思います。
目次
1.遺言書の効力
2.遺産分割協議後、遺言書が発見された場合
3.家庭裁判所で行う検認とは
4.遺言執行者とは
5.まとめ
1.遺言書の効力

遺言では「相続方法」を指定することができます。法定相続分以外の割合で遺産を分け与えたり、特定の遺産を特定の相続人や相続人以外の人へ受け継がせたりすること(遺贈)が可能になります。法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されているためです。
「(遺言による相続分の指定)
民法 第九百二条 被相続人は、前二条の規定(法定相続・代襲相続について)にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」
つまり、遺言があると、法定相続分を超える相続や下回る相続も有効となります。遺言書を使うと、以下のような事項を指定できます。
①相続分の指定、➁遺産分割方法の指定、③遺贈、④寄付、➄遺産分割の禁止(5年以内)、⑥認知、⑦相続人の廃除、⑧保険金受取人の変更、⑨遺言執行者・遺言執行者を指定する人の指定。
逆に、民法で定められている項目以外の事項を遺言書に書いても効力はありません。
2.遺産分割協議後、遺言書が発見された場合

法定相続した遺産を協議で帰属先を定めるのが、遺産分割協議です。この協議は、法定相続人全員の参加が要件です。しかし、協議の後に相続人お一人が遺言書を発見した場合、どうなるのでしょうか?
もし、未開封の遺言書を相続人の一人が発見した場合、「見なかったことにする。」のはやめてください。民法で定められている相続人の「欠格」事由に該当する可能性があります。
まずは、相続人全員に連絡をして、家庭裁判所での「検認」の手続きをしてください。
3.家庭裁判所で行う検認とは

「「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(裁判所HP引用)
つまり、検認手続きでは、遺言の有効無効を判断するものではなく、遺言書の現状を公的機関で保管する手続きです。封がされている遺言書の場合、未開封のまま、家庭裁判所に持ち込んでください。家庭裁判所で開封された遺言書は、すぐにコピーがとられ裁判所で保管します。仮に開封したとしても、検認手続きはできますが、「過料」が発生しますのでご注意を。
4.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負う人です。遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。遺言執行者は民法で「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。(民法1012条)
遺言執行者は、遺言者が遺言内容に指定することもできますし、
遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を指定する場合もありますが、遺言執行者は、遺言者の遺言内容を実現するために相続人に代わって行うために、代理人ではなく本人という立場で執行することになります。2019年の法改正により、遺言執行者は単独で不動産の名義変更できるようになりました。
5.まとめ
遺産分割協議と遺言書では、遺言書の効力の方が優先されます。そのため、相続人全員で遺産分割協議をした後に、相続人の一人が遺言書を発見した場合、速やかに相続人全員に連絡をして、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
遺言内容を執行するには、遺言執行者が必要です。遺言執行者は、遺言書の指定があればその方、その方がすでに亡くなっていたり指定されていない場合には、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。


高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。