相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第1回】2026年2月スタート予定!「所有不動産記録証明制度」とは? ~相続・資産調査が大きく変わる新制度の概要を解説~
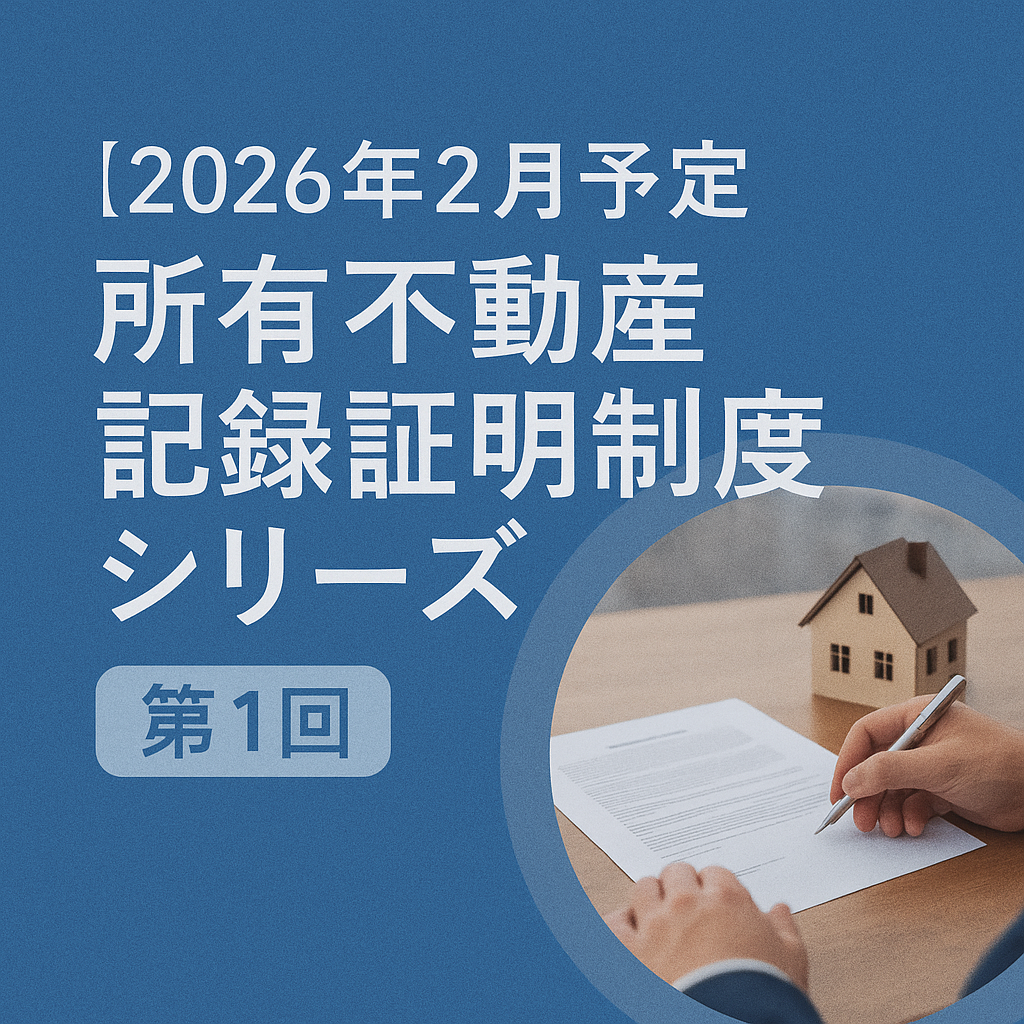
相続の手続きを進める上で、被相続人がどの不動産を所有していたのかを把握することは非常に重要です。しかし現在、その調査は各地の法務局で不動産ごとに登記簿を取得する必要があり、時間も費用もかかってしまうのが現状です。
2026年2月から始まる「所有不動産記録証明制度」は、こうした相続や資産調査における不動産調査の大きな手間を軽減する制度として注目されています。本記事では、これからスタートするこの制度の概要について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
不動産の一括調査、相続対策、所有者の資産把握、財産調査の新制度にご関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
◆目次
- 所有不動産記録証明制度とは何か
- どんな情報がわかるのか
- 現行制度との違いは?
- どんな人に役立つ制度か
- 第2回以降の予告
- まとめ
- 相続・不動産調査のご相談は当事務所へ
1. 所有不動産記録証明制度とは何か

所有不動産記録証明制度は、「個人が全国に所有する不動産を、氏名・住所・生年月日・性別などの情報から一括で検索し、その結果を証明書として取得できる制度」です。
2026年2月の開始を予定しており、法務局が中心となって運用を行います。利用対象者は原則として本人または相続人など一定の関係者に限定される予定です。
2. どんな情報がわかるのか
この制度を利用すると、次のような情報が一覧で表示されます。
- 所有している不動産の所在地(地番・家屋番号)
- 登記名義人として登録されている日付
- 所有権の種類(共有持分かどうか等)
- 管轄の登記所(法務局)
従来は各地の登記所で個別に調査する必要がありましたが、これが一括でわかるため、調査効率が格段に向上します。
3. 現行制度との違いは?

現在、不動産を調査するには「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得する必要があり、どこの不動産を所有しているかの"あたり"がなければ調査が困難です。
一方、所有不動産記録証明制度では「人」単位で検索できるのが最大の特長です。相続が発生した際に、被相続人がどこに不動産を持っているのか全く不明なケースでも、制度を利用すれば所有地を漏れなく把握することができます。
4. どんな人に役立つ制度か

この制度は以下のような方々にとって非常に有用です。
- 被相続人の財産を調査したい相続人※
- 成年後見制度を利用しているご家族
- 不動産売却を検討しているが、資産全体の把握ができていない方
- 成年後見人・任意後見人・相続人代表として手続きを進める専門職
また、司法書士や税理士などの士業にとっても、遺産分割協議や相続登記の際に不可欠な情報収集手段となるでしょう。
5. 第2回以降の予告
次回の記事では、この制度を実際にどのように利用するのか、申請方法や必要書類、費用などを詳しく解説します。
さらに、第3回では注意点や制度の限界、他制度との使い分け、そして実務的な活用例について紹介する予定です。ぜひシリーズでご覧ください。

6. まとめ
所有不動産記録証明制度は、これまで困難だった不動産の一括調査を実現し、相続実務において画期的な変化をもたらす制度です。相続人が財産の全容を把握するための手間を大幅に軽減し、遺産分割や相続登記をスムーズに進めるための一助となるでしょう。
制度開始前に情報をキャッチアップし、準備しておくことが重要です。
アイリスでは、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



