相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
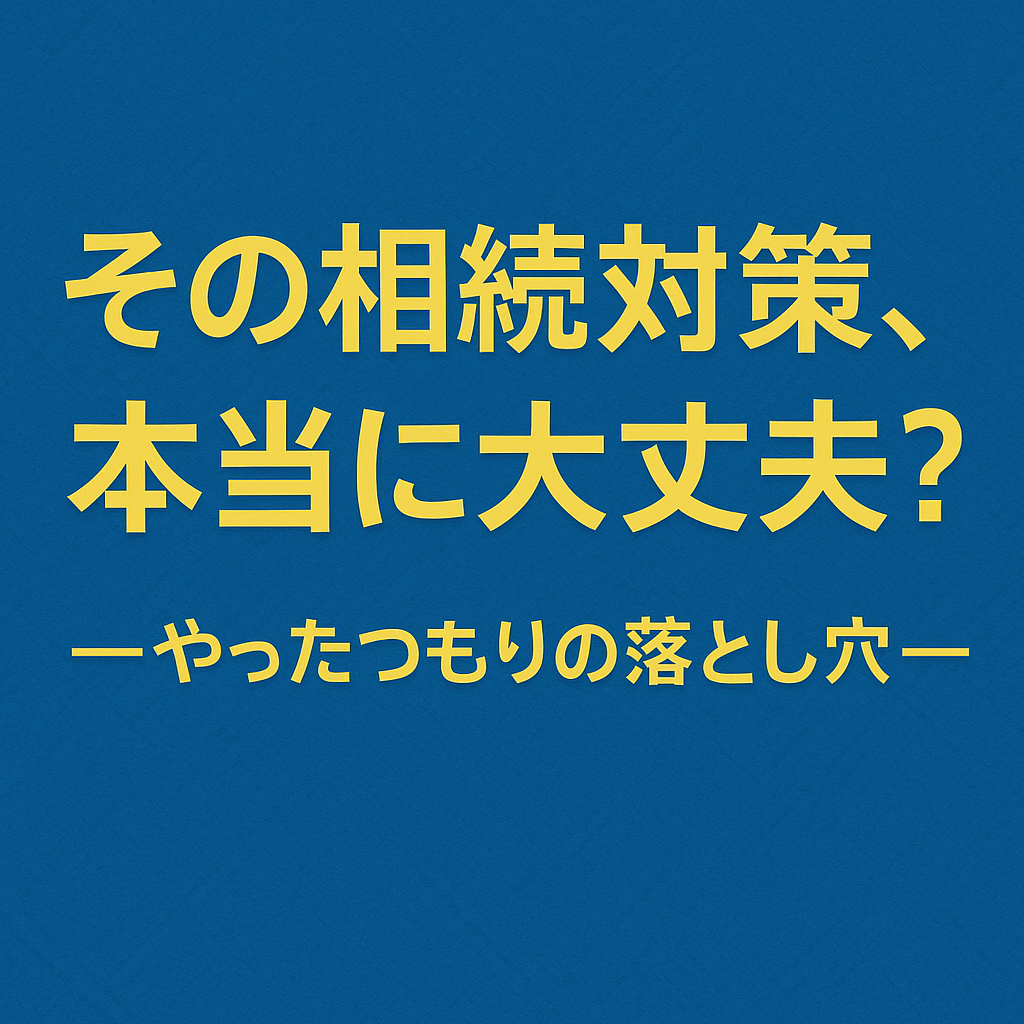
「この土地は長男にあげると父が言っていた」「母から生前に譲ってもらう約束をしていた」──こうした**"口約束"による相続のトラブル**は、今も後を絶ちません。
相続において、親子間の信頼関係や慣習に頼るのは非常に危険です。登記がされていない不動産や、契約書のない贈与の約束は、法的には「無かったこと」になり、他の相続人との間に深刻な対立を生むことも。
本記事では、贈与と登記の重要性、そしてそれが相続にどのような影響を及ぼすのかを、事例を交えて解説します。
【目次】
1. 「あげる」と言われただけではダメ?

生前に親から「この家はお前にやる」と言われていた。
長年その家に住み続けていた——こうしたケースは非常に多く見られます。
しかし、相続が発生した途端、他の相続人から「そんな話は聞いていない」と異議が出されることがあります。
残念ながら、"言った・言わない"の話は証拠にならず、法的効力を持ちません。親の遺志を実現するためには、書面や登記といった"形"が必要なのです。
2. 贈与は"契約"であり、証拠が必要

民法では、贈与は「当事者双方の合意によって成立する契約」とされています(民法549条)。
つまり、「あげる」「もらう」という意思表示の合致があれば成立はしますが、書面がなければ撤回可能とされています(民法550条)。
特に不動産の贈与は、契約書と登記がセットで行われていない限り、第三者に対抗できないため、他の相続人からの異議に対応できなくなる可能性が高くなります。
3. 不動産の名義変更(登記)をしていないとどうなる?

たとえ親から「この土地はお前にやる」と言われていたとしても、**名義が親のままであれば、その土地は"遺産"**として扱われます。
そして、法定相続人全員の共有状態となり、他の相続人の同意がないと処分できなくなるのです。
さらに、口約束の主張が他の相続人の利益を侵害するとして、「特別受益」として遺留分侵害請求の対象になることも。
これは、想定外の相続トラブルの火種になりかねません。
4. 口約束による相続トラブルの典型例

【事例】
父が生前に「長男に自宅をやる」と言っていたが、登記は父名義のまま。
父の死後、長男は当然のように住み続けたが、弟と妹が「遺産分割協議をしてくれ」と主張。
長男は「もらったものだ」と主張するが、登記も契約書もないため証明できず、結局は不動産を含めた分割協議に。
調停にまで発展し、相続手続きは数年越しに。
このように、信頼関係が崩れた瞬間、口約束は"なかったこと"にされてしまうのです。
5. なぜ登記を後回しにしてしまうのか
生前贈与を受けた側としては、登記のための費用(登録免許税、司法書士報酬など)を避けたい、という心理が働くこともあります。
また、「税務署に知られたら贈与税がかかるのでは」との誤解や、親側が「死ぬまでは自分の名義で持っていたい」と考えるケースもあります。
しかし、これらの理由で登記を後回しにした結果、本来の意思が法的に実現されなくなるリスクを高めてしまいます。
6. 贈与契約書や登記を整えておくべき理由

トラブルを未然に防ぐためには、
こうした"形式"をきちんと整えることが不可欠です。
また、生前贈与を行う場合は、**贈与税の非課税制度(例:相続時精算課税制度や住宅取得資金の贈与特例)**を活用すれば、税負担を軽減しながら登記を済ませることも可能です。
7. まとめ:言葉ではなく「証拠」で家族を守る
「親子の間だから大丈夫」「家族がわかってくれるはず」——
そう思っていた"口約束"が、家族関係を壊す結果になってしまうのが、相続の怖さです。
相続は、**「気持ち」より「証拠」**の世界です。
親の意思を実現し、家族の争いを防ぐためには、贈与契約と登記という"形に残る証拠"を残しておくことが最も効果的な対策です。

次回は、**「名義預金」の落とし穴──家族名義の預金は誰のもの?」**をテーマに、実際の通帳や預金の管理が、思わぬ課税や争いの原因になるケースを解説していきます。
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「もらって困る相続財産」を前回解説しましたが、今回はその中でも特に厄介な"負動産"を、どのように整理していくかを詳しく見ていきます。
実務では、遺産分割協議によって特定の相続人に負動産を集中させる"整理型相続"が増加中。香川県の現場から、その実情と注意点を解説します。
相続という言葉に「財産がもらえる」という明るいイメージを持つ方は多いでしょう。
しかし現実には、維持や管理に多大な負担を強いられる"負動産"という遺産も存在します。
本記事では、香川県内でも増加している「もらって困る相続財産」の現実と、その背景を司法書士の視点から解説します。
GoogleがAIを検索に組み込むのに慎重だった理由は、単なる収益の問題だけではありません。本記事では「ユーザー体験」「信頼性」「広告主との関係」といった観点から、Googleの戦略をさらに掘り下げて対話形式で解説します。