相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第5回】遺産分割後にトラブルが発生したらどうする? ~やり直し、無効、遺留分の主張まで徹底解説~
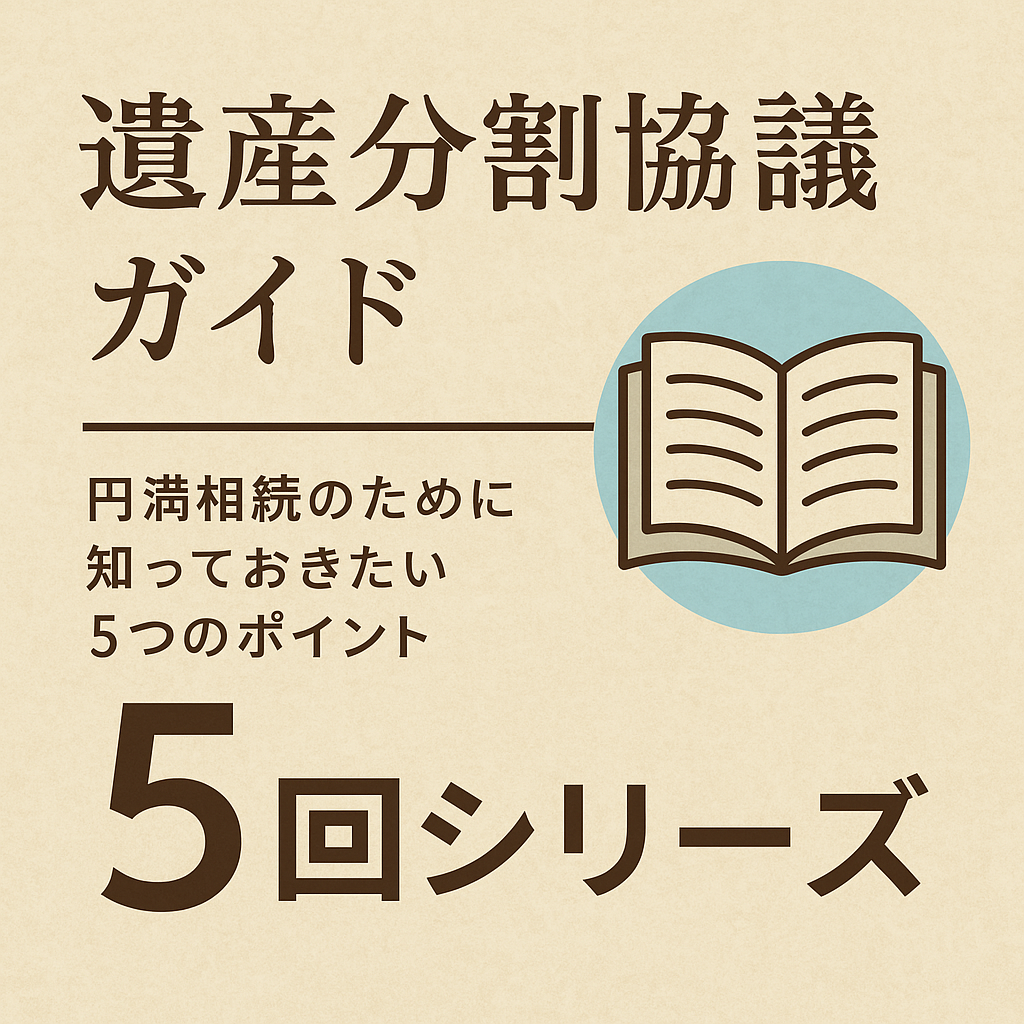
「遺産分割協議が無事終わってホッとしたのに、後から他の相続人が異議を唱えてきた……」「協議書に署名したが、実は内容をよく理解していなかった」――このように、遺産分割が終わったと思っても、後からトラブルになるケースは少なくありません。特に、法定相続人全員の合意がなかったり、内容に不公平があったりすると、やり直しや無効の主張が持ち上がることもあります。本記事では、遺産分割後のトラブルとその対処法、そして遺留分の主張や調停・訴訟での対応まで詳しく解説します。
■目次
- 遺産分割協議の成立とは?
- 協議書の無効が主張されるケース
- 遺産分割の「やり直し」は可能か?
- 遺留分侵害額請求とは何か?
- トラブル回避のためにできること
- 弁護士や司法書士への相談の重要性(CTA)
1. 遺産分割協議の成立とは?

遺産分割協議は、被相続人の財産を誰がどう分けるかを相続人全員で合意する手続きです。そして、その合意内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
協議が成立するには以下の要件が必要です:
- 法定相続人全員が協議に参加している
- 各相続人の意思表示が自由である(強要や詐欺でない)
- 内容に重大な瑕疵がない(錯誤・誤解がない)
これらのいずれかが欠けていると、「協議そのものが無効」とされる可能性があります。
2. 協議書の無効が主張されるケース

以下のような事情がある場合、協議書の有効性に疑義が生じることがあります:
- 一部の相続人が協議に参加していなかった
- 押印したが内容を理解していなかった(認知症等)
- 偽造・改ざんされた協議書だった
- 強圧的な言動で同意を強いられた
無効が認められると、遺産分割はやり直しとなり、登記や口座解約の効力も影響を受ける可能性があります。
3. 遺産分割の「やり直し」は可能か?
協議が一度成立した後に、「やっぱり納得がいかない」と言っても、原則としては簡単にやり直しはできません。しかし以下のケースでは再協議が認められることがあります。
- 全相続人の合意がある場合:再協議書を作成すれば可能
- 新たな財産が発見された場合:追加の協議が必要
- 無効や取消の理由がある場合:家庭裁判所での争いになる可能性あり
一度成立した協議の効力は強いため、慎重に合意形成することが重要です。
4. 遺留分侵害額請求とは何か?

たとえば、ある相続人だけが大半の財産を相続するような協議がなされた場合、他の相続人が「自分の取り分が少なすぎる」と感じることがあります。このような場合に主張できるのが遺留分侵害額請求です。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。遺言や協議によってこれが侵害された場合、侵害された人は他の相続人に対して、金銭での支払いを請求することができます。
ポイントは以下のとおり:
- 請求できるのは、直系卑属(子・孫)や配偶者、父母などの一部相続人のみ
- 原則として、相続開始と侵害を知ってから1年以内に請求しなければならない
- 裁判所に申し立てることで法的請求も可能
遺留分の主張は金銭請求に限られるため、不動産そのものの共有を求めることはできません。
5. トラブル回避のためにできること
遺産分割協議後のトラブルは、協議前にリスクを想定して対策を講じることで防ぐことが可能です。
たとえば:
- 協議書の内容を明確に記載し、専門家にチェックしてもらう
- 認知症の可能性がある相続人がいる場合は、後見制度を利用する
- 特別受益(生前贈与など)や寄与分の有無を事前に整理しておく
- 相続放棄をした人や連絡の取れない相続人の確認を怠らない
こうした配慮をすることで、協議の無効ややり直しリスクを大きく軽減できます。

6. 弁護士や司法書士への相談の重要性(CTA)
相続人間の協議は、感情的な対立や誤解が生じやすく、後からトラブルに発展することが少なくありません。とくに、**「知らずに協議書にサインしてしまった」「内容が不公平だった」**といったケースは、後で後悔しても取り返しがつかないこともあります。
当事務所(司法書士
橋本大輔|アイリス国際司法書士・行政書士事務所)では、
✅ 相談無料(要予約)
✅ 戸籍取得・調査の代行可能(相続登記のご依頼を受けた場合のみ)
✅ 相続放棄や登記手続きにも対応
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
◼シリーズ完結にあたって
5回にわたってお届けしてきた「遺産分割協議シリーズ」も、今回で完結となります。遺産分割は、法律と感情のバランスが難しいテーマです。だからこそ、早めの対策と専門家の関与が、トラブル回避の鍵になります。
これまでの記事も含めて、必要に応じて読み返していただければ幸いです。
今後も相続に関する情報をわかりやすく発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



