【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。

以前、配属研修先で、司法書士事務所で補助者として働きたいという方がいるので、面談に同席してほしいと言われ、一緒に面談をすることになりました。「補助者として働いたら、司法書士試験に必要な知識が付きますか?」と言われ、先生も私も同じ結論に達し、アドバイスをいたしました。その辺りについて、少しお話したいと思います。
目次
1.司法書士試験に必要な知識
2.司法書士実務に必要な知識
3.補助者として働いて司法書士資格を取得できるようになるのか?
1.司法書士試験に必要な知識

司法書士試験の科目は、11科目で、特に主要4科目の練度を高めないとなかなか合格には至りません。主要4科目については、無駄な部分というのはほぼないくらいだと考えていいですし、マイナー科目も科目によっては、全体・個別の知識を明確に要求される分野もあります。つまり、手をほとんど抜くことはできないということになります。
しかし、逆を言えば、この11科目を制すれば、合格も可能ということになります。が、この試験、実は、実務者養成試験なんです。記述試験の内容を見ていただければ明らかだと思うのですが、実務的な視点を持たずして、記述の項目を埋めていくことなんてできませんからね。特に、不動産登記法の記述試験においては、民法と不動産登記法の知識の当てはめで考えないと解けません。不動産登記法には、法律・規則・省令以外に「先例」「判例」「通達」と、法律を補正する形での、いわゆる例外的な取り扱いがなされる場合があります。体感ですが、3割くらいはそういったものがありますし、そこを突いてくる場合も多々ありますので、法律だけ理解していても、高得点獲得には至りません。
ここまでやったのだから、実務をすんなりこなせると思っている方もいると思いますが、実はそうではありません。
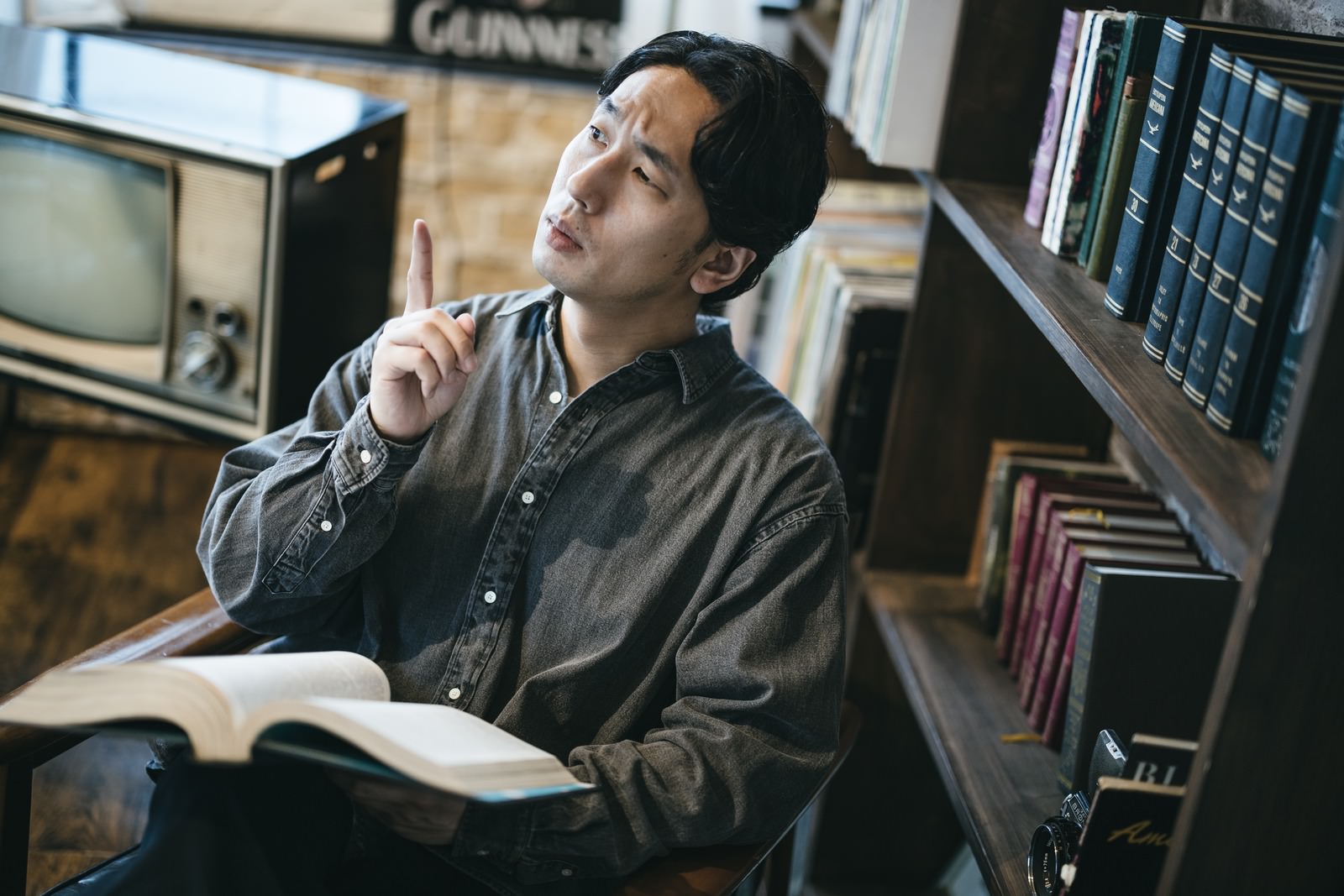
2.司法書士実務に必要な知識
実務に入りますと、相談者からさまざまな相談が持ち込まれ、これに対応していかなければなりません。11科目分の法律知識だけでは足りないと思います。11科目分の知識は当然、熟知している状態で、各相談者に合わせた解決策を提示していかなければならないからです。不動産の売り買いや贈与の場合でも、そこにかかる税金や、土地利用の制限についても知らないと、手続きをした後に、相談者の意向に反してしまうケースもあるからです。
私は、試験合格後、実務に入ってからの知識として「宅地建物取引主任者」の試験を受けました。司法書士試験では、税金の分野と言えば、登録免許税だけですが、実務においては、不動産取得税や譲渡所得税、贈与税、相続税などといった、税務的な知識も要求されます。もちろん最終は、税理士に相談していただきますが、相談時にどのような税金がかかるので、一度税理士に相談しておいた方がいい、とアドバイスするケースが多々あります。
つまり、試験に必要な知識の上に、さらに多くの知識・経験が必要となります。
3.補助者として働いて司法書士資格を取得できるようになるのか?
結論から言うと「なれます」。地元の司法書士事務所で補助者をしながら司法書士になった方を数多く知っています。しかし、試験勉強の知識と実務をかなり意識していたのだと推測いたします。司法書士事務所によっては、大手になると多種多様の業務をやっていますが、携われるのは1部分のみだったりしますし、小規模の個人事務所だと、業務を特化している場合が多いですので、なかなか試験範囲全域にわたり携わることは不可能だと思います。となると考え方によると思うのですが、ある程度の「割り切り」が必要だと考えます。

高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。