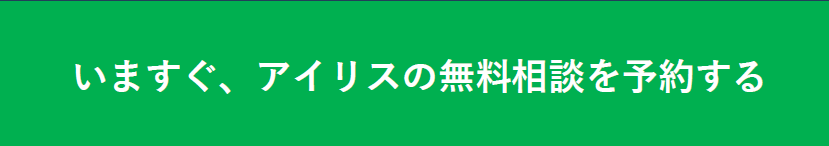相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
増加の理由を探る|少子化・未婚化・地域社会のつながりの希薄化がもたらす影響
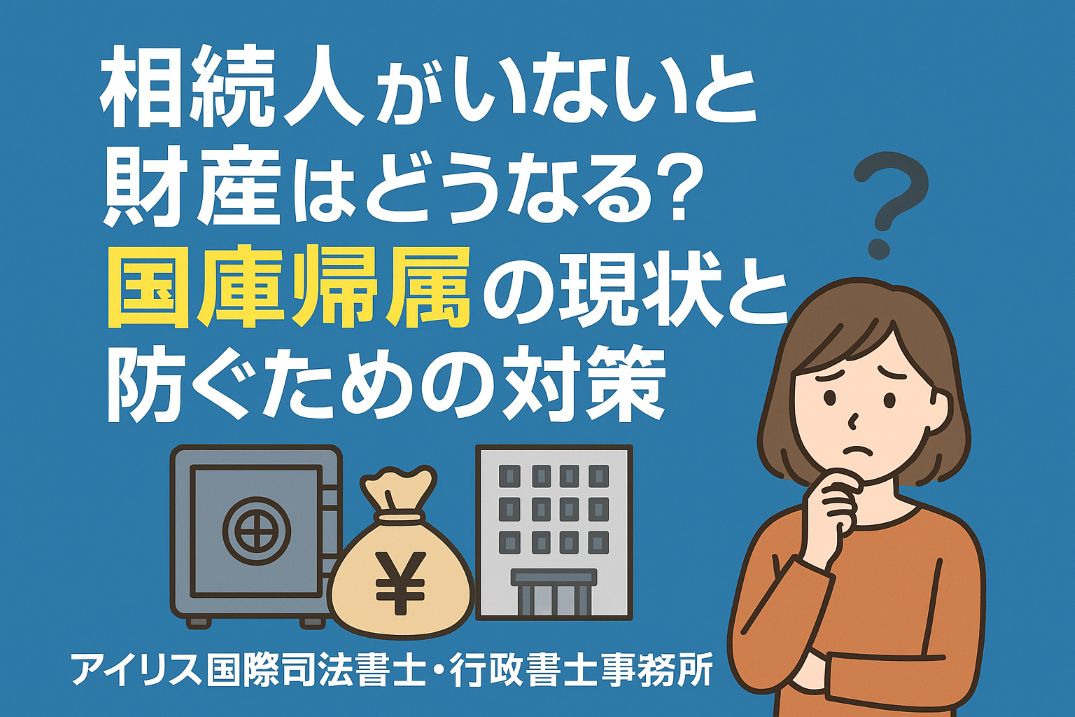
なぜ今、「相続人不存在」が社会問題になるほど増えているのでしょうか?背景には人口構造の変化や地域の人間関係の希薄化があります。今回はその社会的要因に焦点を当てます。
目次
- 少子高齢化が相続に与える影響
- 未婚率・子なし世帯の増加
- 地域社会からの孤立と「発見の遅れ」
- 相続人不存在がもたらす不動産の管理問題
- 空き家・荒廃農地など社会的損失との関連
- まとめ:家族の問題から社会の課題へ
1. 少子高齢化が相続に与える影響

日本は急速な少子高齢化社会に突入しています。総務省の統計によれば、65歳以上の人口は約3割を超え、今後も増加が見込まれています。
高齢者が増える一方で子ども世代が減少しているため、「相続人となる子や孫がいない」ケースが増えるのは自然な流れです。
従来であれば、子や孫が相続していた財産も、少子化により引き継ぎ手が存在せず「相続人不存在」となる事例が目立ってきています。
2. 未婚率・子なし世帯の増加
加えて、未婚化・晩婚化の進展も大きな要因です。
国勢調査によれば、生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことがない人の割合)は、男性で約25%、女性でも15%を超える水準に達しています。
- 未婚 → 配偶者がいない
- 子どもがいない → 直系の相続人がいない
- 親兄弟もすでに他界 → 相続人不存在
こうした世帯が増えていることは、今後さらに「相続人不存在」が社会問題として顕在化していくことを示しています。
3. 地域社会からの孤立と「発見の遅れ」

昔は地域社会のつながりが強く、近隣住民が互いの生活状況を把握していました。ところが近年は都市部・農村部を問わず人間関係が希薄化し、単身高齢者が孤立しやすくなっています。
孤立によって起こる問題は2つです。
- 相続人の存在確認が難しくなる
- 死亡の発見が遅れる
「孤独死」の事例が増えているのも、この社会構造の変化を反映しています。相続の手続きが遅れ、結果的に財産管理が困難になるケースが増えているのです。
4. 相続人不存在がもたらす不動産の管理問題

相続人がいない場合、最も深刻化するのが「不動産の管理問題」です。
- 誰も管理しない空き家が放置される
- 登記名義が故人のままになり利用できない
- 農地や山林が荒廃し、地域環境へ悪影響を及ぼす
このような不動産は法的に整理が難しく、自治体や近隣住民にとって大きな負担となります。
5. 空き家・荒廃農地など社会的損失との関連

相続人不存在は、単に「家族の問題」では終わりません。
放置された財産は、空き家問題や荒廃農地といった社会的損失につながります。
特に地方では、人口減少と相まって地域全体の景観や安全性に影響を与える深刻な課題となっています。
自治体は管理責任を問われる場面も増えており、地域社会全体の問題として対応が求められています。
6. まとめ:家族の問題から社会の課題へ
相続人不存在の増加は、
- 少子高齢化
- 未婚化・子なし世帯の増加
- 地域社会の希薄化
といった社会構造の変化が背景にあります。
これは単なる個人や家族の問題ではなく、空き家・荒廃農地の増加、地域の安全や景観の悪化といった「社会全体の課題」として考える必要があります。
早めの生前対策や専門家への相談が、将来のトラブルや社会的損失を防ぐ第一歩となるでしょう。

(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
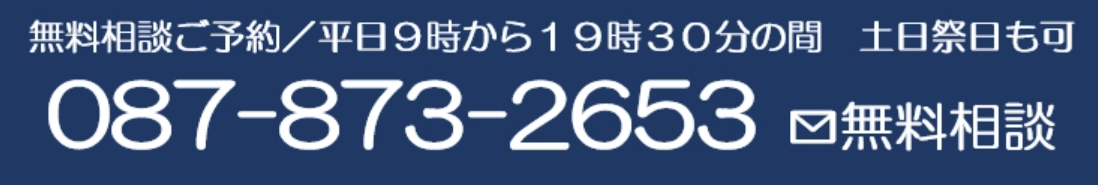
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。