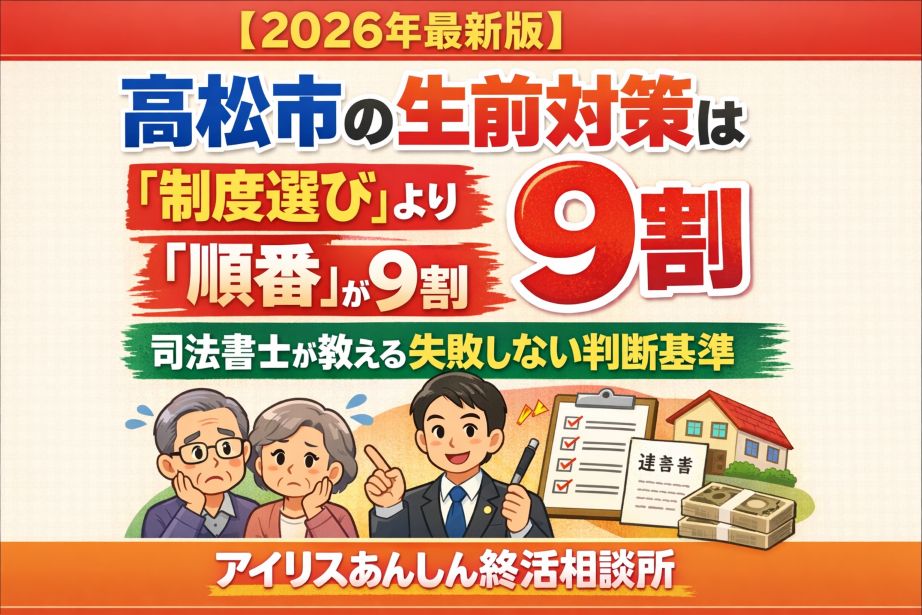高松市で生前対策を始めるなら、
「遺言書・認知症対策・相続登記」この3つを早めに準備することが最重要です。
第3回:香川県で考える生前対策|子どもが県外にいる家庭の相続準備 ― 地元に残る土地どうする?
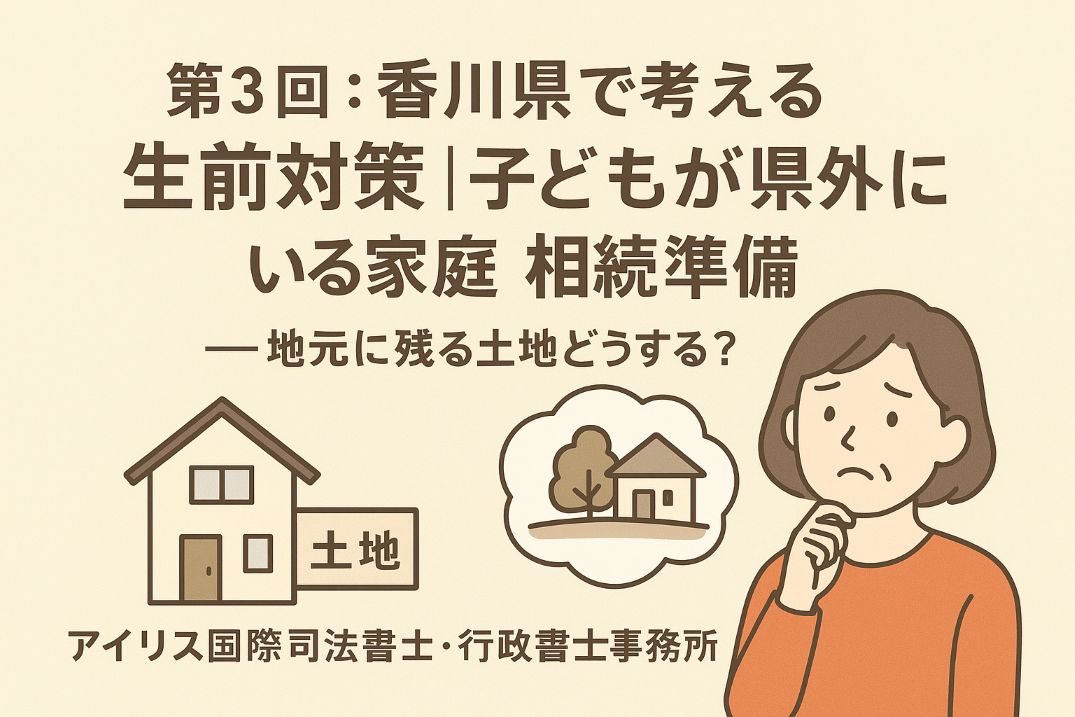
子どもが県外に出て暮らしている──香川県では今や珍しくない家族構成です。
しかし「親が亡くなった後、地元の土地や家をどうするか」で悩むご家庭は少なくありません。
この記事では、司法書士の視点から、県外の子ども世帯が"困らない相続準備"をわかりやすく解説します。
【目次】
- 子どもが県外に住む家庭で起こりやすい「相続の落とし穴」
- 地元の土地・空き家問題が深刻化する理由
- 香川県で実際にあった"相続後に動けない"ケース
- 認知症・登記義務化・相続放棄──放置のリスク
- 生前対策でできる「土地の整理と資金の準備」
- 家族が離れていてもできる3つの準備
- まとめ──"地元の財産"を「残す」か「整理するか」
1. 子どもが県外に住む家庭で起こりやすい「相続の落とし穴」

香川県では近年、「子どもが関西や関東に就職して戻らない」という家庭が増えています。
このとき、親が亡くなったあとに必ず問題になるのが**"地元の不動産"**です。
県外に住む子どもにとって、香川県内の土地や空き家は「すぐに使わない資産」でありながら、固定資産税や管理負担がかかる"負動産"にもなりかねません。
実際、
- 「空き家をどう処分すればいいかわからない」
- 「遠方で売却の立ち会いができない」
- 「兄弟間で意見が合わない」
といった相談が、司法書士事務所にも数多く寄せられています。
2. 地元の土地・空き家問題が深刻化する理由

香川県は全国的に見ても持ち家率が高く、空き家率も上昇傾向です。
特に三豊市・観音寺市・坂出市などでは、親の住まいが空き家になっても「解体費や登記費が負担」として放置されるケースが増えています。
しかし、放置しておくと以下のようなリスクが発生します:
- 雑草・老朽化による近隣トラブル
- 固定資産税や維持費の継続的な負担
- 相続登記義務化(2024年4月施行)への未対応で過料の対象
こうした状況を防ぐためにも、生前の段階で「残すか・整理するか」を明確に決めておくことが重要です。
3. 香川県で実際にあった"相続後に動けない"ケース
司法書士が関わった事例を一つ紹介します。
香川県内で一人暮らしをしていた母親が亡くなり、相続人の子どもは大阪に在住。
実家は築40年以上で、土地は母親名義のまま。
相続手続きを後回しにしていた結果、草木が伸び、近隣から苦情が寄せられた。
結果として、相続登記・固定資産税の支払い・売却まで約2年を要しました。
県外在住のため、書類の郵送・実印のやり取り・印鑑証明の取得などに時間がかかり、費用も想定以上に膨らんだのです。
このようなトラブルを防ぐためには、相続発生時の段階で整理を始めることが不可欠です。
4. 認知症・登記義務化・相続放棄──放置のリスク

親が元気なうちは問題ありませんが、認知症を発症すると不動産の売却・名義変更が一切できなくなります。
成年後見制度を使う場合も、裁判所の監督下に置かれるため、売却や契約に時間と制約が生じます。
さらに、2024年からは相続登記の義務化がスタート。
相続発生から3年以内に登記しないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。
「後でやろう」が通用しない時代です。
だからこそ、親が元気なうちに、子どもと一緒に財産の整理・登記・現金化の方針を話し合っておく必要があります。
5. 生前対策でできる「土地の整理と資金の準備」

地元の土地や建物をどうするかを決める際は、3つの視点で考えるのがおすすめです。
(1)使う予定があるか?
→ 将来帰る・活用する可能性がある場合は、名義を整理し維持管理計画を立てる。
(2)維持コストを払えるか?
→ 固定資産税・修繕費などが重荷なら、早めの売却・賃貸・寄付などを検討。
(3)売却資金をどう管理するか?
→ 預貯金に換えた場合、定期預金よりも普通預金にしておくことを推奨。
定期預金は本人しか解約できませんが、普通預金なら代理カードで引き出せる場合もあり、
万一の時に家族がすぐに資金を使える柔軟性があります。
香川県では、地域金融機関(百十四銀行・香川銀行など)でも高齢者の資産管理サポートを行っているため、
司法書士・銀行・不動産業者が連携して「実際に動かせるお金と資産のバランス」を整えるのが理想です。
6. 家族が離れていてもできる3つの準備

県外の子どもが多忙でも、以下の3つを押さえるだけで生前対策がスムーズになります。
- 不動産・預貯金の一覧を共有
どこに、何があるかを紙やエンディングノートにまとめておく。 - 代理権・後見契約を公正証書で整備
将来の判断力低下に備え、任意後見契約や家族信託を準備。 - 地元の司法書士・行政書士と連携
遠方でもオンライン相談を利用し、登記や契約の代理手続きを進める。
香川県ではZoomを利用した生前対策相談が増えており、県外からの相続準備も比較的スムーズに進められます。
7. まとめ──"地元の財産"を「残す」か「整理するか」
香川県に残る土地・家・田畑──それらは思い出の場所でもありますが、放置すれば"負担"に変わります。
子どもが県外にいるご家庭ほど、早めの話し合いと整理が大切です。
不動産・預貯金・名義・登記。
これらを「動かせるうちに動かす」ことで、家族に安心と選択肢を残せます。
司法書士は、そのサポート役として最適な制度設計を提案いたします。

【無料相談会のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
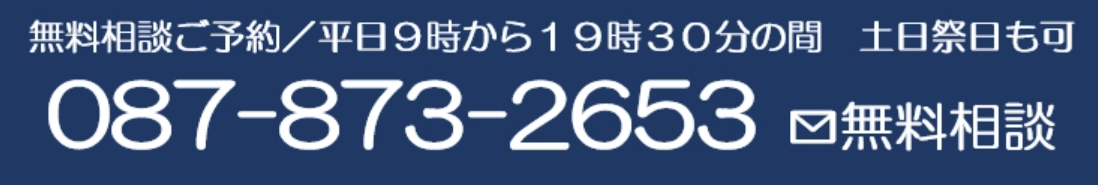
🌐 お問い合わせフォームはこちら
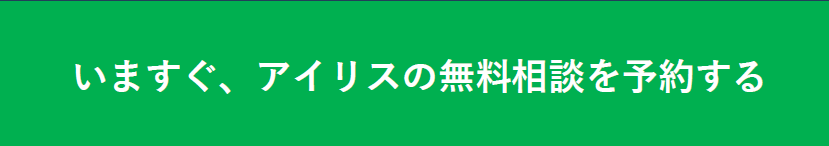
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外の方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記義務化
結論から言うと、丸亀市の生前対策は「いきなり専門家に依頼する」のではなく、行政の無料相談窓口+司法書士を併用する方法が最も失敗が少なく、費用も抑えられる進め方です。
認知症対策で最も大切なのは、実は「医療」ではありません。
生活費を止めないこと=お金の対策 です。
高松市で生前対策を考える方の多くが、最初にこう質問されます。
「遺言と家族信託、どっちがいいですか?」