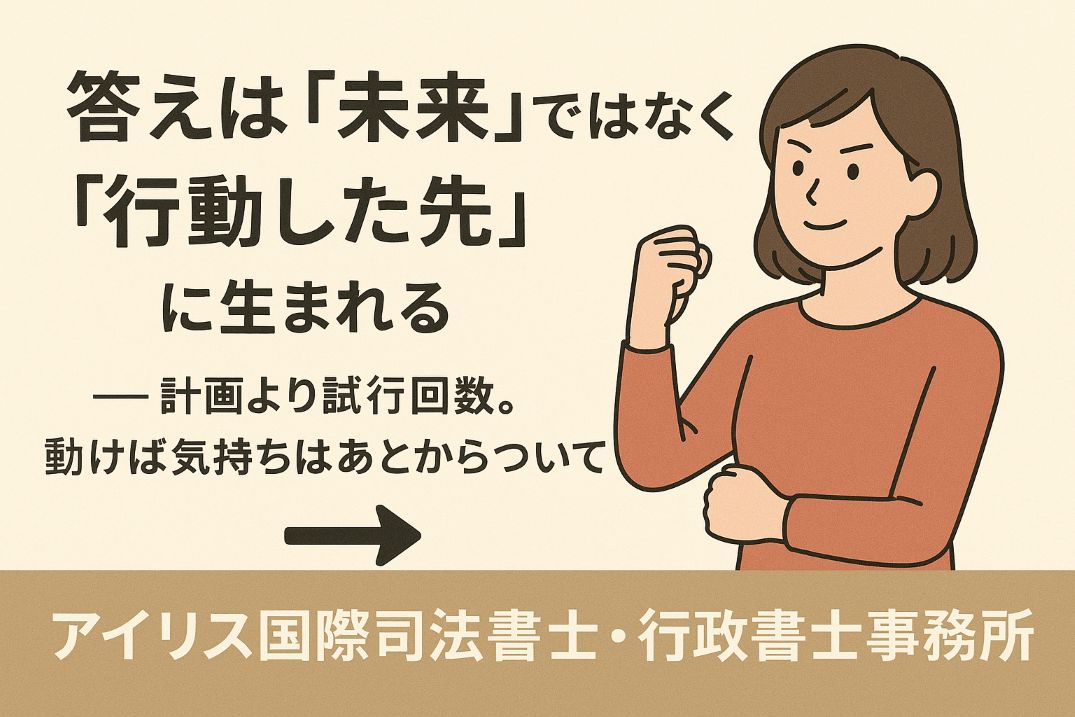相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(司法書士試験)午後問題の時間配分について

司法書士試験において、午後の択一試験は合否を左右する重要な要素です。特に午後のペース配分は、試験の進行に大きな影響を与えます。基本的な時間配分としては、午後の択一に1時間、不動産登記記述に1時間、商業登記記述に1時間を割り当てることが推奨されます。しかし、試験当日は予期しない事態が起こる可能性があり、択一で時間をオーバーしてしまうことも考えられるため、柔軟な対応力が求められます。そのため、事前に時間短縮の手法を考えておくことが重要です。
目次
1. 午後のペース配分
2. 全肢検討の原則
3. 問題を飛ばす選択肢
4. 軸肢検討の解き方
5. トレーニングと実戦的対策
1. 午後のペース配分

基本配分(理想)
午後の択一試験:1時間
不動産登記記述:1時間
商業登記記述:1時間
柔軟な対応の必要性
予期しない事態(択一で時間超過)が起きた場合に備え、時間短縮の手法を事前に検討しておく。
2. 全肢検討の原則

全肢検討の重要性
すべての選択肢をしっかりと検討し、正答を導くことが基本方針。
1時間内で全肢を確認する訓練が必要。
時間配分の難しさ
異常に長い文章問題や、登記簿の事例問題が出題されることもあり、解答に時間を要する場合がある。
全肢検討にこだわりすぎて、特定の問題に時間をかけすぎると、他の問題に時間が足りなくなるリスクがある。
3. 問題を飛ばす選択肢
飛ばすことの心理的負担
問題を飛ばすことも時間節約の一手段だが、後からの焦りや不安を招く可能性があるため、気持ちの良い方法ではない。
4. 軸肢検討の解き方

軸肢検討の手法
選択肢の中で、正誤が確実に判断できる選択肢を軸として、それをもとに他の選択肢の正誤を推測する方法。
全肢検討の代替として、時間がないときに効率よく解答を進める手段となる。
練習の必要性
軸肢検討は実戦で使うためには、日々の過去問や模試を通じたトレーニングが不可欠。
どの問題で軸肢検討を使うべきか、判断力を養うことも重要。
5. トレーニングと実戦的対策
時間を意識したトレーニング
模試や過去問を用いて、時間を意識した解答練習を行い、自分に合った最適なペース配分を身に付ける。
スピードと正確さのバランスを取りながら、軸肢検討を使うタイミングを体得する。
本番の準備
全肢検討を基本としつつ、時間不足になった場合に軸肢検討を活用できるよう準備することで、午後の試験を効率よく乗り切れる。
このように、各項目に分けてまとめることで、司法書士試験の午後択一対策のポイントが整理され、実践的な準備を進めやすくなるでしょう。
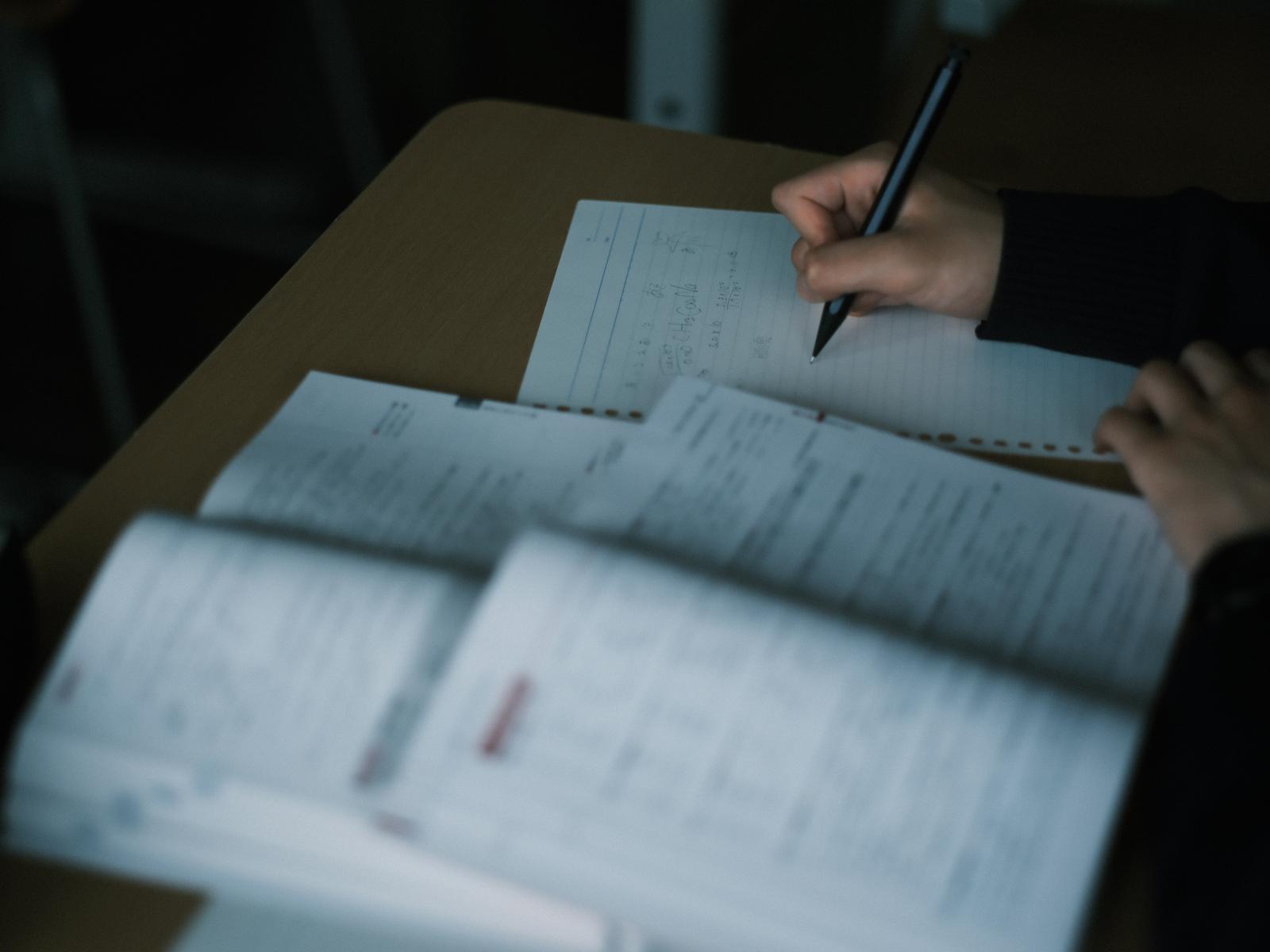
最新のブログ記事
【第4回】新年から一気に伸ばす!年内に整える環境・習慣・心構え
年が明けると「追い込み期」に突入します。その前に整えるべきは、環境・ルーティン・メンタルの3点。年内に準備しておけば、1月からスムーズにギアを上げられます。12月は"走り出す前の助走期間"。焦らず、でも確実に、自分の足場を固めましょう。
私たちは「もっと計画を立ててから」「もう少し気持ちが整ってから」と、行動を先送りにしてしまいがちです。しかし、心理学の研究でも明らかになっているのは、"やってみる"という小さな行動こそが、やる気や自信を呼び起こすという事実です。本稿では、未来を完璧に予測しようとするのではなく、「行動した先に答えが生まれる」という視点の大切さを、日常生活・仕事・学びの場面からひも解いていきます。
これからの生前対策で最も重要なのは、専門家だけで完結させないことです。
相続・終活・生活支援を「地域」とつなぐことで、実行性と安心感は大きく高まります。
2026年以降の生前対策は、「制度+人+地域」をセットで考える時代に入っています。