相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(司法書士試験)学習方法について考える

司法書士試験は難易度が高く、長期間にわたる学習が必要な資格試験です。合格を目指すためには、効果的な学習方法が重要です。ここでは、オーソドックスな方法から斬新なアイディアまで、司法書士試験の学習法についてまとめます。それぞれ中途半端にやったのでは、いつまでたっても合格は困難です。自分に合った学習方法を年内に見つけ、直前期、超直前期にぶれずに突き進むことで、合格への道は開けると思います。
目次
1. オーソドックスな学習方法
2. 効率を上げるための工夫
3. 斬新なアイディア
4. まとめ
1. オーソドックスな学習方法

① テキストを基にした基礎学習
まずは、テキストを使った基礎知識の習得が重要です。試験範囲は非常に広く、民法、不動産登記法、会社法、商業登記法など、多岐にわたる法律分野をカバーしています。それぞれの分野について理解を深めるため、初学者は体系的に学べるテキストを使い、全体の流れを把握することが求められます。
基礎学習では、各法律の条文と趣旨をしっかり理解し、具体例や判例を使って現実にどのように適用されるかをイメージすることが大切です。また、司法書士試験用の過去問や問題集を併用することで、知識の定着を図ります。
② 過去問を徹底活用
司法書士試験の問題形式は毎年変わらないため、過去問を繰り返し解くことは非常に有効です。特に、出題頻度の高い分野や問題パターンを把握することで、試験対策における時間効率を高められます。多くの受験生が使う学習法ですが、解いた後に必ず間違えた問題を復習し、なぜその答えが正しいのかを理解することが成功の鍵です。
③ 模試や答練を活用
試験前には、模擬試験や答練(答案練習)を積極的に活用します。本番に近い環境で時間配分を意識しながら問題を解くことで、実践的なスキルを磨くことができます。また、自己採点を行うことで、苦手な分野や弱点を把握し、試験までにそれらを補強することが可能です。
2. 効率を上げるための工夫
① スキマ時間の活用

司法書士試験は長期戦です。そのため、毎日の学習時間をいかに確保するかが重要です。通勤・通学の時間や昼休み、寝る前の短い時間を活用して、テキストやアプリを使った確認作業を行うことが効果的です。最近では、スマホで学習できるアプリや音声教材も充実しているため、忙しい社会人や主婦でもスキマ時間を有効活用することで、総学習時間を増やすことができます。
② ノートのデジタル化
紙のノートを使うことが一般的ですが、近年はデジタルノートを活用する受験生も増えています。タブレット端末やPCを使って効率的にメモを取り、検索機能で過去の内容を素早く見返すことが可能です。また、デジタルノートなら複数の端末で共有できるため、外出先でも学習が進めやすくなります。
3. 斬新なアイディア
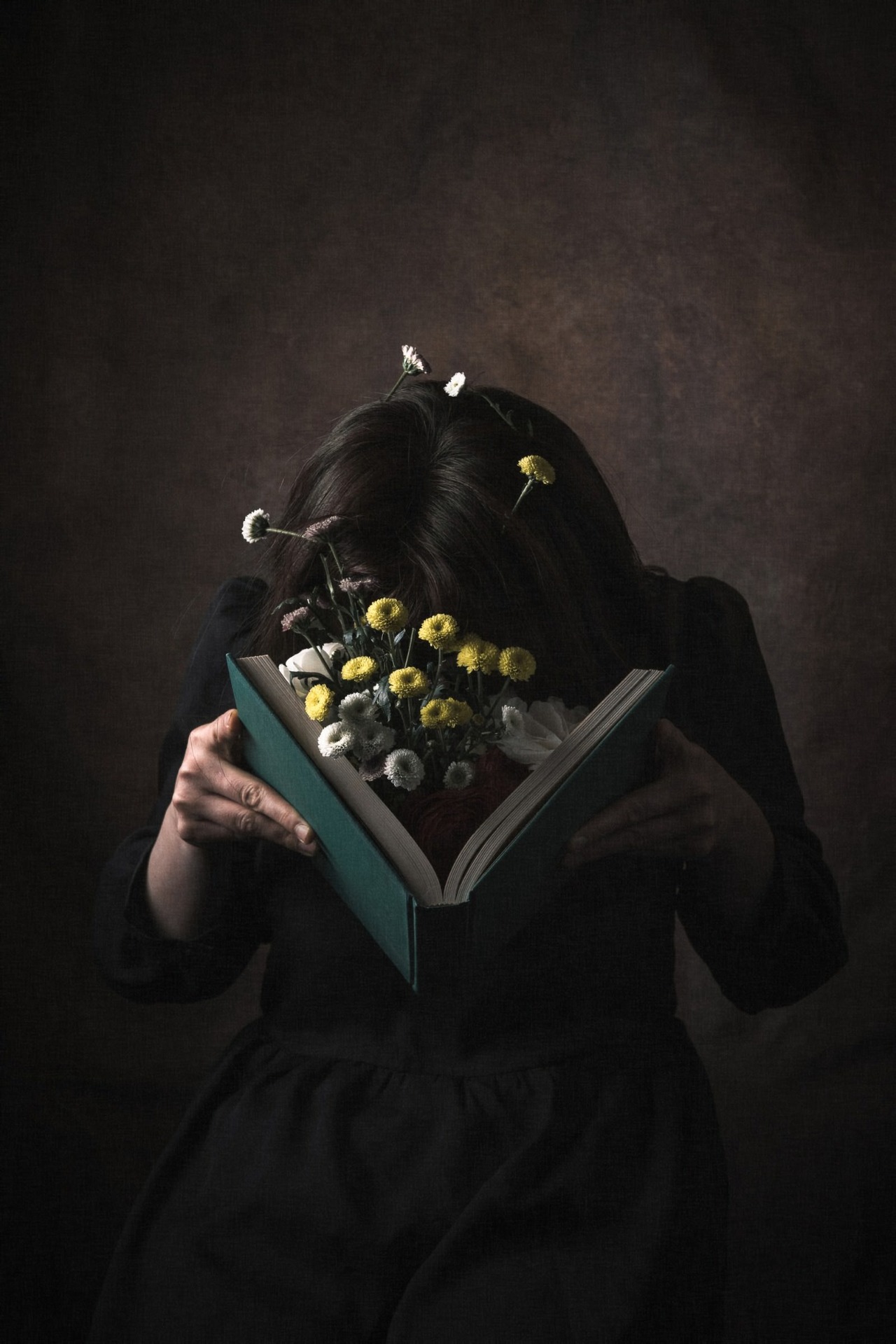
① マインドマップを活用した学習
司法書士試験の範囲は膨大で、それぞれの法律がどのように関連しているかを理解することが重要です。そこで、マインドマップを活用することが効果的です。マインドマップは中心から放射状にキーワードや関連事項を視覚的に整理できるツールで、民法や商業登記法など各科目の重要事項をつなげて整理できます。視覚的に関連性を把握しやすくなるため、複雑な法律の相関関係を一目で理解でき、復習もしやすくなります。
② グループ学習やディスカッション
個人での学習に加え、仲間と一緒に学ぶことで理解が深まります。オンラインでのグループ学習や勉強会に参加し、お互いに問題を出し合ったり、ディスカッションをすることで、他の人の視点や考え方を取り入れられます。特に、自分では気づけなかった盲点や誤った理解を修正するのに役立つため、積極的に取り入れてみる価値があります。
③ メンタル強化のためのビジュアライゼーション
試験に挑むためには、知識の習得だけでなく、メンタルの強化も欠かせません。斬新な学習法として「ビジュアライゼーション」があります。これは、合格している自分を具体的にイメージすることで、潜在意識に自信を植え付ける方法です。日々の学習の中で、自分が司法書士試験に合格し、その後のキャリアを歩む姿を具体的に思い描くことで、モチベーションを高め、試験本番での自信につなげます。
4. まとめ
司法書士試験に合格するためには、オーソドックスな学習法をベースにしながら、自分に合った工夫や斬新なアイディアを取り入れることが重要です。基礎をしっかり固めた上で、効率的な学習方法を模索し、仲間とのディスカッションやマインドマップなどを活用して、知識の整理と定着を図りましょう。また、メンタル面の強化にも気を配り、合格に向けた道のりを歩んでいくことが求められます。試験に向けた準備期間を有効に活用し、合格を手に入れるための計画的な学習を心がけましょう。
できれば年内に学習方法を試し、自分に合った学習方法を見つけ出しておき、直前期以降に余すところなく使い切るといった方法がいいと思います。
すべては、将来、信頼してもらえる司法書士になるためです。頑張って。

最新のブログ記事
「親が認知症になっただけで、銀行口座が凍結されるなんて信じられない」
多くの方がそう思います。しかし実務の現場では、認知症=お金が使えなくなるという事態が毎日のように起きています。
実はこれは銀行の意地悪でも、融通のなさでもなく、法律でそうなっているからです。
そして何より怖いのは、「介護が始まってからでは、もう手遅れ」だということ。
この記事では、なぜ口座が止まるのか、家族がどんな状況に追い込まれるのか、そしてどうすれば凍結を防げるのかを、司法書士の実務視点でお伝えします。
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。



