【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。

「認定特定創業支援等事業」(にんていとくていそうぎょうしえんとうじぎょう)は、日本政府や自治体が提供する創業支援の一環として、中小企業や新規事業者の立ち上げをサポートするための制度です。この制度の一つの大きな利点は、会社設立時の登録免許税が半額になる点です。以下、その概要について説明します。
目次
1. 認定特定創業支援等事業とは
2. 支援内容
3. 登録免許税の減免措置
4. 減免を受けるための条件
5. 他の優遇措置
まとめ
1. 認定特定創業支援等事業とは

「認定特定創業支援等事業」は、地方自治体や商工会議所などが提供する創業支援プログラムの一部です。この制度を活用することで、起業家が事業計画や経営の基本的な知識を学ぶ機会が提供され、また、行政手続きにおいても様々な優遇措置を受けることができます。
2. 支援内容
この制度を利用することで、起業家は以下のような支援を受けることができます。
事業計画の作成支援:ビジネスプランの策定を手助けする専門家によるサポート。
経営や財務の知識提供:起業に必要な財務、税務、法務、労務などの基本的な知識を提供。
交流の場の提供:他の起業家や事業家とのネットワーキングイベントやセミナーの開催。
3. 登録免許税の減免措置
最大の利点の一つは、会社を設立する際の「登録免許税」が半額になることです。通常、株式会社設立時には資本金の0.7%を登録免許税として納める必要がありますが、この支援を受けることで、0.35%に軽減されます。例えば、資本金1,000万円の会社を設立する場合、通常の登録免許税は7万円ですが、支援を受けることで3.5万円となります。
4. 減免を受けるための条件
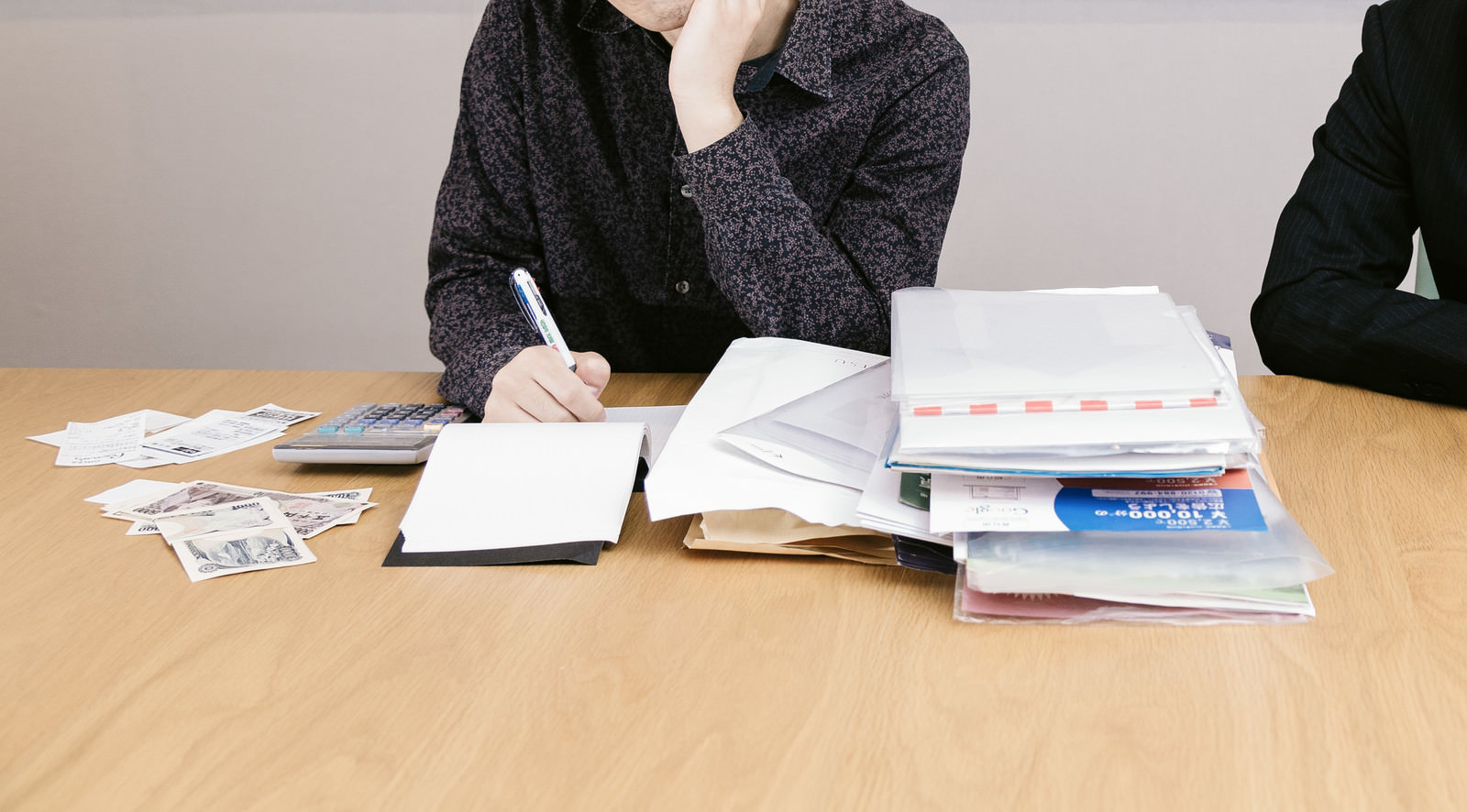
この制度を利用して登録免許税の減免を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
特定の自治体による認定を受けること:創業支援事業を行っている自治体において、その創業支援プログラムを受け、自治体から「特定創業支援等事業を受けた証明書」を発行してもらうこと。
一定の内容の支援を受けること:支援内容として、財務、経営、労務、販路開拓など複数の分野について1か月以上の期間、合計で4回以上の支援を受ける必要があります。
5. 他の優遇措置
「認定特定創業支援等事業」を利用することで、登録免許税の減額以外にも以下のような優遇措置を受けることができます。
信用保証枠の拡大:創業者に対する信用保証枠が拡大され、資金調達がより容易になります。
各種税制優遇:所得税や法人税の軽減措置を受けることが可能です。
まとめ
「認定特定創業支援等事業」は、創業に必要な知識を学びながら、会社設立時のコスト削減や信用保証の拡充などの様々な優遇措置を受けることができる非常に有益な制度です。特に、登録免許税が半額になるという大きなメリットがあるため、これから起業を考えている方は、ぜひこの制度を活用して効率的なスタートを切ることを検討してみてください。
利用を検討する場合は、自治体のホームページや商工会議所などで詳細を確認し、必要な手続きや支援プログラムへの参加を進めることが重要です。

「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。
「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。
法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。
一般社団法人の設立は、非営利法人として社会貢献活動や専門家団体の運営、業界組織の立ち上げなどを行いたい方にとって、有力な選択肢です。株式会社のような出資者がいなくても法人格を持てる点や、比較的簡易な設立手続きが魅力です。