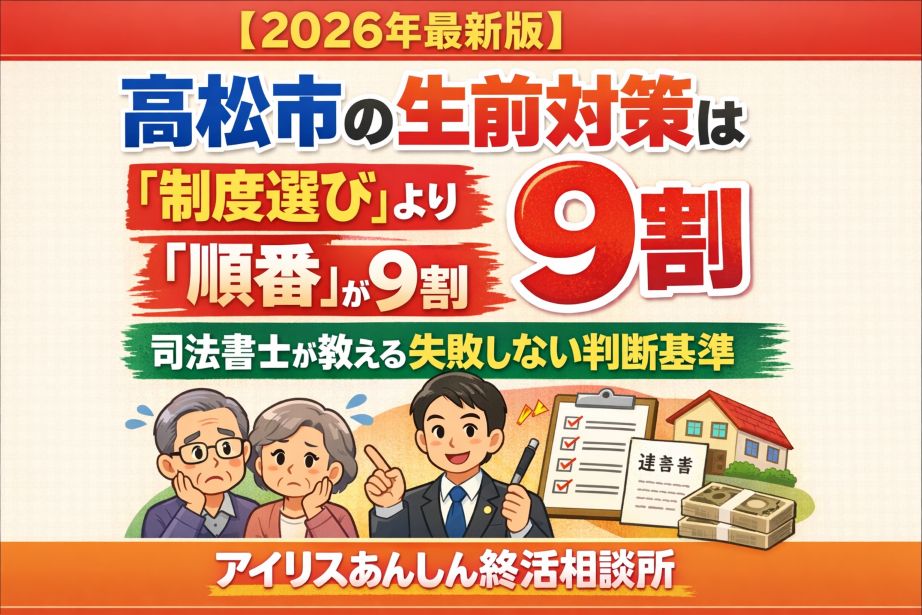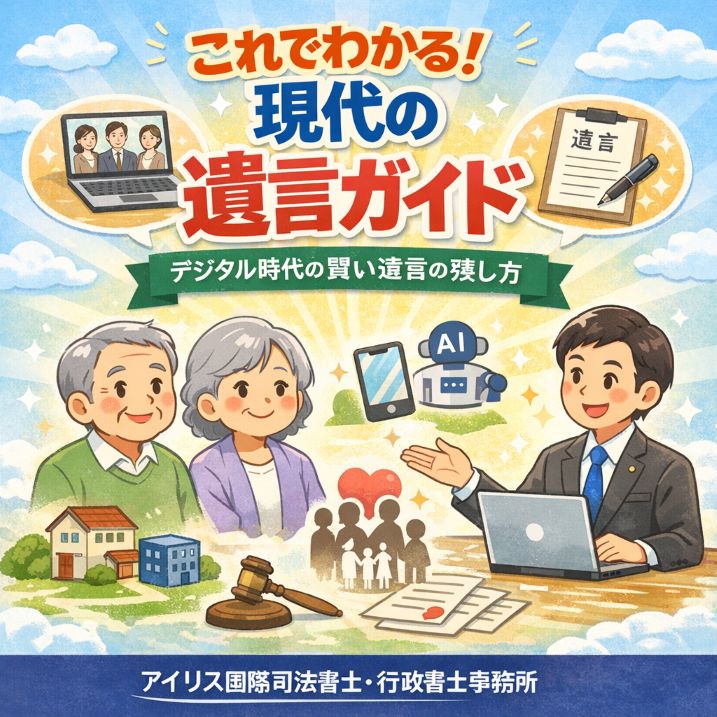相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(論点)一申請情報申請によって申請をすることの可否(共同根抵当権変更登記申請について)
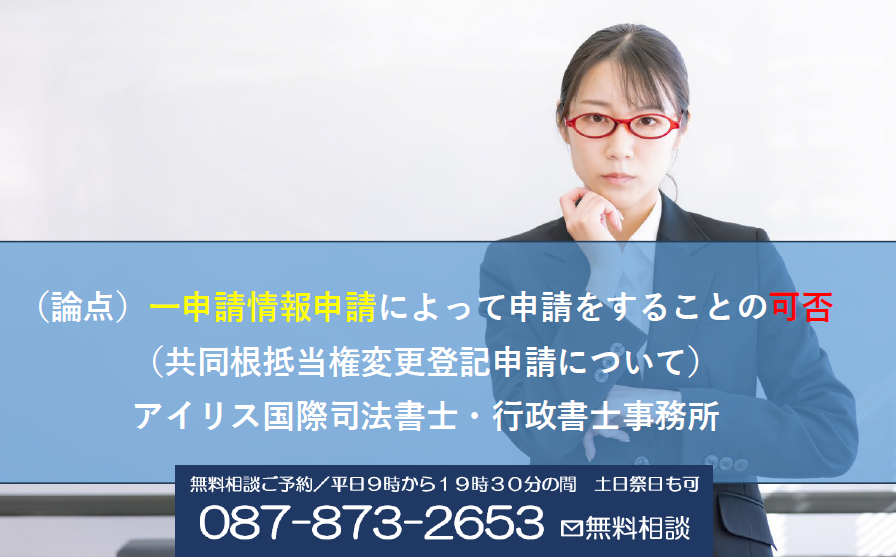
既に設定された共同根抵当権について、変更登記のご依頼がありました。概略は、債権の範囲の変更と、債務者に法人を追加する変更という内容でした。変更の内容は、2つでありますが、一つの変更申請書で登記をすることができるのでしょうか。少し解説したいと思います。
目次
1.共同根抵当権で、2つの項目を変更する場合
2.司法書士作成の報告形式の登記原因証明情報をする場合
3.今回のケースについて(契約書が2通)
4.一申請情報申請の要件
5.まとめ
1.共同根抵当権で、2つの項目を変更する場合

通常ですと、金融機関から司法書士に共同根抵当権の変更登記申請の依頼と併せて、「根抵当権変更契約書(債権の範囲の変更及び債務者の追加変更)」を作成してもらえないかということで話があります。ですので、登記原因証明書として提出する契約書の内容は、登記の申請内容に則したものとなります。登記原因証明情報は1通ですので、形式上も問題なく1つの申請で申請することが可能です。また、契約書に不動産の表示も含まれますので、物件印字も契約書作成の段階で記載することができます。
2.司法書士作成の報告形式の登記原因証明情報をする場合
今回のように変更登記申請の内容を取りまとめ、権利者・義務者の記名押印及び不動産の表示等の法令上の要件を充たした内容となっていることが必要です。この「報告形式の登記原因証明情報」は、登記申請としては有効です。しかし、「原本還付されない」という難点があります。報告形式の登記原因証明情報は、法務局に差し入れてしまうことになりますので、当然、金融機関と設定者間の契約書は必要となります。それだったら初めから、一つの契約書に取りまとめておいた方がいいということで、私の経験上では、ほとんど取り扱ったことはありません。
3.今回のケースについて(契約書が2通)
今回のケースについては、「根抵当権変更の契約書様式があるので、契約書記載後お渡しをして、その後物件印字等をすることになりました。変更登記申請後に、融資の実行が控えており、この点も考慮しなければなりません。
実行日の前日に書類を預かりに行きました。「登記原因証明情報」としての「共同根抵当権変更契約書」が、債務者のものと、債権の範囲の変更のものと2通ありました。変更の契約日は双方合わせていました。
ここで改めて「一申請情報申請」の要件について確認しました。
4.一申請情報申請の要件

「同一登記管轄区域の数個の不動産につき同一の申請情報で登記申請することが認められるもの」とあります。わかりやすく見ていきますと
①管轄登記所が同一であること ※あります
➁登記の目的が同一であること ※共同根抵当権の変更です
③登記原因及びその日付が同一であること ※年月日変更です(先例では共同根抵当権の場合、日付が異なっていてもできるとの先例があります)
④申請人が同一であること
※所有者が土地と建物で異なっている(抵当権の抹消登記の場合では、先例がある)
いくつか不安要素はあるものの、先例などを短時間で調べ上げて、申請書を提出しました。勿論、登記原因証明情報は、2通の契約書で「原本還付手続」をしました。
5.まとめ
登記手続きが完了する前に、登記官の方から連絡がありました。「先生もご存知の通り・・・・・」という内容でしたが、通常は「契約書」は司法書士で作成していたが、今回は金融機関所定の要式での対応となったことと、共同根抵当権の場合、原因日付が同じではなくても申請ができるが、今回の申請は登記原因証明情報が2通となってしまっているため、日付は統一させていただいた旨をしっかりお話をさせて頂きました。
「まあ、今回のところは、」というところで、何とかなりました。
次回からは、金融機関とお役様との間の契約書は作成していただきとして、司法書士側から、変更内容の登記原因証明情報として、報告形式の登記原因証明情報の作成の提案をさせて頂こうと思いました。

最新のブログ記事
高松市で生前対策を考える方の多くが、最初にこう質問されます。
「遺言と家族信託、どっちがいいですか?」
第1回|日本の遺言制度の基本 ― まずは「種類」とそれぞれの特徴を正しく知る ―
結論から言うと、遺言は「種類の違い」を理解しないまま作成すると、かえって相続トラブルの原因になります。
日本には複数の遺言方式がありますが、実務で使われるのは主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
本記事では、遺言制度の基本から、それぞれの特徴・効力・注意点までを整理し、「自分にはどの遺言が合うのか」を判断できる土台をつくります。
高松市生前対策|空き家・相続登記義務化を乗り越える実践7ステップ【司法書士が解説する完全ガイド】
結論から言うと、高松市の生前対策は「空き家対策」と「相続登記義務化」への備えを軸に、元気なうちに7つの準備を進めることが最短ルートです。
実際、相続発生後に慌てて手続きを始めるご家庭の多くが「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔されています。