相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(論点)労災と第三者行為のはなし
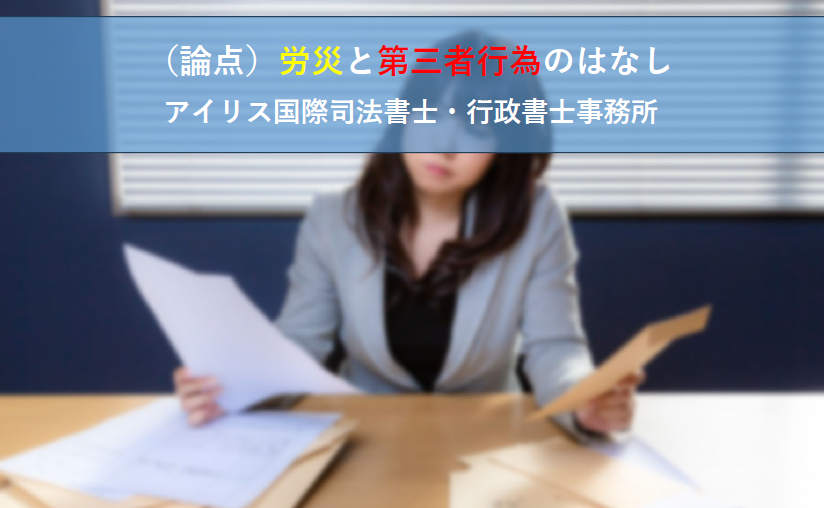
労災(労働災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に事故や災害に遭い、怪我をしたり病気になったりした場合に、治療費や休業補償を受けることができる制度です。しかし、労災事故には、会社や労働者以外の第三者が関与している場合もあります。このようなケースを「第三者行為による労災」といい、通常の労災事故とは異なる点がいくつかあります。
目次
1. 第三者行為とは
2. 労災保険と損害賠償請求
3. 労災と第三者行為の手続き
4. 第三者行為による労災の具体例
5. 第三者行為の注意点
6. まとめ
1. 第三者行為とは
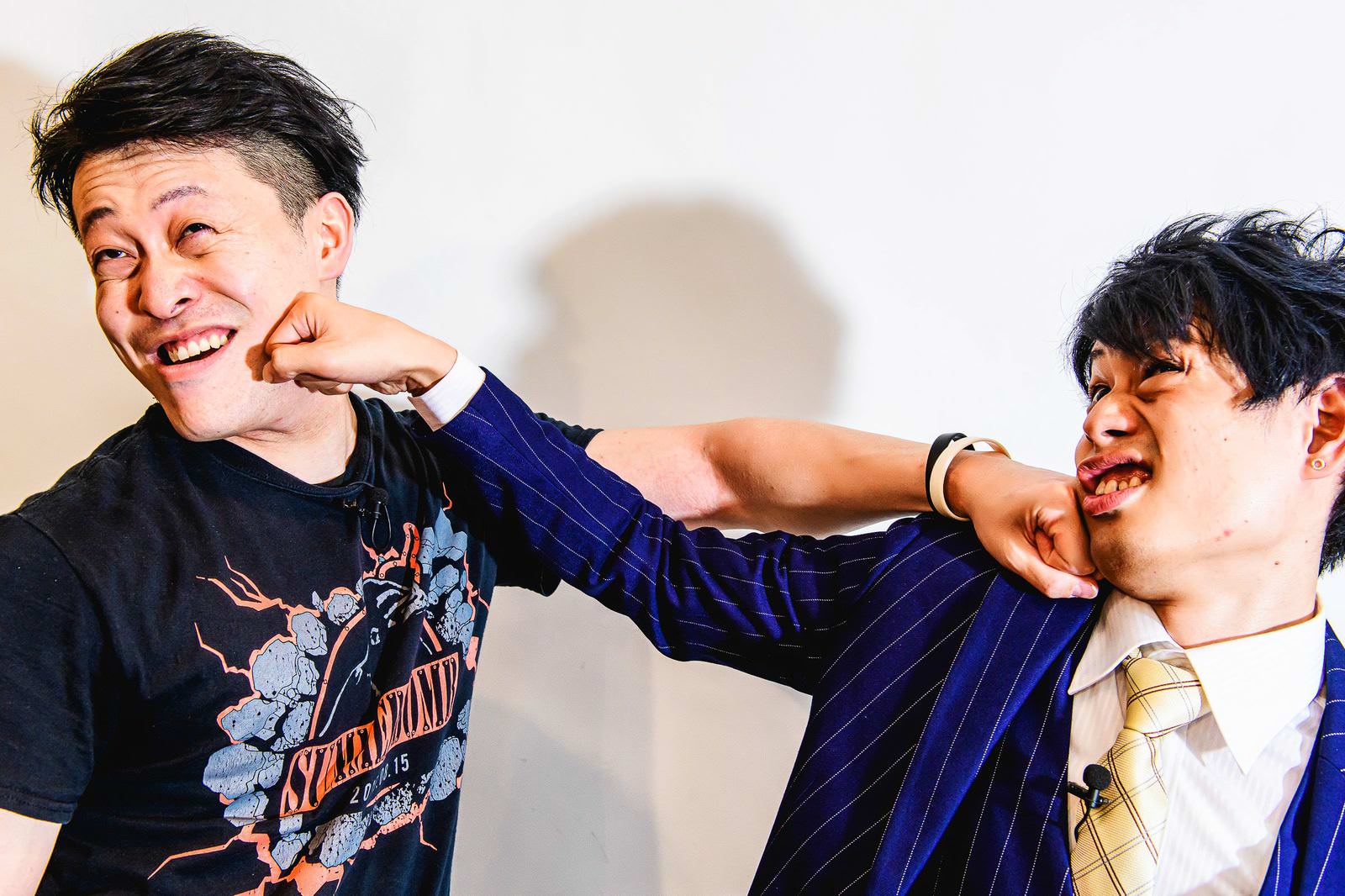
第三者行為とは、労働者が業務中または通勤中に、労働者や会社以外の人や企業(第三者)による行為で怪我をしたり病気になったりすることを指します。たとえば、通勤中に交通事故に遭い、加害者が労働者やその雇用主とは無関係な場合や、業務中に他社の過失で事故が発生した場合が該当します。
このような場合、通常の労災と同様に、労災保険から治療費や休業補償を受けることができますが、第三者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
2. 労災保険と損害賠償請求

第三者行為による労災事故では、労災保険を利用するか、第三者に直接損害賠償請求をするかの選択肢があります。労災保険を利用する場合、労働者は治療費や休業補償などの一定の補償を迅速に受けることができますが、その後、第三者に対して損害賠償請求を行う際には、労災保険で支払われた分は重複して請求できないという制約があります。
具体的には、労災保険を利用して支払われた治療費や休業補償は、労災保険側が第三者に「求償権」を行使することで回収します。このため、労働者が第三者に直接損害賠償請求を行う際には、労災保険で受けた補償を差し引いた分を請求することになります。
一方、労災保険を利用せず、第三者に直接損害賠償請求を行うことも可能です。ただし、この場合は、労災保険の迅速な補償を受けられないため、賠償が確定するまでの間、治療費や生活費の負担が大きくなる可能性があります。
3. 労災と第三者行為の手続き
労災保険を利用する場合、通常の労災申請と同じ手続きを行います。ただし、第三者行為による場合には、追加で「第三者行為災害届」を提出する必要があります。この届出は、労働基準監督署や労働局に提出され、事故の詳細や第三者の情報を明らかにするためのものです。
届出が受理されると、労災保険から治療費や休業補償が支払われますが、労災保険側が第三者に対して求償権を行使し、労災保険で支払った分を第三者に請求します。これにより、労働者は迅速に補償を受けつつ、第三者に対しても責任を追及することが可能となります。
4. 第三者行為による労災の具体例
具体的な例として、通勤中の交通事故が挙げられます。労働者が通勤中に他の車と衝突し、その車の運転手に過失があった場合、労災保険の通勤災害として治療費や休業補償を受けることができます。同時に、その事故の加害者に対して、慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求を行うこともできます。
また、業務中に他社の過失で事故が発生した場合も同様です。例えば、建設現場で他社の重機が倒れて負傷した場合、その重機を運営していた企業に対して損害賠償請求を行うことが可能です。このような場合でも、労災保険を利用して補償を受けつつ、第三者に対して損害賠償請求を行うことができます。
5. 第三者行為の注意点

第三者行為による労災の場合、注意すべき点がいくつかあります。まず、労災保険を利用する場合、第三者に対して損害賠償請求を行う際に、労災保険で支払われた分を差し引いた額しか請求できない点です。これは、労災保険が既に支払われた補償分を第三者に請求するため、重複して補償を受けることができないという仕組みに基づいています。
また、労災保険を利用せず、第三者に直接損害賠償請求を行う場合、賠償が確定するまでの間、生活費や治療費の自己負担が大きくなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。労災保険の迅速な補償を受けることで、経済的な負担を軽減できるため、多くの場合は労災保険を利用することが一般的です。
6. まとめ
第三者行為による労災事故では、労災保険と損害賠償請求の両方を利用することが可能です。労災保険を利用することで迅速に補償を受けられますが、第三者に対して損害賠償請求を行う際には、労災保険で支払われた分を差し引く必要があります。第三者行為災害届の提出や、求償権の行使など、通常の労災とは異なる手続きが必要なため、適切な手続きを踏んで、迅速に補償を受けることが大切です。

最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。



