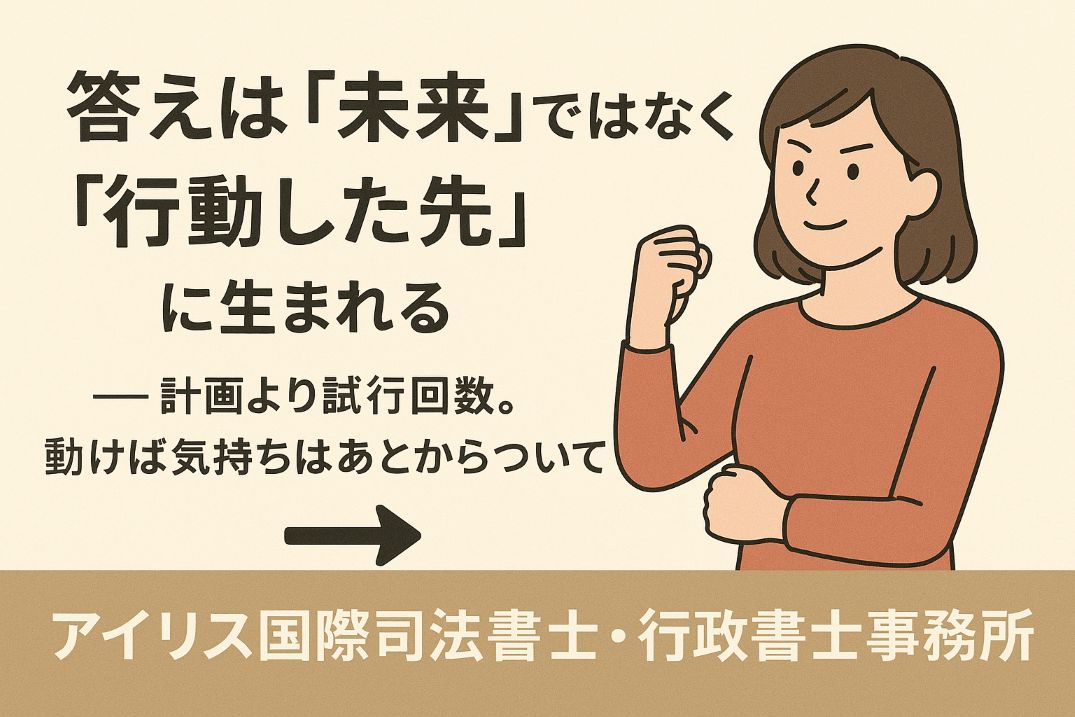相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(論点)相続対策における養子縁組と財産減少の法的・税務的側面(注意すべきポイント)

相続対策の一環として、財産を減らす方法や、養子縁組を活用して法定相続人の数を増やすことが一般的に行われます。しかし、法律上と税務上では異なる基準が存在し、それらを理解せずに対策を講じると、思わぬ結果になることも少なくありません。本記事では、養子縁組による法定相続人の増加と財産を減らす方法に焦点を当て、相続対策を進める際に気を付けるべき法的・税務的側面を解説します。
目次
- 財産を減らすことによる相続対策
- 養子縁組による法定相続人の増加
- 法律上と税務上の違い:養子縁組の制約
- 専門家に相談する際の注意点
- まとめ
1. 財産を減らすことによる相続対策
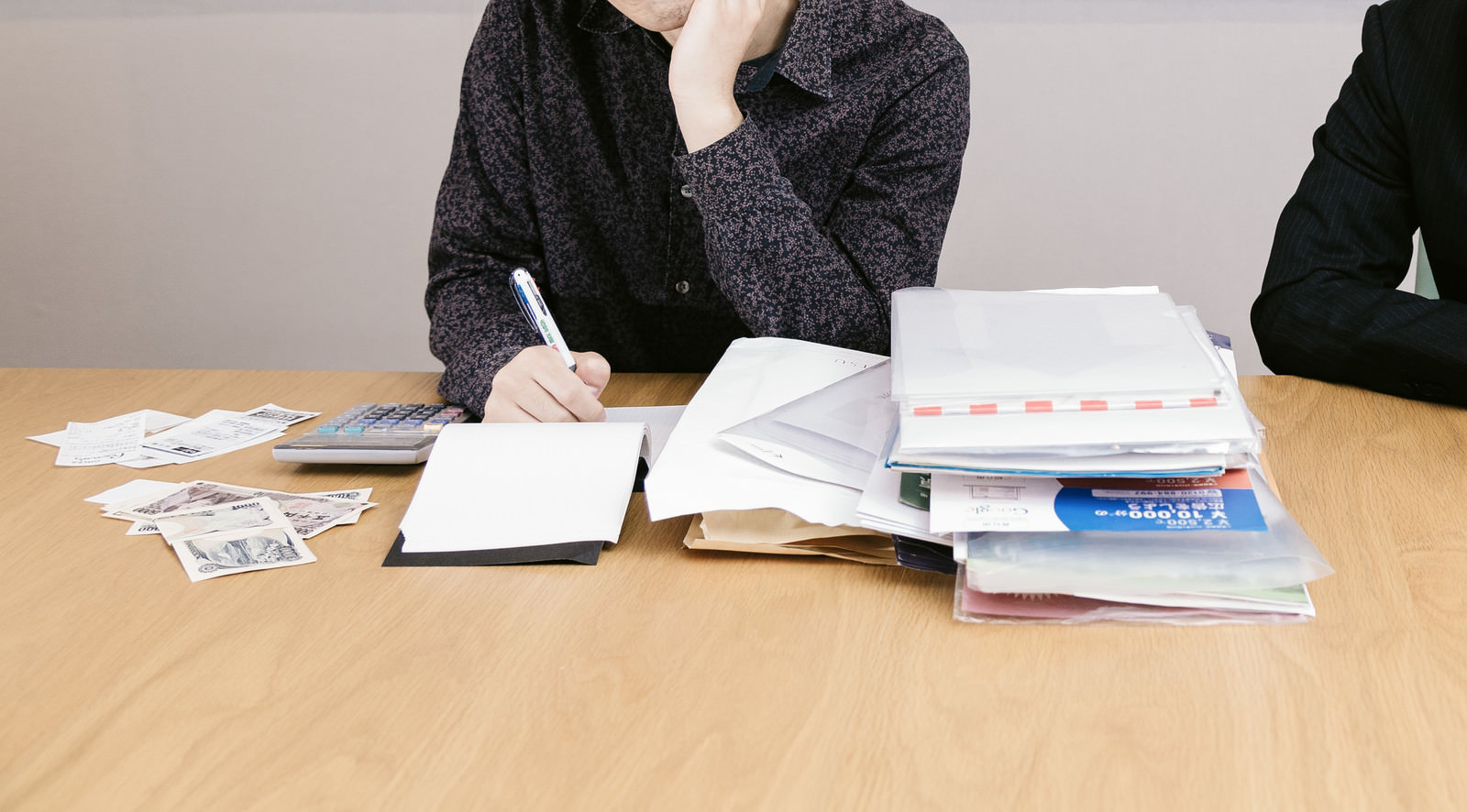
相続税対策の基本的な考え方として、財産の額を減らすことがあります。財産を減らす方法として一般的なのが、生前贈与です。毎年110万円まで非課税で贈与できるため、この制度を活用して計画的に財産を減らしていくことが可能です。
また、親族や信頼できる第三者に財産を信託する家族信託の方法もあります。家族信託では、被相続人が存命中に財産の管理を委ね、亡くなった際に遺産として相続人に渡る財産を計画的に減らすことができます。このように、生前から少しずつ財産を減らしておくことで、相続時の財産規模を小さくし、相続税の負担を軽減することが可能です。
2. 養子縁組による法定相続人の増加

相続対策の一つに、養子縁組を行うことで法定相続人を増やし、相続税の基礎控除額を増やす方法があります。相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」という計算式で決まるため、養子を迎えて法定相続人を増やすことで基礎控除額を増やすことができます。
例えば、被相続人に子供がいない場合、養子を迎えることで法定相続人の数が増え、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。しかし、養子縁組はただ法定相続人を増やすだけでなく、家庭の状況や相続人の意向を十分に考慮して行う必要があります。
3. 法律上と税務上の違い:養子縁組の制約
ここで注意すべきなのが、法律上の養子縁組と税務上の取り扱いが異なる点です。法律上、養子縁組は制限がなく、何人でも養子を迎えることができます。しかし、税務上の相続税計算における法定相続人の数には制限があります。
税務上の規定では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか、基礎控除の計算において養子縁組を考慮することができません。したがって、実子がいない夫婦が養子を3人迎えた場合でも、相続税の基礎控除を計算する際に考慮できるのは2人までとなります。
この税務上の制約を知らずに、多くの養子を迎えることで相続税を大幅に軽減しようと考えても、期待した効果は得られません。そのため、養子縁組を相続対策として活用する際には、この法律上と税務上の違いを十分に理解しておくことが重要です。
4. 専門家に相談する際の注意点

相続対策を進める際、多くの方が税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談します。しかし、専門家のアドバイスが全て万全とは限らず、法的な側面だけでなく、税務的な側面も十分に考慮していなければ「こんなはずではなかった」という結果になりかねません。
例えば、法律に詳しい専門家が養子縁組を無制限に勧めたとしても、税務上の制約については考慮されていなければ、後々予想以上の相続税が課されることもあります。逆に、税務の専門家が提案した節税対策が、法的には家族間のトラブルを引き起こすリスクがあることもあります。
そのため、相続対策を行う際には、法律と税務の両方に精通した専門家に相談するか、双方の専門家が集まる相談会で、総合的な視点でアドバイスを受けることが重要です。さらに、家族の意向や財産の種類など、個別の事情を反映した対策が求められます。
※アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、月一で「相続法律・税務無料相談会」を実施しております。税務の相談も必要と判断した場合、そちらの相談会へ誘導するようにしております。
5. まとめ
相続対策は、財産の減少や法定相続人の増加を目的に多様な手法が存在しますが、それぞれには法律上と税務上の違いがあることを理解しておく必要があります。特に養子縁組を活用した相続税対策では、税務上の制約により、思ったような効果が得られない場合もあるため注意が必要です。
また、専門家に相談する際も、法律面だけでなく税務面についても十分に検討することが大切です。相続対策は、単なる節税やトラブル防止にとどまらず、家族の将来を見据えた計画的な準備が求められます。最適な対策を講じるためには、専門家の意見を尊重しつつ、自分自身も十分な知識を持って準備を進めることが重要です。

最新のブログ記事
「親が元気なうちは、まだ相続のことは考えなくていい」
そう思っている方が非常に多いのですが、実務の現場では認知症になった瞬間に、不動産は"事実上ロックされる"という事態が日常的に起きています。
しかも2024年から始まった相続登記義務化により、「登記できない家」は法律違反のリスクまで背負う時代になりました。
結論から言えば、不動産の相続対策は"認知症になる前"にしかできません。
この記事では、なぜそう言い切れるのかを、法律と現場の両面から解説します。
【第4回】新年から一気に伸ばす!年内に整える環境・習慣・心構え
年が明けると「追い込み期」に突入します。その前に整えるべきは、環境・ルーティン・メンタルの3点。年内に準備しておけば、1月からスムーズにギアを上げられます。12月は"走り出す前の助走期間"。焦らず、でも確実に、自分の足場を固めましょう。
私たちは「もっと計画を立ててから」「もう少し気持ちが整ってから」と、行動を先送りにしてしまいがちです。しかし、心理学の研究でも明らかになっているのは、"やってみる"という小さな行動こそが、やる気や自信を呼び起こすという事実です。本稿では、未来を完璧に予測しようとするのではなく、「行動した先に答えが生まれる」という視点の大切さを、日常生活・仕事・学びの場面からひも解いていきます。