相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第1回】「遺言は書いただけでは不十分?──“形式”が運命を分ける」
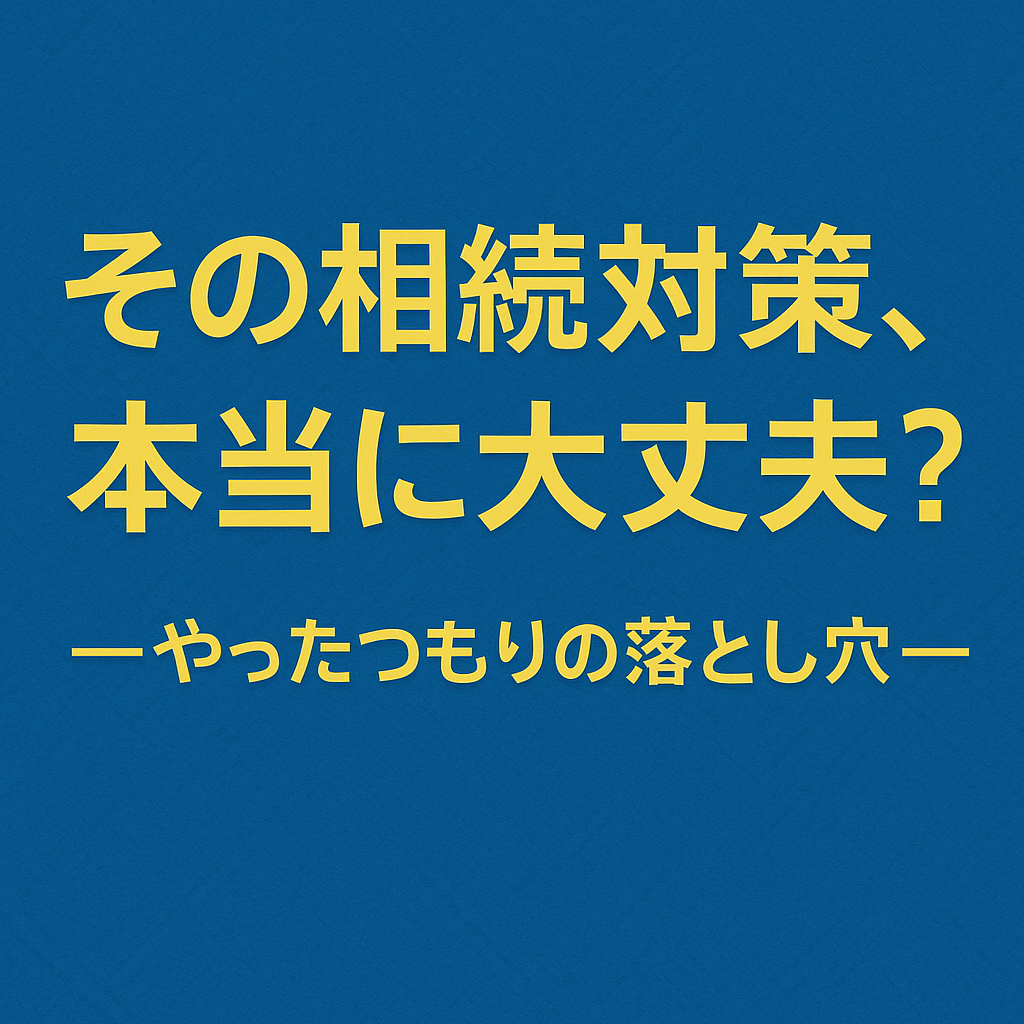
「遺言書を書いておけば相続は安心」と思っていませんか?実は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言の"形式"によって、相続手続きの手間やリスクが大きく変わるのです。特に、家庭裁判所の検認手続きが必要となる自筆証書遺言は、手続きに時間がかかるうえに、無効になるケースもあるため注意が必要です。本記事では、遺言の種類ごとの特徴と、相続を円滑に進めるために知っておくべきポイントを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
【目次】
- 遺言は"書いたら安心"ではない
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- 検認手続きが相続を遅らせる理由
- 無効になってしまう自筆遺言の事例
- 公正証書遺言を選ぶメリットとは
- 遺言保管制度はどこまで使えるのか
- まとめ:形式を軽視した遺言は、家族を困らせる
1. 遺言は"書いたら安心"ではない

「父が遺言を残していたので安心しました」
——相続の現場では、よくこうした声を聞きます。
しかし、その遺言が**"自筆"によるもので、法的な要件を満たしていなかった場合**、その安心は一瞬で不安に変わります。
相続対策として遺言を残すことは非常に重要ですが、その形式と内容を正しく理解していないと、かえって相続手続きを混乱させる原因になります。
2. 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言にはいくつかの種類がありますが、特に一般的なのは次の2つです。
- 自筆証書遺言:本人がすべて手書きで作成する遺言
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管される遺言
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的な不備があると無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、法的にしっかりした形で残せるのが大きなメリットです。
3. 検認手続きが相続を遅らせる理由

自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
これは、遺言の内容を確認し、改ざんがされていないかをチェックする手続きですが、この検認が終わらない限り、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きが進められないのです。
検認には、申立書類の準備や相続人全員への通知、家庭裁判所からの呼び出しなど、数週間から数ヶ月の時間がかかることもあります。
「遺言があるのに相続が進まない」という、思わぬ落とし穴です。
4. 無効になってしまう自筆遺言の事例

たとえば、以下のようなケースでは、自筆証書遺言が無効となる可能性があります。
- 日付が「令和〇年〇月吉日」となっている(不特定な日付)
- 一部をワープロで印刷している
- 遺言内容があいまいで解釈が分かれる
- 相続人の名前がフルネームでなく、特定できない
このように、本人はきちんと遺言を書いたつもりでも、法的に有効と認められないケースが非常に多く存在します。
5. 公正証書遺言を選ぶメリットとは

公正証書遺言は、公証人が法律に則って作成し、本人と証人2名の前で確認されます。そのため、形式的な不備が起こることはまずありません。また、遺言の原本は公証役場に保管され、相続発生後は検認不要で、すぐに相続手続きを進めることが可能です。
費用の目安としては、内容によりますが1万〜数万円程度が相場です。安心と確実性を買うと考えれば、十分妥当な投資といえるでしょう。
6. 遺言保管制度はどこまで使えるのか

2020年から始まった法務局の遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書遺言でも「検認不要」で手続きできます。
ただし、法務局で保管されていても、内容が法律上有効であるかどうかまでは保証されません。つまり、保管制度は形式のチェックだけで、内容そのものの適法性までは担保されないという点に注意が必要です。
また、相続人が存在を知らないままだと、遺言書が"発見されないまま"になってしまう恐れもあります。
7. まとめ:形式を軽視した遺言は、家族を困らせる
遺言は、残せばよいのではなく、正しく残すことが重要です。
形式に不備がある遺言は、家族を混乱させ、かえって遺産分割を遅らせる原因になります。
相続トラブルを防ぎ、遺された人たちの手続きがスムーズに進むようにするためには、できるだけ公正証書遺言、あるいは信頼できる専門家のサポートのもとでの遺言作成が不可欠です。
「安心したいなら、"書き方"にもこだわる」——これが、後悔しない相続対策の第一歩です。

最新のブログ記事
家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】
「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」
最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】
「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味
司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。
この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。
本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。


