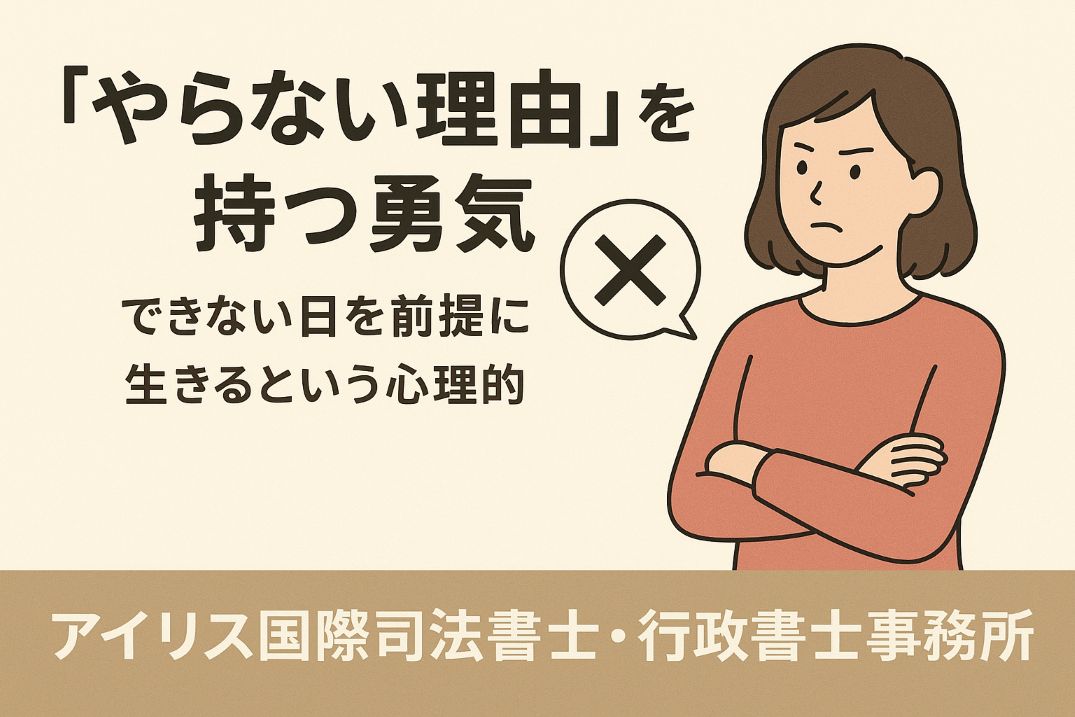相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第1回】デジタル時代の相続に潜む“見えない遺産”とは ~サブスク、ネット銀行、暗号資産…相続財産の全貌がつかめない時代~
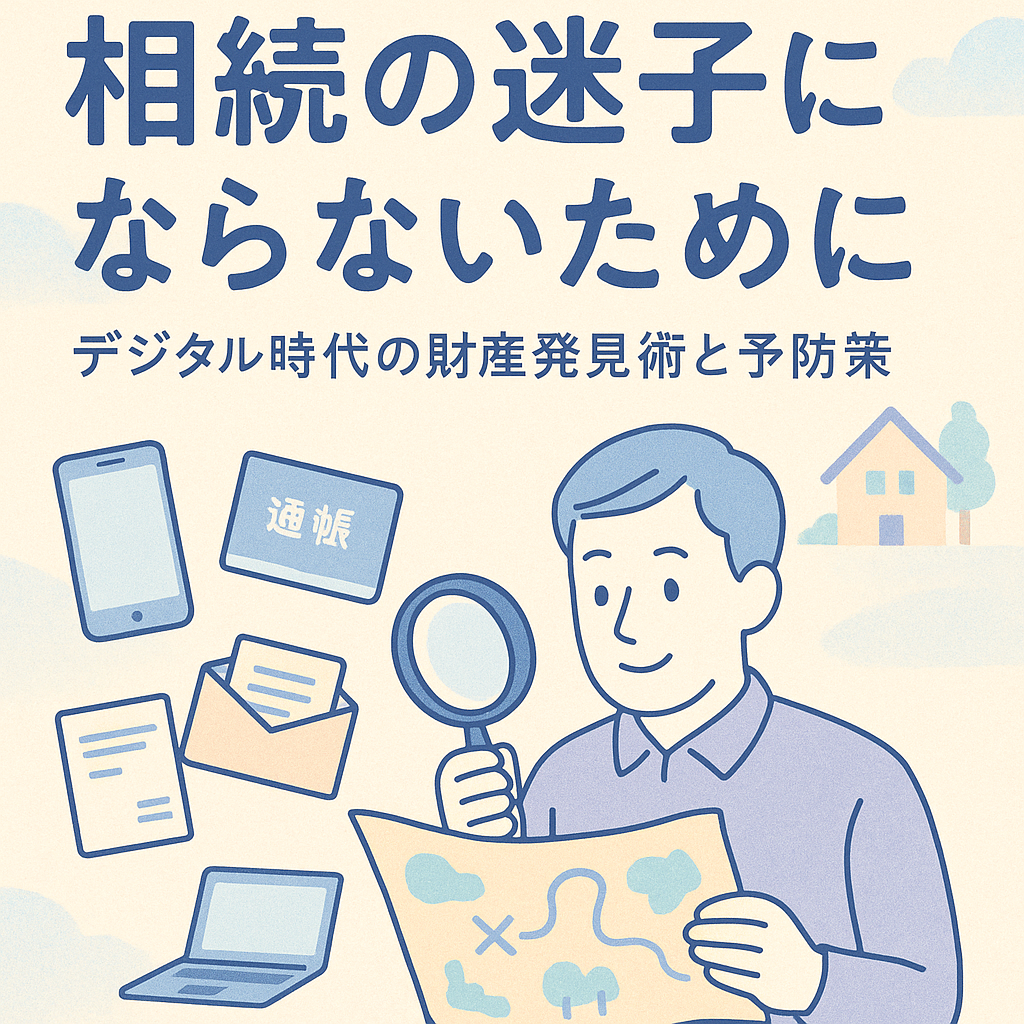
インターネットが生活に浸透した現代、相続財産の中身も大きく様変わりしています。かつては預貯金や不動産、株式といった"目に見える"資産が中心でしたが、近年では通帳も契約書類もない「ネット完結型」の資産――すなわち**デジタル遺産(デジタル資産)**が急増しており、相続時の財産調査や手続きが非常に困難になりつつあります。
本記事では、デジタル資産が相続手続きにおいてどのような課題を生むのかを事例とともに紹介し、見落とされがちな"見えない遺産"の現実に迫ります。これからの相続対策を考えるうえで、避けては通れないテーマです。
目次
- デジタル遺産とは何か?
- 急増する「ネット完結型サービス」
- 通帳も郵送物もない=気づけない
- よくある見落とし事例
- 相続トラブルの温床に
- まとめ:デジタル遺産こそ可視化が必要
1. デジタル遺産とは何か?

デジタル遺産(またはデジタル資産)とは、パソコンやスマートフォンを通じて利用されている、インターネット上の財産や契約情報のことを指します。主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ネット銀行の預金口座(例:楽天銀行、住信SBIネット銀行)
- 証券会社のネット口座(SBI証券、楽天証券など)
- 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアムなど)
- サブスクリプション型の契約(Netflix、Apple Music、Amazon Primeなど)
- オンライン決済サービス(PayPay、楽天Payなど)
- クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)
これらの資産や契約情報は、紙の通帳や契約書では管理されず、すべてオンライン上に完結していることが特徴です。そのため、本人以外が存在を把握することが極めて難しくなっています。
2. 急増する「ネット完結型サービス」

近年、金融機関・エンタメ・ライフスタイル全般において、「紙をなくす」「店舗に行かなくていい」ことが利便性とされ、ネット完結型のサービスが主流となっています。
特に以下のようなジャンルでは、もはや紙の証拠が一切残らないケースも珍しくありません。
- 給与の振込先をネット銀行に設定していた
- クレジットカードの明細はすべてWeb明細
- 資産運用はネット証券+ロボアドバイザー(ウェルスナビなど)
- 写真や書類の保存はGoogleフォトやiCloud
このような資産や契約は、「本人のIDとパスワード」にアクセスできなければ、そもそも存在に気づけないという特徴があります。
3. 通帳も郵送物もない=気づけない

従来の相続手続きでは、通帳や証券、郵便物などから財産の存在を特定することが一般的でした。しかしネット完結型サービスは、郵送物すら届かないことが多く、部屋をいくら整理しても何も出てこない=相続人が存在を把握できないという事態になりがちです。
例:
- 楽天銀行の口座はスマホアプリだけで完結。紙の通帳もキャッシュカードもない。
- PayPayや楽天Payの残高もアプリ上のみで確認可能。
また、AppleやGoogleのサブスクサービスは、自動更新され続けてカード引き落としが続くケースもあり、死亡後に知らずに数か月〜数年経過してから家族が気づくこともあります。
4. よくある見落とし事例
以下は、実際の相談や事例としてよくあるものです:
- 【仮想通貨の消失】
ビットコインを保有していたが、取引所も端末も不明でアクセス不能に。時価数百万円が事実上の喪失。 - 【放置された証券口座】
楽天証券にある株式が発見されず、配当金も未請求のまま数年経過。相続税の申告漏れにも。 - 【有料サブスクの放置】
亡くなった父のAmazonプライム、DAZN、iCloudが自動更新され続け、クレジットカードが止まるまで気づかず。 - 【クラウド内の遺言書】
遺言書がDropboxに保管されていたが、家族がログインできず無効扱いに。
5. 相続トラブルの温床に

デジタル遺産の存在に気づけなかったことで、次のようなトラブルに発展することがあります。
- 相続人間で「財産を隠しているのでは?」と疑念が生まれる
- 相続税申告が不完全になり、後日追徴課税が発生
- 相続放棄をしたのに後日ネット資産が発見される(=放棄の再考が必要)
- 資産が発見されてもアクセス不能で換金できない
司法書士や税理士など専門家に相談しても、「物理的に存在を証明するものがない」と、法的な手続きにも限界があります。
6. まとめ:デジタル遺産こそ可視化が必要
これからの時代、デジタル遺産の把握と管理は、相続をスムーズに進めるための重要なカギとなります。
- 親世代のデジタル利用の実態を家族で共有すること
- 生前の段階から「見える化」する工夫が求められること
- 司法書士や専門家の力を借りながら、「紙に残らない資産」に目を向けること

次回は、相続発生後に「見えない遺産」をどうやって調査するか――現実的な手法を7つ紹介します。相続人になったとき、または将来の相続対策を考える方にとって、必見の内容です。
最新のブログ記事
結論からお伝えします。
これからの生前対策は、「一つの制度に頼る時代」から「複数を組み合わせて備える時代」へ完全に移行しています。
私は昭和45年生まれです。物心ついた頃から、両親、特に母親から繰り返し言われてきた言葉があります。
「もっとグローバルに物を見ないとだめだ」。
“やらない理由”を持つ勇気 ― できない日を前提に生きるという心理的安全性
「頑張らなきゃ」「やらないといけない」――そんな言葉が頭の中で鳴り続けていませんか。現代は、"常に全力でいること"を求められがちです。しかし、人には波があり、余裕がない日や心が疲れている日もあります。だからこそ、「今日はできない」と認めることは怠けではなく、心理的安全性を守るための大切な選択です。本記事では、"やらない理由"を持つことを肯定し、自分のペースで生きるための考え方をお伝えします。