相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第2回】“じまい”が進まない理由と、放置が招くトラブルとは 〜感情・相続・近隣迷惑…現場で起きているリアルな問題〜
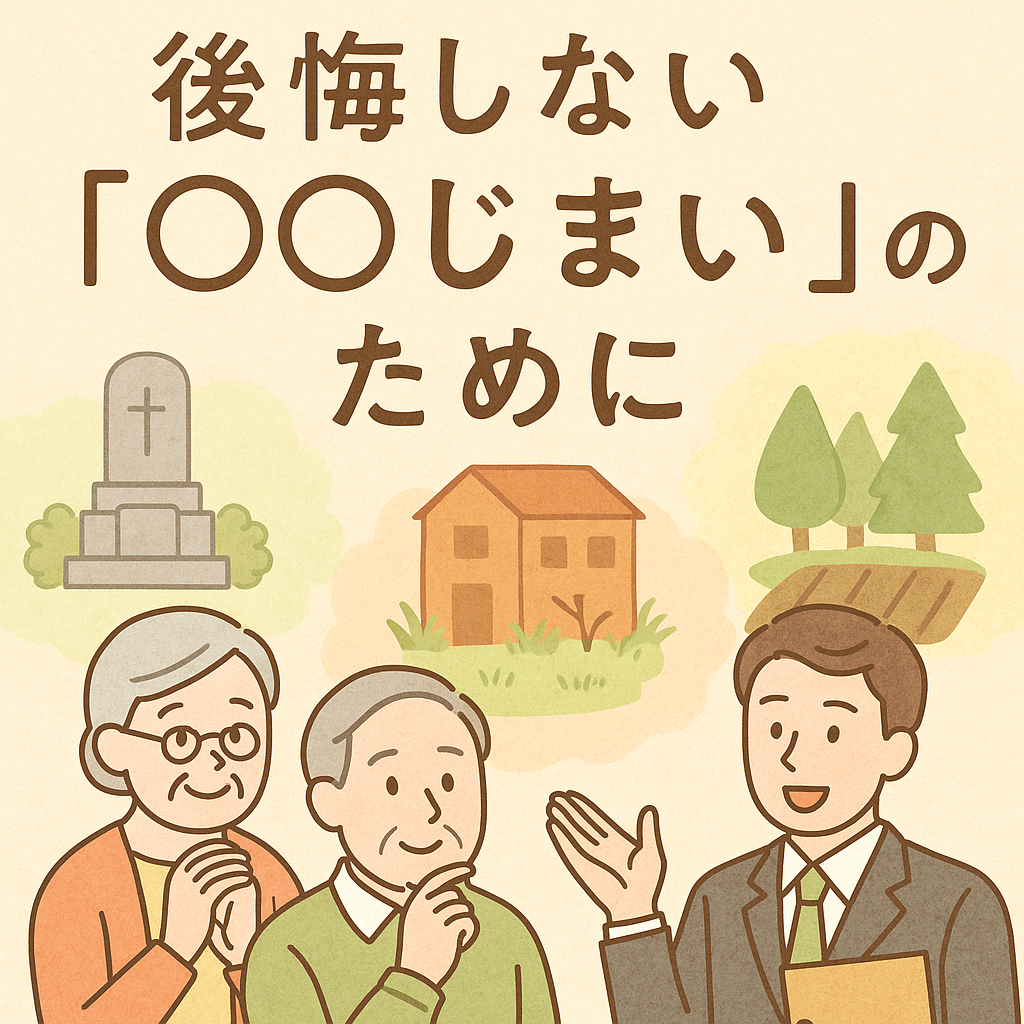
「墓じまい」「家じまい」「土地じまい」など、人生の後始末としての"じまい"が注目される一方で、実際には「やろうと思っているけど進まない」という人が少なくありません。
なぜ"じまい"はスムーズに進まないのか?
そこには、家族の感情、相続の問題、費用負担、そして放置によるトラブルなど、さまざまな事情が複雑に絡んでいます。
この記事では、じまいをためらう心理的な要因や、手続きの難しさ、そして対応を怠ったことで生じる実際のトラブルについて、具体的なケースをもとにわかりやすく解説します。
■ 目次
- "じまい"が進まない本当の理由とは
- よくある感情的対立と家族のすれ違い
- 相続・手続き・費用の現実
- 放置が招くリスクとトラブル事例
- まとめ:「今」やらないリスクを直視する
1. "じまい"が進まない本当の理由とは

"じまい"が進まない背景には、単なる「忙しいから」「後回しにしている」というだけではなく、次のような心理的・実務的な壁があります。
- 亡き親への罪悪感:「親が大切にしていた家や墓を壊すなんて…」という心の抵抗
- 兄弟姉妹間の温度差:「私は早く片づけたいが、兄は"まだ考えたくない"と言う」
- どこから手をつければいいのかわからない:調査・見積・行政手続きなどが煩雑
感情と現実が交錯し、結果として何年も放置されるケースが増えています。
2. よくある感情的対立と家族のすれ違い

"じまい"には、財産価値だけでなく「思い出」や「家族の歴史」がついて回ります。
そのため、次のような感情の衝突がよく起きます。
- 「勝手に決めるな」問題:地方の実家を管理している長男が「家を売る」と言い出したとき、遠方に住む妹が「相談もなく決めるなんて」と反発。
- 「まだ心の整理ができていない」問題:親の死後まもなく墓じまいを提案すると、他の家族が「もうそんな話をするのか」と拒否反応。
特に相続人が複数いる場合、それぞれの価値観・感情が異なるため、「誰も手を出せないまま時間だけが過ぎる」という状況に陥りがちです。
3. 相続・手続き・費用の現実

"じまい"には、感情の問題だけでなく、法的・経済的な課題もついてきます。
- 相続登記が未了の不動産:名義変更がされていないため、売却や解体ができない
- 費用負担の押し付け合い:「家は不要だが、解体費用は出したくない」
- 墓じまいに必要な書類の煩雑さ:改葬許可申請書、受け入れ先との契約など
こうした事務的ハードルの高さが、"じまい"を一段と遠ざけてしまうのです。
4. 放置が招くリスクとトラブル事例
何年も"じまい"を放置することで、以下のような問題が現実に起きています。
■ 空き家が老朽化して倒壊寸前に
地方の実家を10年以上放置。近隣住民から「瓦が落ちてきそう」「草が伸びて害虫が出る」と苦情が出て、行政が"特定空き家"として指導。固定資産税が6倍になったケースも。
■ 墓石が倒れ、他人にケガをさせた
山間部の古い墓を放置していたところ、大雨によって墓石が倒壊。たまたま訪れた別家の親族がケガを負い、損害賠償トラブルに発展。
■ 名義が曖昧な山林で所有者不明扱いに
曽祖父名義のまま放置された山林が、相続登記未了で所有者不明土地として扱われ、将来的に収用や共有解消の対象になった。
こうしたケースは決して特別なものではなく、「どの家庭にも起こりうること」と言って過言ではありません。
5. まとめ:「今」やらないリスクを直視する
"じまい"は感情的にも、手続き的にも決して簡単なものではありません。
だからこそ、「あとで」と思っているうちに状況が悪化し、家族の負担や社会的トラブルへとつながってしまうのです。
必要なのは、「迷惑をかけたくない」という気持ちを形にしていくこと。
小さな一歩で構いません。まずは、現状を把握する、親族と話す、専門家に相談する、そうした行動が"じまい"を前に進める鍵となります。

次回は、実際に"じまい"を決断した人々の声や事例を紹介しながら、「やってよかった」という視点で考えていきます。
最新のブログ記事
家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】
「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」
最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】
「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味
司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。
この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。
本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。


