相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第2回】老子と荘子に学ぶ「力を抜く勇気」——柔らかくしなやかに生きるという選択
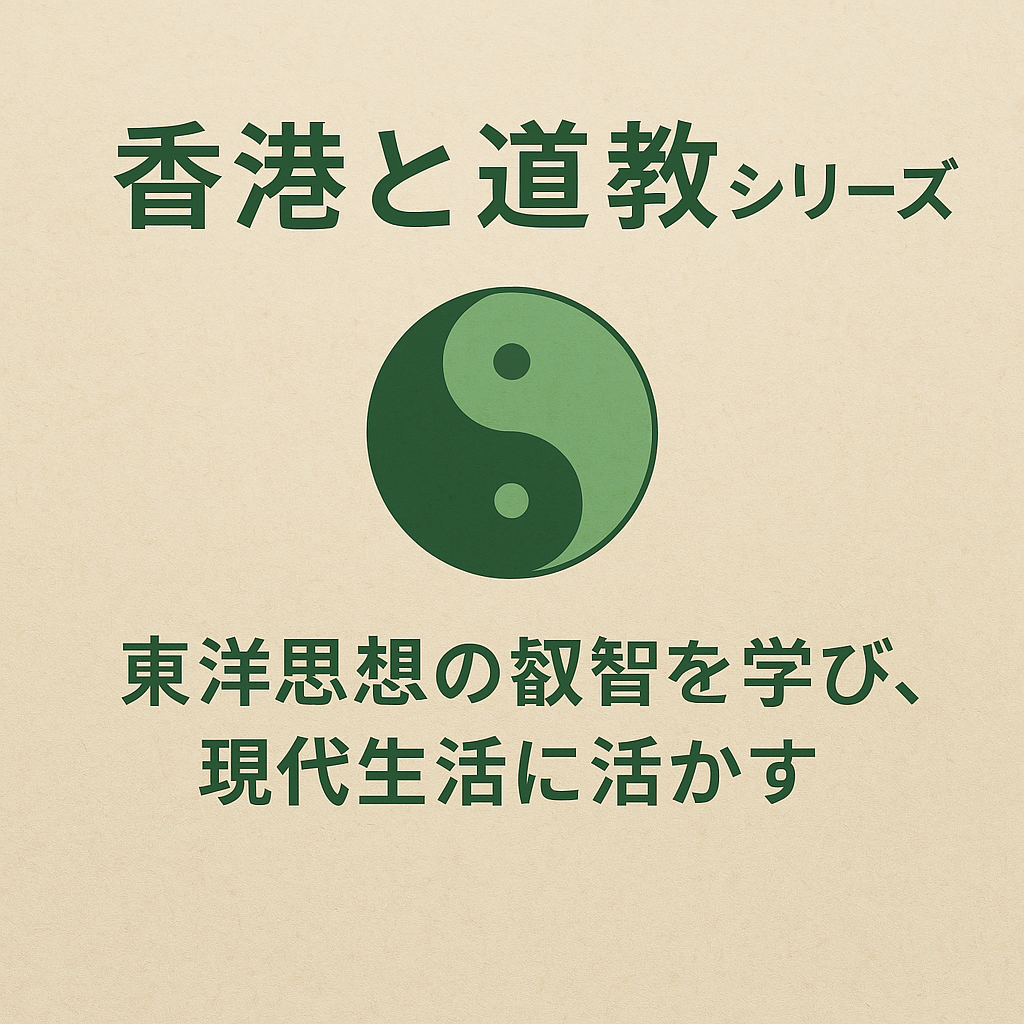
「老子 荘子 違い」「老荘思想 現代に活かす」「力を抜く 東洋哲学」などのキーワードで検索される方に向けて——。
老子や荘子に代表される老荘思想は、「力を入れすぎず、自然と調和して生きる」ことを大切にする東洋哲学です。現代社会では、頑張りすぎることが美徳とされがちですが、老荘思想はその真逆。むしろ「無理をしないこと」こそが、真に強く、しなやかな生き方だと教えてくれます。本記事では、老子と荘子の思想の違いと共通点、そして現代における実践的な意味を解説します。
📖目次
- 老荘思想とは?
- 老子が説く「無為」の哲学
- 荘子が描く「自由な心」の境地
- 現代社会における"力を抜く"という選択
- まとめ:あなたの中にある「自然」に戻るために
1. 老荘思想とは?

老荘思想とは、中国戦国時代の思想家・老子と荘子の教えを中心に構成された東洋哲学の一体系です。「道(タオ)」という万物の根源を重視し、自然に逆らわず調和の中で生きることを理想とします。
老子が抽象的・哲学的な理論に重点を置いたのに対し、荘子はより物語的・感覚的な表現で、自由で軽やかな人生観を示しました。両者の思想はセットで語られることが多く、「老荘思想」としてまとめられています。
2. 老子が説く「無為」の哲学

老子の代表作『道徳経』では、「無為自然(むいしぜん)」という言葉が象徴的に用いられます。これは「無理に何かをしようとせず、自然の流れに任せる」ことを意味します。
例えば、川の水が岩を避けながら流れるように、人もまた自分の内なる"道"に従って進めばよい。力で押し通すのではなく、「やわらかく生きる」ことが結果として最も強いと説いています。
老子の思想は、現代でいえば「コントロールできないことに執着しない」「物事を手放す勇気を持つ」といったマインドセットにもつながります。
3. 荘子が描く「自由な心」の境地
一方、荘子はより自由奔放でユーモラスなスタイルで、「心の自由」を追い求めました。たとえば有名な「胡蝶の夢」では、自分が蝶になった夢を見たのか、それとも蝶が自分になった夢を見ているのか分からない——というエピソードを通じて、現実と夢、自我と世界のあいまいさを描いています。
荘子にとって大切なのは、「とらわれないこと」。肩書きや評価、社会的な役割に縛られることなく、自分の内面に素直に生きることを理想としました。そこには、誰とも競わず、比べず、自分の"道"を歩く姿勢が貫かれています。
4. 現代社会における"力を抜く"という選択

現代は、成果主義やSNSによる比較、情報過多の時代です。「もっと頑張らなければ」「人に負けたくない」という無意識の緊張が、私たちを常に縛りつけています。
しかし、老荘思想に立ち返ると、「力を抜くこと」「競争から距離を取ること」は"逃げ"ではなく"戦略"であることが分かります。疲れたとき、悩んだとき、肩の力を抜いて自然に任せる——そんな選択ができる人こそが、むしろ強く、しなやかに生きられるのです。
5. まとめ:あなたの中にある「自然」に戻るために
老子と荘子の思想は、決して難解な古典ではなく、現代を生きる私たちの心の休息にもなり得る"知恵の宝庫"です。
がむしゃらに頑張ることだけが正解ではない。
疲れたら立ち止まり、流れに任せ、自分の"道"に耳を傾けること。
老荘思想は、その一歩を後押ししてくれる優しい伴走者のような存在です。
次回は、この老荘思想が派生した「風水」にスポットを当て、空間と運気の関係、そして道教とのつながりについてお届けします。
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



