相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第3回】名義預金の落とし穴──家族名義の預金は誰のもの?
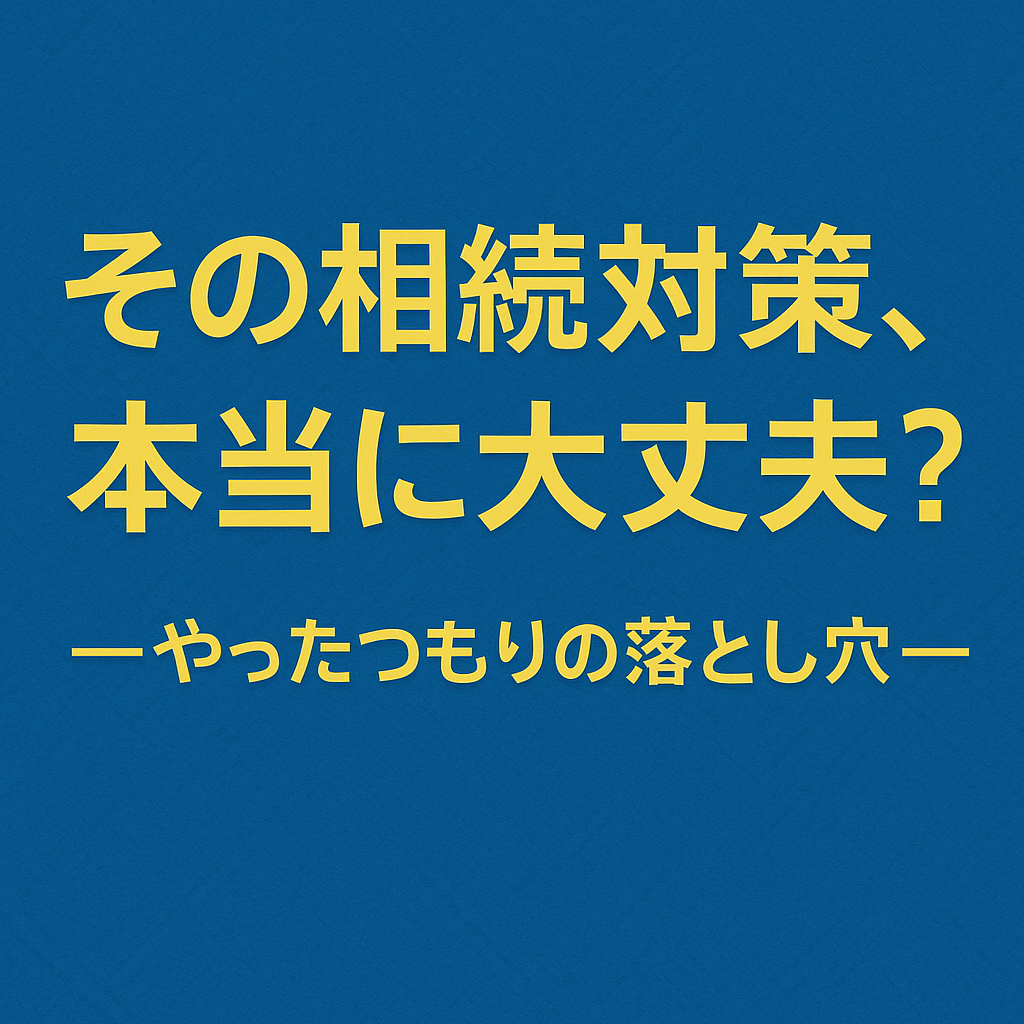
「母の通帳にお金を移しておいたから大丈夫」「子ども名義の預金は、生前贈与のつもりだった」──このような名義だけを変えた預金(名義預金)が、相続時に相続税の対象となることや、相続トラブルの原因になることをご存じでしょうか?
名義預金は見た目には"家族の預金"ですが、実質的には亡くなった人(被相続人)の財産とみなされる場合が多く、課税や分割対象になる可能性があります。本記事では、名義預金の定義と危険性、税務上の扱い、そして家族を守るための対策を、実例とともに詳しく解説します。
【目次】
- 名義預金とは?──名前は家族、でも中身は本人
- なぜ名義預金が相続トラブルになるのか
- 税務署が「名義預金」と判定するポイント
- 名義預金に関する実際のトラブル例
- 対策①:本当の贈与にするために必要なこと
- 対策②:生前からの"使い方"と"記録"の工夫
- まとめ:通帳の名義ではなく、実質で判断される
1. 名義預金とは?──名前は家族、でも中身は本人

名義預金とは、「形式上は配偶者や子どもなどの名義になっているが、実質的には被相続人(亡くなった方)が管理・支配していた預金」を指します。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- 子ども名義の預金通帳を親が管理し、出し入れも親がしていた
- 通帳の印鑑が親のものと同一
- 子ども本人は口座の存在を知らない
このような場合、たとえ通帳の名義が子どもであっても、実質的には被相続人の財産とみなされるのです。
2. なぜ名義預金が相続トラブルになるのか
名義預金は、相続税の申告の際に財産に含めるかどうかが曖昧になるため、家族間でトラブルの原因となりがちです。
- 長男が母名義の通帳を「自分が生前に贈与を受けていた」と主張
- 他の兄弟が「贈与の証拠がないから、遺産に含めるべき」と反論
こうした対立が調停や訴訟にまで発展することもあります。
3. 税務署が「名義預金」と判定するポイント

税務署は、通帳の名義ではなく、資金の出どころと通帳の管理実態を重視します。以下のような場合、名義預金と認定されやすくなります。
- 預金の原資が被相続人(親など)の収入である
- 贈与契約書などがない
- 名義人本人が預金の存在や使用目的を把握していない
- 通帳や印鑑を被相続人が管理していた
税務調査では、金融機関の記録や通帳・印鑑の保管状況、生活実態まで細かく確認されることがあります。
4. 名義預金に関する実際のトラブル例

【事例】
母の死後、相続財産として申告されたのは、自宅と定期預金のみ。しかし、税務調査で長女名義の口座に2,000万円の預金があることが発覚。
実は母が長年にわたって管理していたもので、長女も「自分のお金ではない」と証言。結果として、その2,000万円も母の相続財産とみなされ、相続税が追徴課税されることに。
このように、「名義だけの預金」は相続税の申告漏れとされる危険があり、延滞税や加算税まで課される可能性があります。
5. 対策①:本当の贈与にするために必要なこと
名義預金を「本当の贈与」として成立させるためには、以下の点に留意する必要があります。
- 贈与契約書を作成(可能であれば日付入りで自筆または公正証書)
- 贈与税の申告(年間110万円以上の場合)を行う
- 贈与を受けた本人が預金の存在と内容を把握している
形式的な処理だけでなく、「贈与の意思」と「受贈者の認識」が重要です。
6. 対策②:生前からの"使い方"と"記録"の工夫
名義預金問題を避けるには、生前からの管理の透明化が効果的です。
- 通帳や印鑑を名義人本人に渡す
- 預金の使途を記録しておく
- 家族間でお金の流れを共有する
また、可能であれば贈与ではなく「生前に財産を分ける」方針で、遺言や民事信託の活用も検討するとよいでしょう。
7. まとめ:通帳の名義ではなく、実質で判断される
相続における名義預金の問題は、「名義」と「実質」の乖離が生むトラブルです。
家族名義にして安心していても、管理や意思が伴っていなければ、相続税の対象となり、争いの火種にもなり得ます。
家族を守るためには、形式だけでなく中身を伴わせることが大切です。贈与の記録を残す、本人に通帳を渡す、適切に申告する——そうした一手間が、後々の相続をスムーズにし、家族関係を守る鍵となります。

次回は「負動産の悲劇──不要な土地を子に押しつけないために」と題して、処分も管理も難しい"負動産"が相続人を苦しめるケースとその対策についてお届けします。
最新のブログ記事
「親が認知症になっただけで、銀行口座が凍結されるなんて信じられない」
多くの方がそう思います。しかし実務の現場では、認知症=お金が使えなくなるという事態が毎日のように起きています。
実はこれは銀行の意地悪でも、融通のなさでもなく、法律でそうなっているからです。
そして何より怖いのは、「介護が始まってからでは、もう手遅れ」だということ。
この記事では、なぜ口座が止まるのか、家族がどんな状況に追い込まれるのか、そしてどうすれば凍結を防げるのかを、司法書士の実務視点でお伝えします。
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。



