相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第4回】相続した農地は「貸す」という選択肢も!農地バンクなどを活用する方法とは?
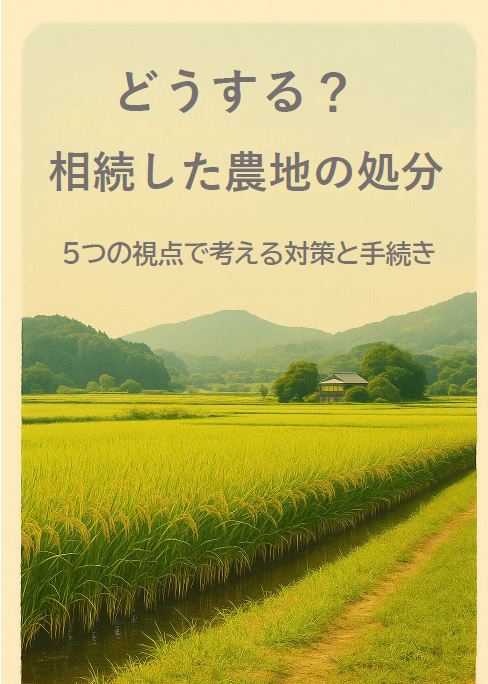
【はじめに:農地は売れないなら"貸す"という方法もある】
「農地を相続したけれど、農業をする予定はない。売ることも難しい」――そんな方に注目していただきたいのが、農地を"貸す"という選択肢です。
農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。
特に、国が推進している農地中間管理機構(いわゆる「農地バンク」)の活用は、有効な手段の一つです。
農地を相続した方にとって、「耕作放棄地」として管理放棄してしまうよりも、社会的にも経済的にもメリットがある方法として注目されています。
この記事では、農地を相続した場合に「貸す」という選択肢がどのように機能するのか、メリット・デメリット、手続きの流れについて詳しくご紹介します。
目次
- 農地を貸すときの基本ルール
- 「農地バンク(農地中間管理機構)」とは?
- 農地バンクを使うメリットと条件
- 個人間での農地の賃貸借も可能?
- 貸すときに注意すべきポイント
- 「貸す」か「売る」か判断の基準とは?
- まとめ:農地を活かす選択を
- 【CTA】農地の活用に迷ったら、まずはご相談を
1. 農地を貸すときの基本ルール

農地を貸し出す際にも、やはり農地法の規制が関係してきます。
農地を他人に貸す場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。
ただし、以下のような例外があります:
- 農地中間管理機構を介して貸す場合は、許可ではなく届出で可
- 相続人が複数いる場合は、事前に共有者の同意が必要
また、契約期間や耕作目的によっても取り扱いが異なるため、事前の確認と専門家の助言が不可欠です。
2. 「農地バンク(農地中間管理機構)」とは?
農地バンクとは、正式には農地中間管理機構と呼ばれる公的な組織で、各都道府県単位で設置されています。
その主な役割は以下のとおりです:
- 農地の「貸したい人」と「借りたい人」をマッチングする
- 農地の管理を中間的に引き受け、適切な利用者へ再貸し付けする
- 農業の担い手に農地を集積・集約する
貸主(地主)は、農地バンクに農地を提供することで、煩雑な賃貸契約や管理の手間を軽減できます。
3. 農地バンクを使うメリットと条件

【メリット】
- 農地法第3条の**「許可」が不要(届出のみ)で簡単**
- 利用者の選定や契約管理を農地バンクが代行
- 一定の賃料収入が見込める
- 農地の有効活用が社会的にも評価される
【利用の条件】
- 農地の状態が一定基準を満たしている(耕作可能)
- 地域によっては「優先区域」の指定がある
- 一定の契約期間が必要(原則10年が目安)
自治体や農業委員会の協力も得られやすいため、相続農地の放置対策としては最も現実的な選択肢の一つです。
4. 個人間での農地の賃貸借も可能?
農地を農地バンクを通さずに、個人間で貸すことも可能です。
ただしその場合、農地法第3条による「賃貸借の許可」が必要になります。
この許可を得るには、借り手側に以下のような条件が求められます:
- 農業に従事する能力・実績がある
- 農業経営として適切な規模を維持している
- 地域の農業との調和がとれている
また、契約書の整備、契約期間、更新手続きなどの管理も自分で行う必要があるため、煩雑さは否めません。
5. 貸すときに注意すべきポイント

農地を貸し出す際には、次の点に注意が必要です:
- 【契約内容の明確化】
口約束ではなく、書面で契約内容を明示すること - 【賃料の取り決め】
地域の相場を参考に設定し、金額・支払時期を明記 - 【契約期間】
短期よりも長期契約の方が農業者側のメリットが大きい - 【管理責任の所在】
境界トラブルや災害時の責任分担も事前に明文化しておく
また、賃料を「無償」とする場合にも、農地法の許可・届出は必要になることを覚えておきましょう。
6. 「貸す」か「売る」か判断の基準とは?
相続した農地の将来について「貸すか売るか」迷ったときは、以下の観点で考えるとよいでしょう。
- 将来的に農地を自分や家族が使う予定があるか?
- 売却が可能な地域かどうか(都市計画区域など)
- 買い手が見つかる見込みはあるか?
- 貸すことでの収益や社会的貢献をどう評価するか?
特に「すぐには売れない」「誰に売ればよいか分からない」といった場合には、貸すことで時間的猶予を得ることも有効です。
7. まとめ:農地を活かす選択を
相続した農地に手をつけずにいると、草が生い茂ったり、近隣からの苦情が出たりと、管理リスクが高まります。
けれど「貸す」という手段を取れば、農地は社会に貢献しながら、持ち主にとっても利益をもたらす存在になります。
特に農地バンクを活用すれば、煩雑な手続きの多くを任せられ、実質的に放置せずに済むのです。
次回(第5回)は、どうしても売れない・貸せない農地に対して取れる"出口戦略"についてご紹介します。

【CTA:農地の貸し出しや活用方法にお悩みの方へ】
「農地バンクって、実際どう使うの?」
「貸したら返ってこないのでは?トラブルが心配…」
そんな不安や疑問、ありませんか?
当事務所では、農地の相続・活用・貸出に関する無料相談を承っています。
農業委員会との調整や、契約書の作成支援もおまかせください!
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
「放置する前に、一度だけでも相談してみる」――それが、未来への最良の一歩かもしれません。
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



