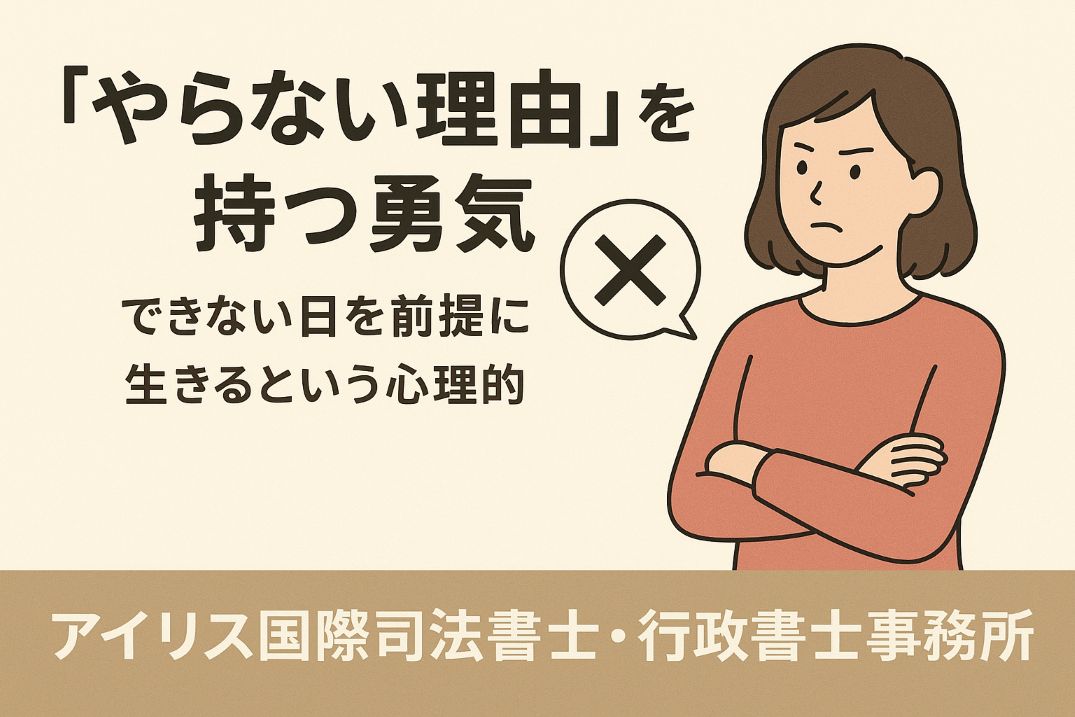相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第4回】知らなかったでは済まされない? デジタル遺産と相続トラブルのリアル
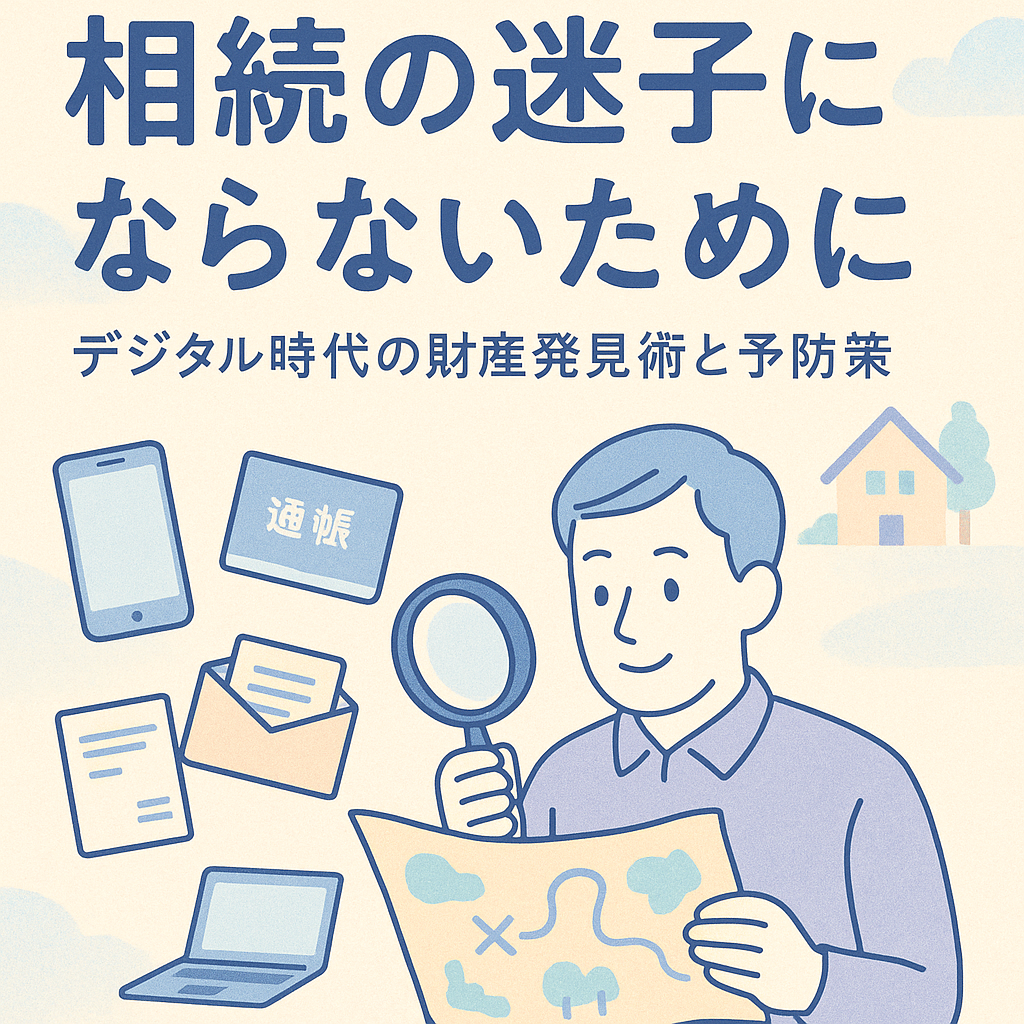
相続の現場で近年深刻化しているのが「デジタル遺産をめぐるトラブル」です。ネット銀行、仮想通貨、電子マネー、SNSアカウント——生前に整理されないまま残されたこれらの資産や情報が、遺族間の争いの火種になることも少なくありません。
「そもそもどこに何があるのか分からない」「IDやパスワードが分からずログインできない」「仮想通貨が消失した」など、デジタル資産ならではの相続問題が急増しており、法律上の課題も多く存在します。
本記事では、相続の際に起こり得るデジタル遺産に関する法的トラブルとその予防策について、具体的に解説します。
目次
- デジタル遺産にまつわる典型的な相続トラブルとは
- ID・パスワードが分からない場合の法的対応
- 仮想通貨の消失と所有権の証明問題
- SNSやクラウド上の情報と「人格権」問題
- 民法上の「相続財産」として扱えるか?
- 事前対策としての遺言・委任契約の活用
- 専門家に相談すべき場面とは
- まとめ:法律とデジタルの"すき間"を埋めるには
1. デジタル遺産にまつわる典型的な相続トラブルとは

相続人が複数いる場合、「どこにどれだけ資産があるか分からない」ことが、争いの元になります。特にデジタル資産は目に見えず、通知も紙で来ないため、相続人の一部だけが把握していると、「隠し財産だ」「故意に伝えていない」などといった疑念を招くことがあります。
例:
- 仮想通貨ウォレットの存在に一部の相続人だけが気づき、他の相続人と対立
- LINE Payの残高が口座に入金されないまま失効
- サブスク料金の未払いが続き、クレジットカードに請求される
2. ID・パスワードが分からない場合の法的対応

デジタル資産にアクセスするには、IDとパスワードが必須ですが、それが分からない場合、第三者である遺族が勝手にログインすることは原則として法律に触れる可能性があります。
民法では相続財産は包括的に相続されますが、利用規約や不正アクセス禁止法との関係が複雑です。他の相続人と共同して対応してください。
● 実務上の対応:
- サービス提供会社に「相続人としての開示請求」を行う(戸籍・遺言書などが必要)
- 弁護士を通じて正式に照会を行うケースも
- IDやログイン履歴から、残高照会だけでもできる場合もある
3. 仮想通貨の消失と所有権の証明問題

仮想通貨(暗号資産)は、「ウォレットの秘密鍵」や「アカウントの2段階認証コード」がないとアクセス不能になります。これが分からないまま放置されると、数十万~数百万円分の資産が実質的に"消失"することも。
さらに、所有していたことを証明するには、ログイン履歴や送金記録などが必要ですが、取引所が閉鎖されていたり、過去の記録が手元にないと証明が難しくなります。
4. SNSやクラウド上の情報と「人格権」問題
Facebook、Instagram、Twitter(X)などのSNSアカウントや、クラウド上に保管された写真・日記・記録類などの扱いも課題です。
これらは金銭的価値よりも、「亡くなった本人の人格にかかわる情報」として削除か保存かで家族が対立することも。
- 本人が遺したい意向が不明な場合、親族内で意見が分かれる
- 他人の個人情報が含まれていると、保存・公開でプライバシー侵害のリスクも
- クラウド有料契約の解約忘れによる課金トラブルも発生しやすい
5. 民法上の「相続財産」として扱えるか?
民法上、相続財産は「財産的価値のあるもの」が対象ですが、暗号資産や電子マネー、ポイントなどは一律に相続できるわけではありません。
- 仮想通貨:法的には相続財産に該当(ただし実質的にアクセスできないと意味がない)
- 電子マネー:利用規約で「相続不可」とするサービスも(例:楽天ポイント等)
- サブスク:名義人限定の契約が多く、原則として契約終了
つまり、「相続できる」かどうかは、法律と利用規約の両方を確認する必要があります。
6. 事前対策としての遺言・委任契約の活用

これらの法的リスクを軽減するには、生前の対策が不可欠です。
- 遺言書:暗号資産やネット口座の存在、分配方法を明記しておく
- 任意後見契約:認知症などで判断力が落ちたときのアクセス権限を委任
- 秘密鍵・パスワードの保管先を明示:紙で残す/信託型サービスを利用するなど
また、遺言に「特定のクラウドサービスを解約してよい」と記しておけば、家族が判断に迷うことも少なくなります。
7. 専門家に相談すべき場面とは
以下のようなケースでは、司法書士や弁護士、ITリテラシーのある税理士など、専門家の力を借りるのが確実です。
- 仮想通貨の存在は分かっているがアクセスできない
- SNSアカウントを削除したいが、手続きが分からない
- 他の相続人と資産の取り扱いで意見が対立している
- サービス提供会社との交渉が必要
デジタル資産の相続は、法的知識と実務知識の両方が求められます。経験豊富な士業の関与が、解決の近道になることも多いのです。
まとめ:法律とデジタルの"すき間"を埋めるには
デジタル遺産に関する相続トラブルは、「知らなかった」「想定外だった」で済まされない事態を招く可能性があります。
とくに、相続人の間で知識の差や情報格差がある場合、疑念や不信が大きな争いに発展することも。
だからこそ、生前のうちに:
- 情報を見える化し
- アクセス手段を残し
- 法的根拠となる書類(遺言や契約)を用意する
ことが、ご自身にもご家族にも安心をもたらします。

次回(第5回/最終回)は、**司法書士による「生前対策としての不動産・遺言・後見の総まとめ」**をお届けします。
最新のブログ記事
結論からお伝えします。
これからの生前対策は、「一つの制度に頼る時代」から「複数を組み合わせて備える時代」へ完全に移行しています。
私は昭和45年生まれです。物心ついた頃から、両親、特に母親から繰り返し言われてきた言葉があります。
「もっとグローバルに物を見ないとだめだ」。
“やらない理由”を持つ勇気 ― できない日を前提に生きるという心理的安全性
「頑張らなきゃ」「やらないといけない」――そんな言葉が頭の中で鳴り続けていませんか。現代は、"常に全力でいること"を求められがちです。しかし、人には波があり、余裕がない日や心が疲れている日もあります。だからこそ、「今日はできない」と認めることは怠けではなく、心理的安全性を守るための大切な選択です。本記事では、"やらない理由"を持つことを肯定し、自分のペースで生きるための考え方をお伝えします。