相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第4回】連絡が取れない相続人がいる場合の対処法 ~音信不通・所在不明の相続人がいるとき、相続登記はどうなる?~
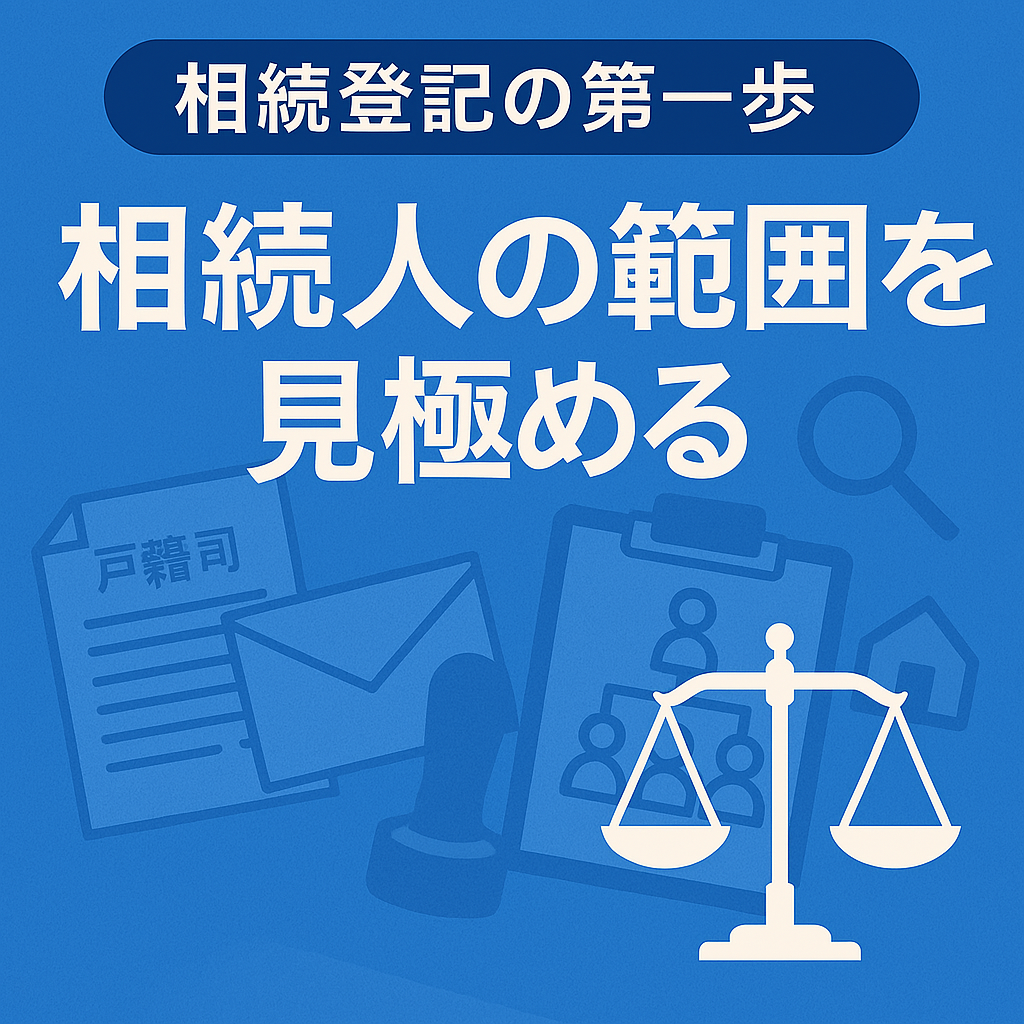
相続手続きを進めようとしても、「長年会っていない親族がいて連絡がつかない」「海外にいる兄弟の住所が不明」など、連絡が取れない相続人の存在が大きな障害になることがあります。
特に相続登記を行う際は、相続人全員の同意や署名押印が原則として必要になるため、一人でも所在不明者がいれば、登記手続きはストップしてしまいます。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の法的対処法として、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の活用、遺産分割協議の進め方などを、司法書士の視点から解説します。
家族のつながりが希薄化する現代だからこそ、知っておきたい相続人不明時の対応策をしっかり押さえましょう。
■ 目次
- 相続登記における「相続人全員の合意」の原則
- 相続人と連絡が取れないケースの分類
- 「住所不明」「音信不通」の相続人への対応策
- 不在者財産管理人の選任手続き
- 長期不在・生死不明のケースと失踪宣告
- 相続放棄していた場合はどう扱う?
- 実務上の注意点とよくあるトラブル
- まとめ:放置せず、専門家に早めの相談を
- アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
1. 相続登記における「相続人全員の合意」の原則

相続登記では、遺産分割協議により特定の相続人が不動産を取得する場合、相続人全員の同意と署名・実印・印鑑証明書が必要になります。
つまり、1人でも署名できない相続人がいれば登記申請ができません。この点が、連絡不能な相続人がいるときに大きな壁になります。
2. 相続人と連絡が取れないケースの分類

連絡が取れない相続人と一口に言っても、その状況はさまざまです。
主なケースを以下に分類します。
- ①音信不通(携帯・メール・SNSなども一切反応なし)
- ②住所不明(住民票の追跡でも現住所不詳)
- ③海外在住で連絡が取れない
- ④意思能力に疑義(高齢・認知症等で意思確認ができない)
- ⑤生死不明(長期間連絡がなく、死亡している可能性も)
対応策は、それぞれの事情に応じて異なります。
3. 「住所不明」「音信不通」の相続人への対応策
まずは、住民票・戸籍の附票・転出先調査などにより、相続人の現住所や所在を調査します。
しかし、住所が分かっても連絡が取れない場合や、完全に所在が不明な場合は、法的な措置が必要です。
4. 不在者財産管理人の選任手続き

連絡が取れない相続人がいるままでは遺産分割協議を進められません。
そのため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。
- 管轄:不在者の最後の住所地の家庭裁判所
- 申立人:他の相続人など
- 選任される人物:弁護士や司法書士等の専門家が多い
- 役割:不在者の利益を守りつつ、遺産分割協議に参加する
この制度により、相続人本人が参加できない場合でも、手続きを進めることが可能になります。
5. 長期不在・生死不明のケースと失踪宣告
生死不明状態が7年以上(戦争・災害など特例あり)続いている場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が認められれば、法律上「死亡したもの」として扱われるため、代襲相続などが発生し、次の手続きへと進むことができます。
ただし、手続きには期間がかかるため、早めに動くことが大切です。
6. 相続放棄していた場合はどう扱う?
「以前に相続放棄した」という相続人がいる場合、その証明として**家庭裁判所の「相続放棄受理証明書」**が必要です。
証明書があれば、該当者は相続人から外れるため、遺産分割協議に参加させる必要はなくなります。
7. 実務上の注意点とよくあるトラブル

- 勝手に「この人はもう関係ない」と判断し、登記を進めると後日、登記無効や訴訟の原因になる可能性があります。
- 海外在住の相続人がいる場合、その国の印鑑証明制度や公証制度の有無によって書類の取得が困難なケースも。
- 不在者財産管理人の選任は、裁判所の判断により数か月を要することもあるため、余裕を持った対応が必要です。
8. まとめ:放置せず、専門家に早めの相談を
相続人の中に連絡が取れない人がいると、手続き全体が止まってしまい、相続登記の義務期限(2024年4月から3年以内)が迫ると過料の対象になる可能性もあります。
相続登記は「いつかやればいい」ではなく、今できる手続きを先延ばしにしないことが最善策です。
早期に司法書士や弁護士と連携して対処することが、家族間のトラブル予防にもつながります。

9. アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
「連絡が取れない相続人がいて、手続きが止まっている」
「不在者財産管理人の手続きをどう進めればいいか分からない」
そんなお困りごとは、アイリス国際司法書士・行政書士事務所が全力でサポートいたします。
相続登記の経験豊富な司法書士が、法的手続きから書類収集までワンストップで対応可能です。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



