相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第5回】生命保険を活用した生前対策~相続・納税・遺族の安心を同時に備える方法~

「生命保険で相続税が節税できるって本当?」
「子どもが揉めないように、現金で遺してあげたい…」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
生命保険は"亡くなった後"だけでなく、"亡くなる前"から使える生前対策の強い味方です。
遺言や成年後見、家族信託といった制度と比べて、手軽に始めやすく、また保険金は"受取人固有の財産"となるため、遺産分割協議の対象外で、相続トラブルを回避しやすいという利点があります。
この記事では、生命保険を使った賢い相続・生前対策の方法を、実例とともにわかりやすく解説します。
■目次
- 生命保険が生前対策になる理由とは?
- 保険金の非課税枠を活用しよう
- 相続トラブルを防ぐ仕組みとしての生命保険
- 「納税資金」としての使い方
- よくある失敗事例と注意点
- まとめ:生命保険で"争続"を防ぐ
- ご相談のご案内(CTA)
1. 生命保険が生前対策になる理由とは?

生命保険は「亡くなったときに保険金が支払われる」という仕組みですが、あらかじめ誰にいくら渡すかを設計しておける点が、他の相続対策にはない特徴です。
たとえば…
- 配偶者に生活費を確保したい
- 同居して親の介護をしてくれている長女に多めに渡したい
- 事業を承継する長男に資金を集中させたい
といった意向を反映できるのが、「受取人を指定できる」保険の強みです。
2. 保険金の非課税枠を活用しよう

生命保険には、相続税の非課税枠が認められています。
具体的には、以下のように計算されます。
📌 非課税限度額=「500万円 × 法定相続人の数」
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、500万円 × 3人=1,500万円までが非課税。
これは、現金や預金では認められない優遇措置であり、生命保険ならではのメリットです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 被相続人の死亡によって支払われる契約であること
- 受取人が相続人であること(相続人以外は非課税枠の対象外)
3. 相続トラブルを防ぐ仕組みとしての生命保険
生命保険は「遺産分割協議」の対象にならず、受取人がすぐにお金を受け取れるというスピード性が最大の特徴です。
そのため、以下のようなケースに非常に有効です。
- 相続人同士の関係がぎくしゃくしている
- 遺言がない、もしくは偏った内容の遺言がある
- 預貯金の名義変更に時間がかかりそう
「〇〇に1000万円渡したい」という気持ちを確実に実現しつつ、他の相続人の同意を得る必要がないのが大きな強みです。
4. 「納税資金」としての使い方
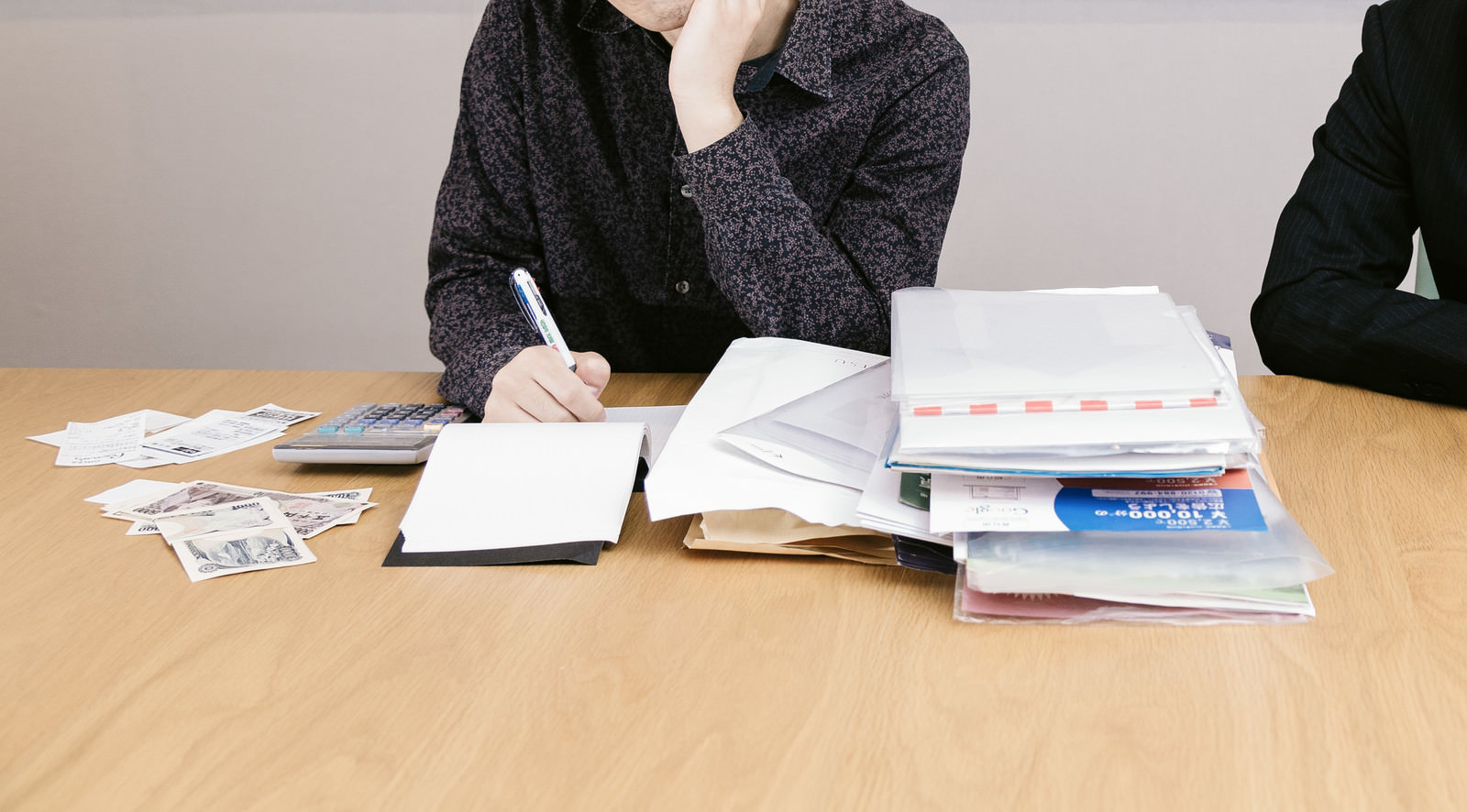
相続税は、原則として現金で一括納付が求められます。
しかし、相続財産が不動産ばかりで現金が少ないと、納税に困ってしまうケースも。
そんなとき、あらかじめ生命保険で現金を準備しておくことで、以下の問題を回避できます。
- 不動産を「やむなく売却」して納税するリスク
- 相続人間で「納税額の負担割合」をめぐる争い
- 手元資金が不足している相続人の困窮
また、法人契約の保険を使えば、事業承継と納税資金対策を両立することも可能です(専門家の設計が必要)。
5. よくある失敗事例と注意点
生命保険を使った生前対策にも、注意点があります。以下は代表的な失敗例です。
❌ 保険金の受取人が"相続人以外"になっており、非課税枠が使えなかった
❌ 保険の名義変更で"贈与税"がかかってしまった
❌ 契約内容を家族が知らず、保険金の請求ができなかった
❌ 兄弟間で「不公平だ」と不満が出て、逆に争族に…
生命保険は契約内容の設計が命です。
相続との関係を意識して、「誰が契約者で、誰が被保険者で、誰が受取人か」を明確にし、家族にも伝えておくことが重要です。
6. まとめ:生命保険で"争続"を防ぐ
生命保険は、相続対策の中で唯一、すぐに現金を残せる手段です。
- トラブルの予防
- 相続税の節税
- 納税資金の準備
- 特定の相続人への配慮
これらを一手に解決できるポテンシャルを持っているため、早い段階での検討がおすすめです。
また、信託や遺言など他の制度と組み合わせることで、さらに強固な生前対策が可能になります。

7. ご相談のご案内(CTA)
「うちの家族構成でも、保険を使った対策は有効?」
「保険設計と遺言、どちらを優先すべきか悩んでいる…」
そんなお悩みがありましたら、ぜひアイリス国際司法書士・行政書士事務所にご相談ください。提携の保険会社の方のご紹介等可能です。
保険の仕組みと法律の両面から、オーダーメイドの生前対策をご提案いたします。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
最新のブログ記事
家族信託を使えば万事解決?司法書士が解説する「万能神話」の落とし穴【2026年版】
「家族信託を使えば、相続も認知症も全部解決する」
最近、こうした説明を耳にする機会が増えました。
成年後見を使えば自由にできる?司法書士が警鐘する「大きな誤解」と本当の役割【2026年版】
「認知症になったら成年後見を使えば大丈夫」
「後見人がいれば、財産は自由に動かせる」
【第1回】年明けからの再スタート ― “直前期に回す道具”を作る意味
司法書士試験の合否を分けるのは「年明けから4月の過ごし方」と言われます。
この時期は新しい知識を増やすよりも、「直前期に回す道具」=自分専用の復習ツールを整えることが最重要です。
本記事では、合格者が実践した"自作の学習道具づくり"の意義と、年明けからの学習設計を具体的に紹介します。


