相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第3回】該当ありの照会結果~生命保険の契約が見つかった後の手続きと注意点~
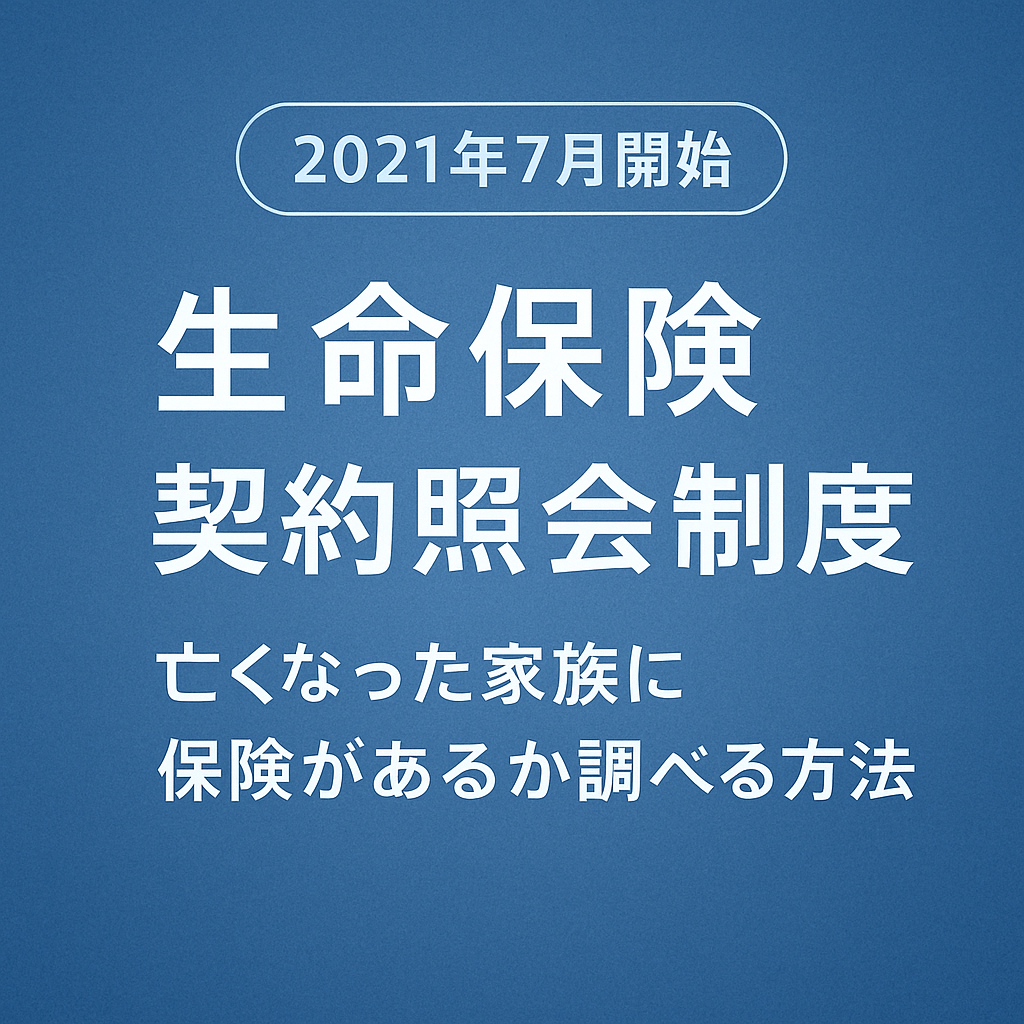
「生命保険契約照会制度」で保険契約の存在が判明した――。これは相続人にとって大きな第一歩ですが、ここからが本番です。どのように保険会社に連絡し、必要書類を揃え、保険金の請求に至るのか。手続きを誤ると、余計な時間と手間がかかるばかりか、場合によっては請求権を失ってしまうことも。この最終回では、照会後に「該当あり」の結果が出たときの対応を、実務の視点からわかりやすく解説します。
【目次】
- 「該当あり」の照会結果が届いたら
- 保険会社への連絡と確認事項
- 保険金請求に必要な書類と手続き
- 相続手続きとの関係と注意点
- よくあるトラブルと対処法
- まとめ:確実な請求で大切な保険を受け取るために
- 【CTA】相続手続きの専門家に相談して、確実な受け取りを
1. 「該当あり」の照会結果が届いたら

照会結果に「該当あり」と記載されている場合、被相続人が1社以上の生命保険に加入していたことになります。通知には、以下のような情報が記載されています:
- 保険会社名
- 契約の有無(該当の有無)
- 担当窓口の連絡先
なお、具体的な契約内容(契約金額や受取人など)は記載されていません。詳細を知るには、記載された保険会社に個別に連絡する必要があります。
2. 保険会社への連絡と確認事項

照会結果を受け取ったら、まずは保険会社に電話や書面で連絡を取りましょう。その際には、以下の点を確認します:
- 契約者・被保険者・受取人の氏名と一致の有無
- 契約内容(保険金額、保険の種類、満期や解約の状況)
- 必要書類の一覧
- 請求期限(時効)
時効に注意!
生命保険金の請求権は、原則として3年で時効を迎えます(商法第95条)。死亡から3年が経過すると、保険金の請求ができなくなる可能性があるため、速やかな対応が重要です。
3. 保険金請求に必要な書類と手続き
保険会社によって若干の違いはありますが、一般的に必要とされる書類は以下の通りです:
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 被保険者の住民票除票
- 請求者(受取人)の本人確認書類
- 戸籍謄本(関係性を証明するため)
- 保険証券(ある場合)
これらの書類を提出後、内容に不備がなければおおよそ1~2週間程度で保険金が支払われることが多いです。
4. 相続手続きとの関係と注意点

【保険金は原則として「相続財産」ではない】
生命保険金は、契約時に指定された「受取人」に直接支払われるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。つまり、受取人が指定されている場合は、その人の「固有の財産」となります。
ただし、次のような例外には注意が必要です:
- 受取人が「相続人」などとしか記されていない場合:法定相続人全員が対象となり、相続財産として扱われる可能性があります。
- 受取人がすでに亡くなっていた場合:保険会社との調整が必要になり、再度請求者の確定が求められます。
5. よくあるトラブルと対処法

生命保険の請求をめぐっては、以下のようなトラブルも散見されます:
- 保険契約が失効していた
- 保険証券が見つからず、契約の詳細確認に時間がかかる
- 受取人が不明確で、家族間で争いが生じる
- 必要書類がそろわず、請求手続きが止まる
このような事態を防ぐには、生命保険契約照会の段階から、専門家と連携して進めることが有効です。司法書士や行政書士、相続に強い専門家に早期相談することで、手続きの不備やトラブルを未然に防げます。
6. まとめ:確実な請求で大切な保険を受け取るために
生命保険契約照会制度は、相続人にとって重要な「気づき」のきっかけを与えてくれる制度です。しかし、照会で「該当あり」となっても、そこから保険金を受け取るには多くの確認と手続きが必要です。
- 速やかな保険会社への連絡
- 書類の正確な準備
- 相続手続きとの整合性確認
これらを一つずつ丁寧に進めることが、トラブルを防ぎ、確実に保険金を受け取る鍵となります。

【CTA】専門家と一緒に、確実な保険金の受け取りを
生命保険の請求は、相続の一部にすぎません。その後の不動産名義変更、遺産分割協議、相続税の申告など、多くのステップが控えています。
当事務所では、相続全般にわたるご相談を受け付けております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※ノウハウを教えてほしいという相談にはお答えできません。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



