相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【論点】「所有者不明土地」「空き家」を次世代への資産承継の模索
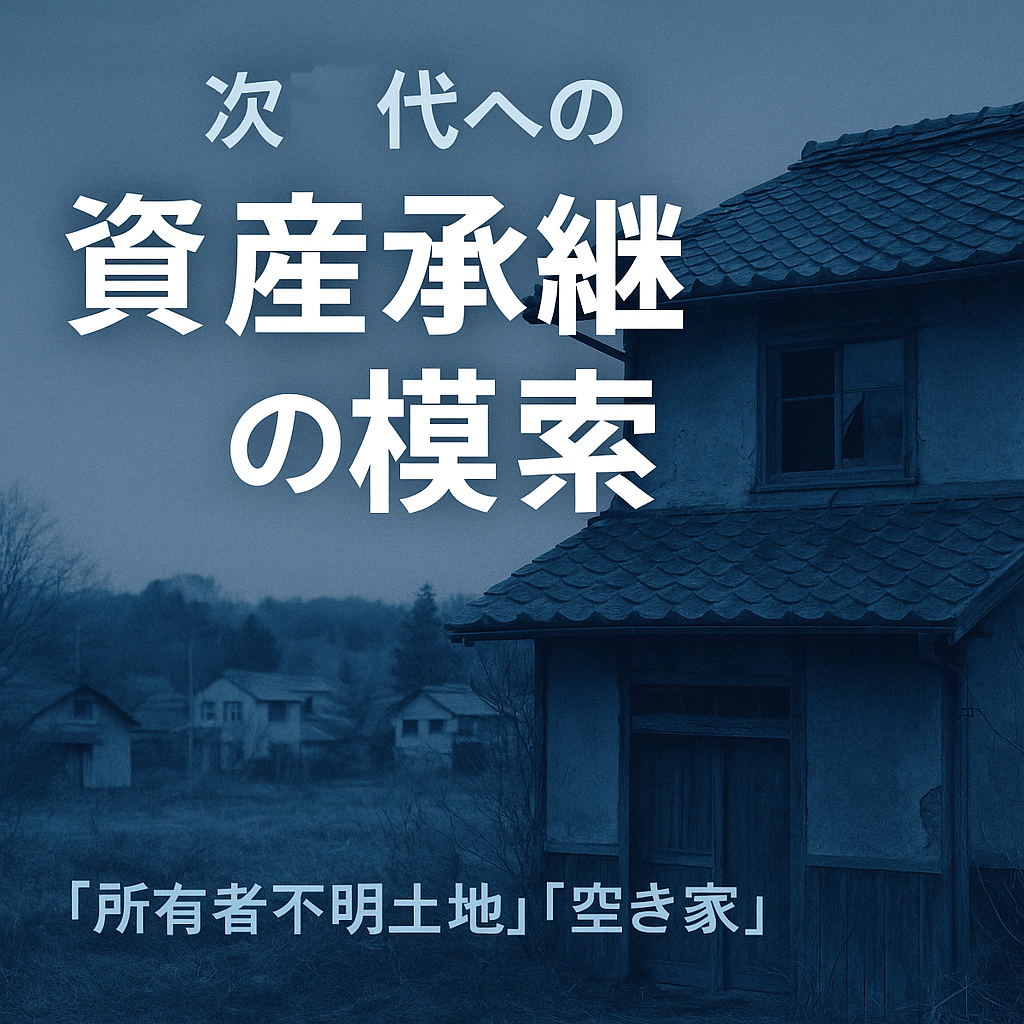
増加する空き家や所有者不明土地の問題に対し、日本政府は様々な制度整備を進めています。戦後の財産分散から始まった資産の細分化と価値の低下は、現代において大きな社会課題へと発展しています。本記事では、「空き家対策特別措置法」や「所有者不明土地法」などの制度を通して、次世代への円滑な資産承継のあり方を探ります。
■目次
- 所有者不明土地問題の深刻化
- 空き家対策特別措置法の施行とその効果
- 所有者不明土地法の概要と課題
- 相続登記義務化による改善の期待
- 資産承継を見据えた生前対策の重要性
1.所有者不明土地問題の深刻化

全国の土地面積のうち、約20%が「所有者不明土地」とされています。これは、相続登記が行われず、登記簿上の名義人が亡くなったまま放置されている土地が主な原因です。とくに山林や農地では、「利用価値がない」「売れない」といった理由で登記や管理が後回しになりがちで、結果として地域の活性化や防災、インフラ整備を妨げる大きな要因となっています。
2.空き家対策特別措置法の施行とその効果

2015年に施行された「空き家対策特別措置法」は、管理されていない危険な空き家を「特定空き家」として指定し、市町村が所有者に対し指導・勧告・命令を行える制度です。命令に従わない場合は行政代執行により解体されることもあります。法施行後、空き家の調査が進んだことで、地域の景観改善や防犯効果が見られる一方で、所有者不明の場合の対応には限界があります。
3.所有者不明土地法の概要と課題
2019年施行の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(通称:所有者不明土地法)」では、一定の手続きを経れば、所有者が不明な土地を民間や行政が暫定的に利用できる制度が設けられました。しかし、土地の正確な権利関係の調査には時間と費用がかかり、また所有者が判明した際の対応も複雑です。制度の利用促進には、専門家の支援や行政のノウハウ蓄積が不可欠です。
4.相続登記義務化による改善の期待

2021年の民法・不動産登記法改正により、2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まりました。これにより、相続により不動産を取得した相続人は、3年以内に登記申請をしなければならず、怠ると過料(罰金)の対象となります。この制度により、所有者不明土地の増加に歯止めがかかることが期待されていますが、相続人が複数いる場合の調整や、放棄された財産の扱いなど、実務上の課題も残っています。
5.資産承継を見据えた生前対策の重要性
制度による対応が進む一方で、根本的な解決には、生前の段階で「誰に」「何を」「どう渡すか」を明確にしておくことが重要です。遺言書の作成や家族信託の活用により、将来の相続争いや放棄のリスクを減らすことができます。また、使われなくなった不動産を早期に売却・寄附・活用することも、資産の流動性を高め、社会全体にとっても有益な選択肢となります。
■まとめ
所有者不明土地や空き家の増加という課題に対し、制度的な対応が進みつつありますが、それだけでは十分とは言えません。財産の承継は制度と個人の意識の双方がかみ合って初めてスムーズに行われます。そうした制度的背景と今後の方向性を見てきました。

最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



