【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
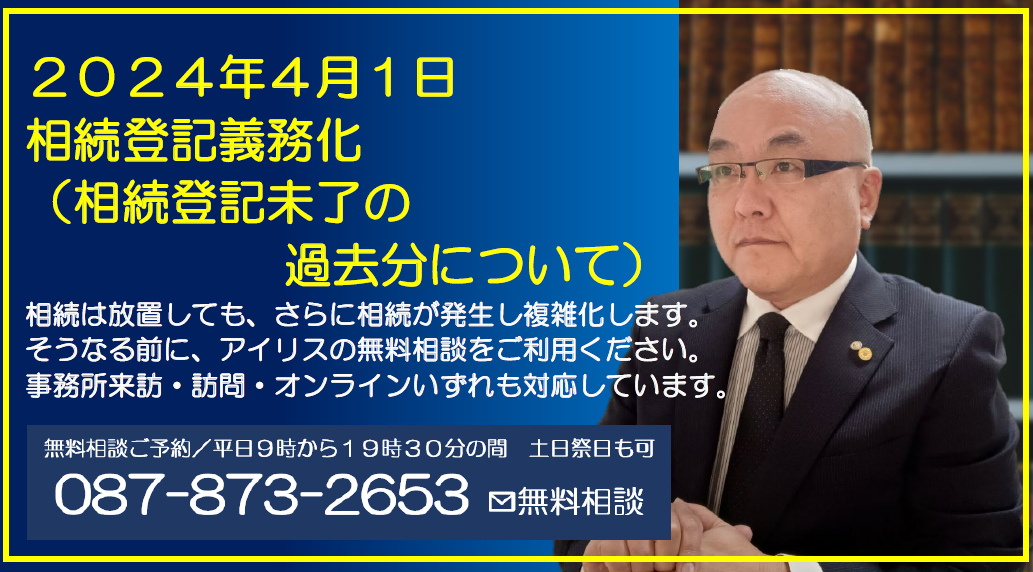
令和6年4月1日相続登記義務化について、過去分の相続登記未了の物件についてのご質問がありましたので、わかりやすく解説したいと思います。結果から言いますと、今回の相続登記義務化は、過去分も対象となります。未登記建物についての問い合わせもありましたので、併せて確認します。それでは見ていきましょう。
目次
1.相続登記義務化について
2.過去に発生した相続で相続登記未了の物件
3.未登記不動産について
4.まとめ
1.相続登記義務化について
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。(法務省HP引用)
2.過去に発生した相続で相続登記未了の物件
過去に発生した相続で相続登記未了の物件も、令和6年4月1日開始の相続登記義務化の対象となります。
実際に、このような物件の相続登記を受任する場合があるのですが、相続人の調査が長引く恐れがあります。戦前の旧民法と戦後の民法では、相続人の考え方が大きく異なるため、登記簿に掲載されている名義人及び名義人から家督相続をした方の亡くなるタイミングによっては、膨大な数の相続人との遺産分割協議となってしまうケースが多いです。
相続登記義務化は令和6年4月1日施行ですが、このような物件をお持ちの方は、早めに専門家に相談をすることをお勧めいたします。

3.未登記不動産について
この未登記不動産の所有者が変更となった場合(相続により所有者が変更になった場合を含みます)の届出先は、高松市役所では「資産税課」が担当窓口になっています。当然ですが、登記簿が法務局に存在しませんので、相続登記義務化の対象ではありません。
また、届け出期間は高松市HP上では、この届出は義務化されており、
(1)固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者であることを知った日から3か月以内に現所有者申告を提出しなければなりません。
(2)現所有者の申告を正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
と、罰則付きのものになっています。
しかし、3か月以内に遺産分割をして帰属先を決めるのは困難ですので、その場合には、相続人全員の同意書の添付で受け付けていただけます。
(未登記建物の申告の添付書類)
①遺産分割協議前
亡くなられた方の除籍謄本
相続人の戸籍謄本
全員の同意書及び印鑑証明書
➁遺産分割協議後
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
※高松市役所では、コピー可となっていますが、自治体によっては原本を要求され、自治体でコピーする場合もございます。また、添付書類も異なる場合がありますので、あらかじめ担当窓口にご確認ください。
未登記不動産を取り壊す場合、役所への届出をしないでいると、いつまでも固定資産税を支払い続けることになりますので、窓口に行き「未登記建物を取り壊したので届出がしたいのですが」と言っていただければ、対応してくれます。
この未登記物件の届出につきましては、罰則もあります。
未登記不動産の役所への届出は、義務化されています。正当な理由なしに3か月間届出を怠ると10万円以下の過料に課せられます。
相続放棄をする相続人がいるなどして、3か月以内に遺産分割協議ができない場合には、予め窓口に相談をしておいた方がいいと思われます。
4.まとめ
令和6年4月1日相続登記義務化では、過去分の相続についても対象になります。相続登記未了期間が長いと、相続人の調査が膨大になる可能性があります。
未登記物件については、令和6年4月1日相続登記義務化の対象とはなりません。しかし、役場に所有者の変更を届ける必要があります。これを怠ると罰則もあります。
アイリスでは、相続関連の無料相談会を随時実施しております。不安のある方は、是非ご利用ください。
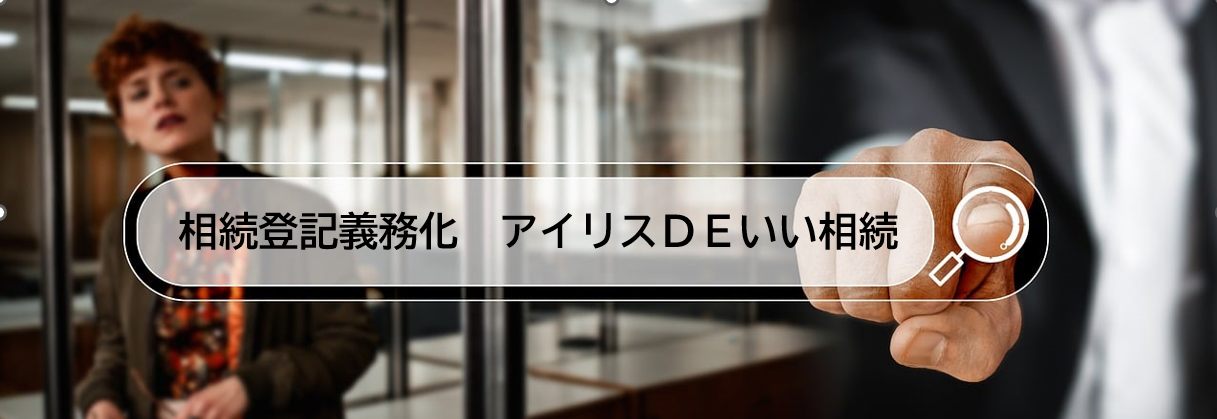


高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。