【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
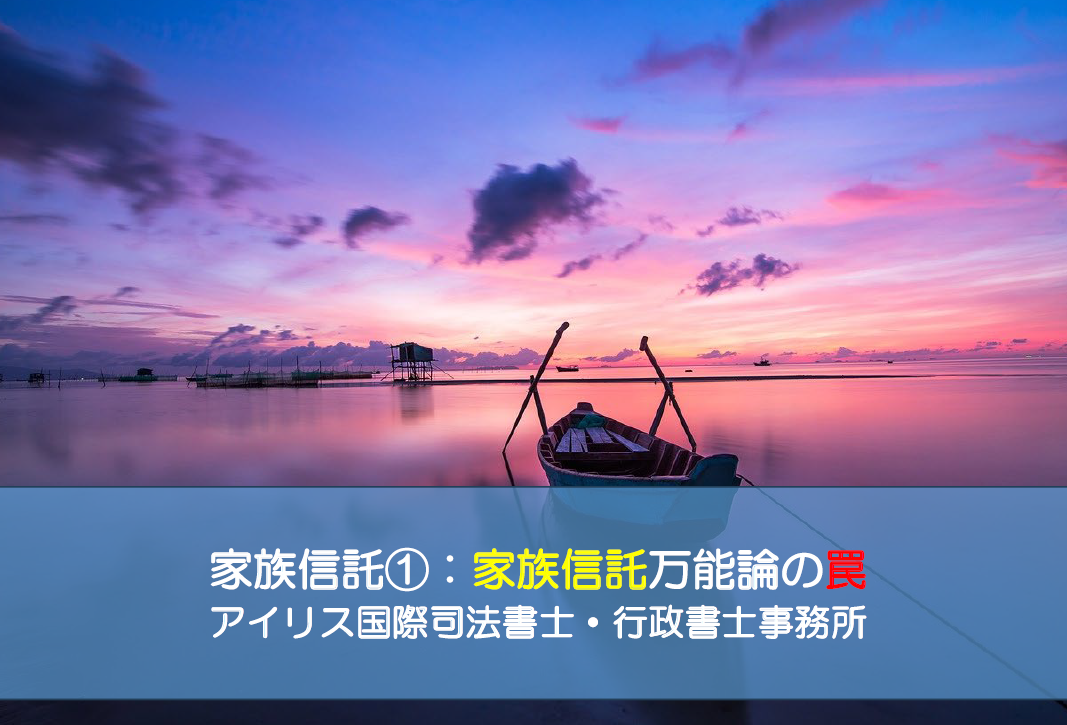
昨年、雑誌に取り上げられたのち、問い合わせが増えた「家族(民事)信託」ですが、雑誌に書いてあるような万能な制度ではありません。勿論、必要な方にとっては、非常に有効な相続対策の手段となりますが、だからと言って全員にメリットがある制度、というわけではないです。家族信託を締結するには、それなりに費用が掛かります。自身の相続対策に必要かそうでないかの参考にしてみてください。
※アイリスでは、きっちり説明の上、納得いただいた後に家族信託の手続きに入るようにしております。
目次
1.家族信託とは
2.家族信託の問題点
3.家族信託が必要ないケース
4.まとめ
家族信託とは、家族間で信託契約を結ぶことです。「信託」とは、自分の財産を家族や専門家などの信頼できる人に託して、あらかじめ決められた目的を達成するようにその財産を管理し、運用することを言います。
私の知り合いの保険会社の社員の方から「家族信託で受託者を信頼できる弁護士を指定して、父親の全財産を運用をしていたのに、暴走して、残された家族の意見も聞かないで好き勝手やっている。」と言われたことがあります。そもそも契約時に、家族信託で全財産を財産運用する必要性があったのか?また、受託者をその弁護士に選んだのはなぜなのか?という疑問が残ります。家族信託は「信頼できる人」にお願いすべきで、契約時に家族全員の同意をとらずに契約をしてしまっている可能性があります。

受託者の権限は大きいです。そして、受託者は信託目的達成のために受益者(おそらく父親)のために、財産の運用をしているものと考えます。ですので、ご家族との話し合いをせずに契約してしまうと、家族にとって意にそぐわない状態になってしまうケースがあります。このように、受託者の権限が大きいからこそ、家族全員と話し合って、本来は「信頼できる人」を指定することが重要なのです。
※受益者を委託者以外の第三者を指定すると「贈与税」の対象となります。
①親族関係に争いがあるケース

家族信託契約は委託者と受託者のみで行うことができます。他の家族の同意は不要です。(現状は、家族の同意書を取得するのが通常です。のちの紛争防止のため。)
家族信託契約をすることによって、後見のように家庭裁判所などの第三者の監督を受けずに家族だけで管理できる仕組みを作ることができます。他の家族に伝えないで家族信託契約を締結することで、話し合い不足によって起こるトラブルにつながる可能性があります。
➁信頼できる親族がいないケース

受託者の権限の幅が非常に大きいため、信託財産の管理・運用・処分をするだけでなく、信託契約で定めた権限を行使することができます。受託者は、自分自身の財産と信託財産はわけて管理し、自分の財産以上に慎重に扱う義務を負っています。つまり、受託者だけの判断で財産管理ができてしまうので、場合により横領のリスクもあります。このようなことから、財産管理をしっかりと任せられる人がないない場合には家族信託をすべきではありません。
③不動産の売却・活用や多額の金銭の支払いなどの予定がないケース
委託者の自宅や賃貸物件(アパートなど)の貸付・売却などの予定がない、親の認知症によって凍結される財産がないもしくは凍結されても困らない、親の介護や治療、生活、施設への入居などの出費に関して信託財産からの収益を当てにしなくてもいいなどが挙げることができます。
このような場合には、遺言書で相続の対策をしておけば十分対応できるため、家族信託を要しません。
④生前贈与などによって資産譲渡が完了しているケース
つまり、父親から生前に子供たちに資産譲渡等により管理すべき財産が承継されている場合です。わざわざ家族信託を新たに結ぶ必要はありません。
家族信託は、本人の財産を管理する制度であり、子供たちに贈与済みの財産を管理することはできません。
➄資産より身の回りの管理をしてほしいケース
家族信託で対応できるのは、あくまで信託財産に係る範囲のみであり、介護・治療・施設への入所などの法律行為をする「身上監護」がご希望である場合には、任意後見などの成年後見制度を検討すべきです。
また、成年後見制度利用による身上監護がなくても、介護を受ける本人のご家族が近くに住んでいる時は、手続きの代行を認めてくれることが多いです。
※私が勤めていた有料老人ホームでも、契約時、ご家族の署名で大丈夫でした。しかし、本来は契約は当人同士、つまり、サービス提供者とそれを受ける方との間で行うのが通常ですが、「ご本人のためになる」との理由でOKにしていました。
⑥家族信託できない財産が対象の場合
(1)農地
農地は信託法とは別に農地法という法律の規制を受けるため、信託財産とするには、農業委員会等の許可や届け出が必要となります。
(2)借地
借地権の譲渡に当たるため地主の承諾が必要となります。承諾なしに信託財産として管理してしまいますと、「無断譲渡」とみなされ、民法612条2項の規定により契約を解除される可能性があります。
(3)上場株式や投資信託
上場株式や投資信託について家族信託に対応する証券会社が現状少ないため、信託口口座が開設できないことが多いです。
このように、家族信託できない財産については、裁判所の監督は受けますが、後見制度で管理するという手法を使うことができます。
このように、家族信託は万能ではありません。また、全ての家族に当てはまることもありません。他の制度との併用で、ご利用者とそのご家族が納得いく形で、信頼できる方に管理してもらうことが重要となってきます。

高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。