相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
第5回 「相続対策、まだ早い」は大間違い! 〜準備の早さが“家族を守るカギ”〜
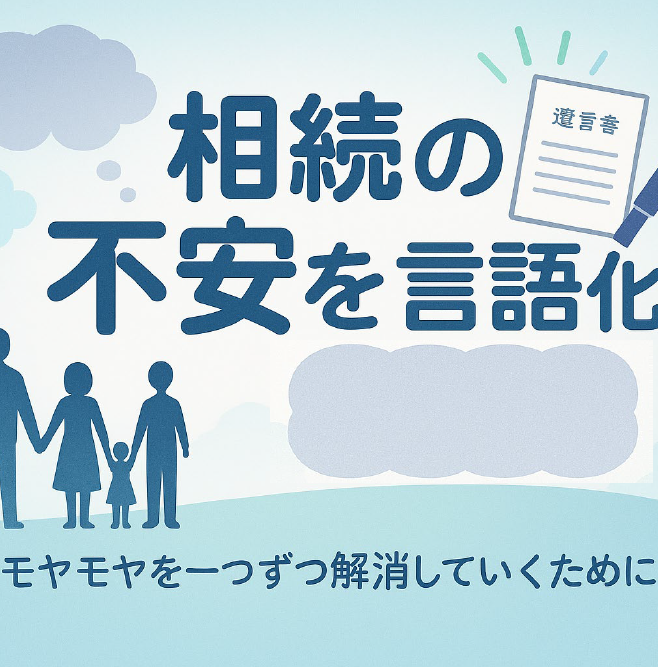
「うちはまだ元気だし、相続なんて考えるのは早いよ」
そう思っていませんか?
しかし、相続問題は「元気なうち」にこそ備えておくべきもの。
実際、相続トラブルの多くは、「何も決めていなかったこと」が原因で起こります。
そして、認知症や突然の病気、事故などにより、手遅れになるリスクも…。
この記事では、「相続対策はなぜ早めに始めるべきなのか」「実際に起こっているトラブル事例」「どんな対策があるのか」について解説します。
家族の未来を守るため、今すぐ一歩踏み出しましょう。
【目次】
- 相続対策を"先延ばし"にする人が多い理由
- 先延ばしが招く3つの重大リスク
- 実際にあった"手遅れ"の相続トラブル
- 生前からできる相続対策とは?
- まとめ:今こそ「相続対策元年」にしよう
- 無料相談のご案内(CTA)
1. 相続対策を"先延ばし"にする人が多い理由

「まだ健康だし」
「子ども同士は仲がいいから揉めないよ」
「財産もそんなにないし」
多くの人がこのように考えて、相続のことを真剣に考えるのを後回しにしています。
実際に、2023年の民間調査によると、「相続対策をしていない理由」として最も多かったのは、
**「まだ元気だから」**が約60%という結果に。
しかし、人生は思い通りには進まないことも多く、「想定外」によって家族が困ることも少なくありません。
2. 先延ばしが招く3つの重大リスク

リスク①:認知症で判断能力を失うと、対策できなくなる
認知症などで判断能力が低下すると、遺言の作成や贈与契約などの法律行為ができなくなります。
その結果、相続対策が一切不可能になってしまいます。
リスク②:突然の病気や事故で、遺言を残せないまま他界
病気や事故は予告なく訪れます。
もし遺言がなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要になり、争族トラブルに発展することも。
リスク③:時間が経つほど対策の選択肢が減る
たとえば、生前贈与の活用には数年単位の計画が必要なこともあります。
ぎりぎりになってからでは、節税にも限界があり、最終的に家族に多大な税負担を残す可能性も。
3. 実際にあった"手遅れ"の相続トラブル

ケース1:認知症で遺言が作れず、兄弟間で大揉めに
母親が元気なうちに遺言を作るよう勧めていたが、「まだ大丈夫」と先延ばしにしていたところ、突然の認知症発症。
判断能力が認められず、遺言が作成できなくなった結果、相続人同士の話し合いがこじれて、家庭裁判所での調停にまで発展。
ケース2:不動産の名義変更が間に合わず、売却不能に
父の急逝後に不動産を売却しようとしたが、相続登記も遺言書もなく、10人以上の相続人で話がまとまらず、不動産が塩漬けに。
4. 生前からできる相続対策とは?

● 遺言書の作成
自筆証書遺言や公正証書遺言で、財産の分け方を明確に。
※法的な要件を満たさなければ無効になるため、専門家の関与が推奨されます。
● 任意後見契約の締結
判断能力があるうちに、将来の後見人をあらかじめ指定しておく契約。認知症対策に有効。
● 家族信託の活用
財産を信頼できる家族に託すことで、柔軟な財産管理・承継が可能になります。
特に不動産や中小企業の事業承継に効果的。
● 生前贈与・相続税対策
暦年贈与や相続時精算課税制度など、税制を活用して財産の一部を先に渡すことで、節税効果が期待できます。
5. まとめ:今こそ「相続対策元年」にしよう
相続対策は、「まだ早い」と思っているうちがチャンスです。
万が一が起こってからでは、できることは限られてしまいます。
家族のために、将来のトラブルを未然に防ぐために。
そして、自分の想いをきちんと形に残すために。
相続対策は、あなたの"今"の決断から始まります。

6. 無料相談のご案内【CTA】
✅「相続の話なんて、まだ早い」と思っていませんか?
✅「何から始めればいいのかわからない」と感じていませんか?
当事務所では、相続対策に関する無料相談を実施中です。
一緒に"あなたの想い"をカタチにしましょう。
📞お問い合わせはこちら
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
▶ 電話:087-873-2653
▶ メール:irisjs2021@gmail.com
▶ お問い合わせフォーム:[https://www.irisjs2021.com/]
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



