【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
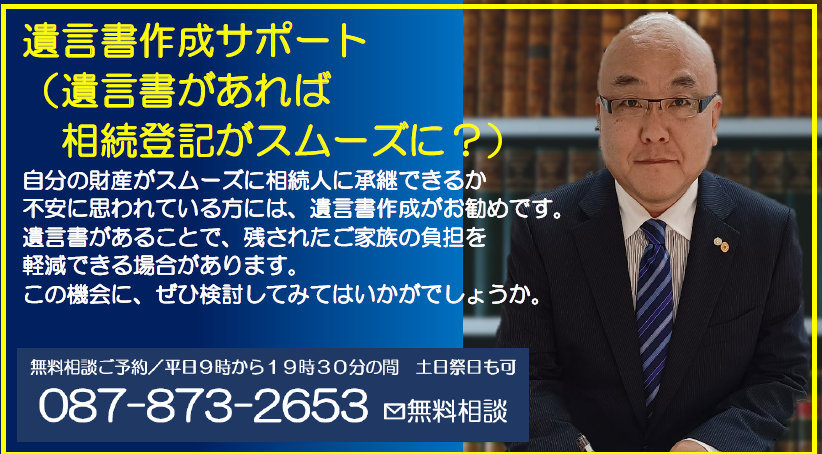
相続手続きで遺言書があった場合、なぜ相続人の負担が軽減されスムーズに手続きを進めることができるのかについて解説したいと思います。遺言書があったおかげで、揉めた話もよく聞くのですが、揉める事例(相続人以外の第三者に全財産を遺贈する)などについても解説しております。
目次
1.相続手続きに遺言書があった場合の「スムーズになる」とは
2.遺言書がなかった場合の相続手続き
3.亡くなったからが、全財産を愛人等(第三者)に遺贈した場合
4.遺留分とは
5.遺言書で相続財産の帰属先が決まる
1.相続手続きに遺言書があった場合の「スムーズになる」とは
「楽」という表現は、相続手続きにおいて遺言書があった場合に、手続きがスムーズかつ簡単に進むことを意味しています。遺言書がある場合、遺された人々や財産の分割方法が明確に示されており、法的手続きの際に問題が生じることが少なくなります。また、遺言書によっては、相続人間の紛争を回避するために、明確な規定がなされていることもあります。このため、遺言書がある場合は、遺産分割や手続きのトラブルを避けることができるため、「スムーズに手続きができる」と表現されることがあります。
それでは、遺言書がなかった場合、どうなるのでしょうか。
2.遺言書がなかった場合の相続手続き
遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産を遺産分割協議により分割しなければなりません。そんなの、家族みんな仲がいいから大丈夫という方もいるかもしれません。しかし、今仲が良くても相続財産の話し合いになったとき、少しでも公平でなさそうな場合には、文句を言う相続人が出てくるとも限りません。また、離婚した前妻の子供も相続人になります。こうなってくると、一気にハードルが高くなってきます。もし、前妻の子供を入れないでなされた遺産分割協議は「無効」です。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員参加が条件だからです。文句を言っている相続人を外しても同じ結果になります。
遺産分割協議がうまくまとまらない場合、遺産分割調停を経て審判まで行きますと、家族の関係はかなり険悪になります。

3.亡くなったからが、全財産を愛人等(第三者)に遺贈した場合
遺言書はすべてを解決する万能なツールなのかというとそうではありません。内容次第で、前向きにも後ろ向きにもなってしまう可能性があります。なぜなら、遺言書は、遺言者の一方的な意思表示により作成され(もちろん法廷の要件はありますが)、遺言者の死亡によりその遺言書は効力を生じます。その内容が「すべての財産を愛人に遺贈する」でもです。ただし、この遺言が、愛人契約をするために作成されたなどの事情(公序良俗違反)がある場合は、相続人から無効を主張することができますが、主張・立証が困難な場合もあるかもしれません。それでは、残された相続人たちは、遺言書の効力のために相続財産を全くもらえないのでしょうか。
4.相続人の遺留分とは
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。ネガティブな遺言書の内容であった場合、相続人の遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
※遺留分は、相続人の相続の権利を守る最後の砦となります。
5.遺言書で相続財産の帰属先が決まる
遺言書がない場合、「遺産分割協議」を経なければ、相続財産の帰属先は決まりません。
遺産分割協議が固まるまでは、遺産が宙に浮く形になってしまうわけです。遺産分割協議をまとめるために、専門家に依頼したとしても、費用・時間・手間が残された相続人の方に負担となってしまうわけです。
一方で、遺言書を作成し相続財産の帰属先を決めておくことで、相続発生時に遺産の帰属先は、一応決まるわけです。その後に、相続人全員の協議により変更はできるものの、宙に浮く状態を避けることができます。
先ほど解説した遺留分も、帰属先が気に食わないから、最低限、私(相続人)の取り分をくださいと請求するものです。つまり、相続財産の帰属先が決まった後の話になります。

6.まとめ
相続財産の帰属先の話をしてきましたが、遺言書を作成することで、遺言者の「想い」を形にすることができるというだけでなく、その後に発生する遺産分割協議がなくても相続財産の帰属先が決まるという利点があります。つまり、相続登記や預金の名義変更の手続きが、遺言書があればスムーズに進めることができます。
欧米では遺言書は紳士のたしなみと言われるくらい一般的ですが、日本では約10%ほどの利用しかありません。
遺言であなたの「想い」を形にしておくことで残されたご家族の負担が減ることも大きな利点です。
ぜひ遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。


高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。