相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(司法書士試験)全肢検討の重要性

司法書士試験において、択一式問題の「全肢検討」を行うべきか否かは多くの受験生にとって悩ましい問題です。特に午後の択一試験では、その後に控える記述式試験の時間配分に影響を与えるため、限られた時間の中でどのように取り組むかが鍵となります。令和6年度からは記述式試験の配点が従来の倍となり、その重要性が一層高まっています。
目次
1. 全肢検討の意義と重要性
2. 記述式試験の配点増加の影響
3. 全肢検討を行うべき理由
4. 時間管理の工夫
まとめ
1. 全肢検討の意義と重要性
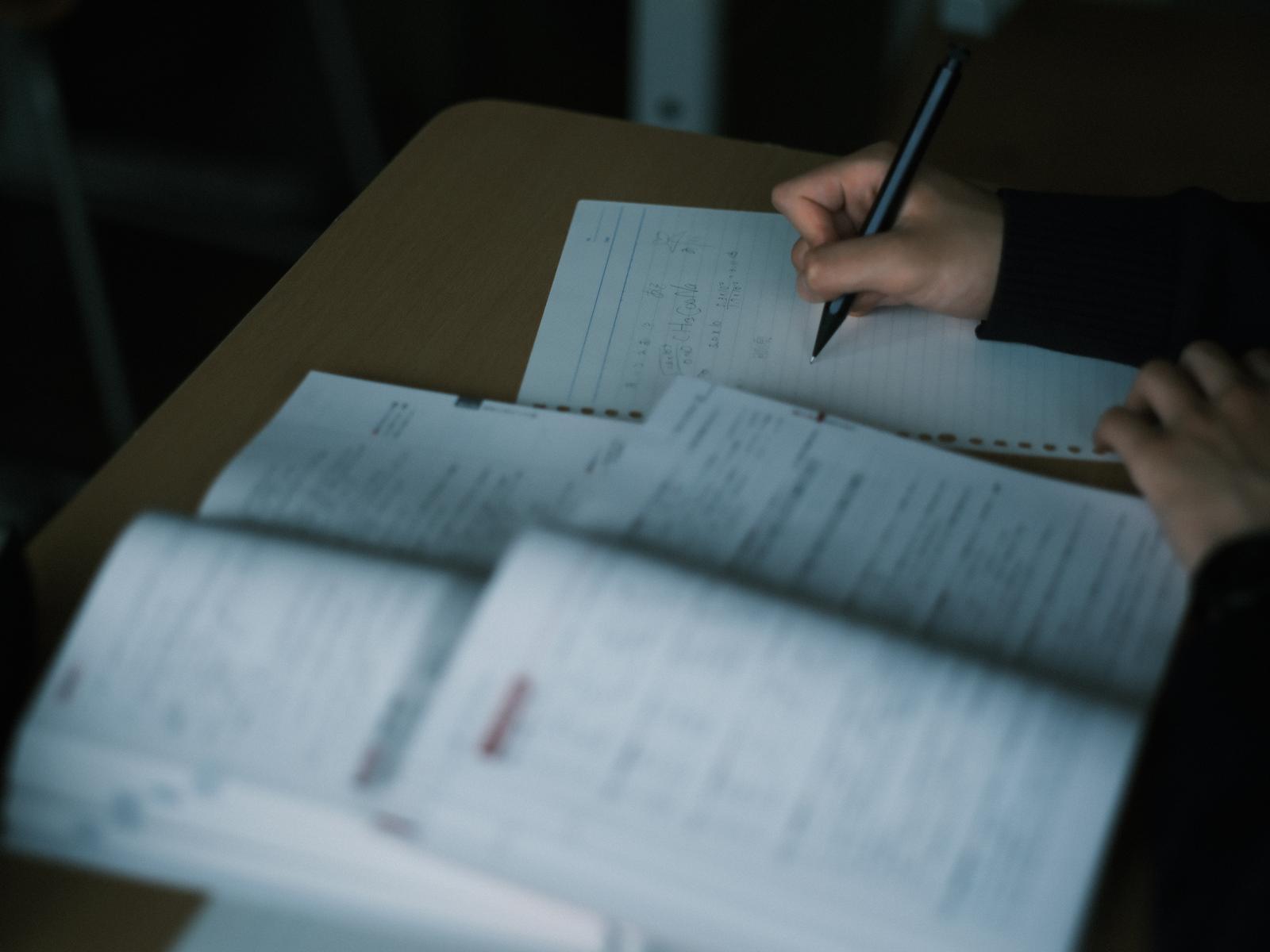
全肢検討とは、択一問題の各選択肢を一つずつ確認し、正誤を判断する方法です。司法書士試験は非常に高い精度が要求されるため、一つでも間違えれば合否が左右される可能性があります。このため、特に午前の択一試験では、時間が許す限り全肢検討を行うことで、確実に正答を導き出すことが可能です。
午後の択一試験においても、全肢検討は極めて重要です。確かに午後試験は時間が限られており、特に記述式試験の時間配分を考慮すると、択一式試験に十分な時間をかけることは難しいかもしれません。しかし、全肢検討を行わずに「おおよそ正しそうだ」と判断して進めることは、誤答のリスクを高めます。午後の択一は、記述試験以上に時間のプレッシャーがかかるため、焦って解答を進めることが不正解を招く原因となるのです。
2. 記述式試験の配点増加の影響
令和6年度からは、記述式試験の配点が従来の倍に引き上げられるため、記述に重点を置くべきだという考え方が強まることが予想されます。記述式試験での得点が合否に与える影響が大きくなるため、時間をかけて丁寧に取り組むことは重要です。しかし、だからといって択一式試験を軽視するのは危険です。択一式試験で十分な得点を得られなければ、記述でどれだけ得点を伸ばしても合格は難しくなります。
記述式試験の配点増加に伴い、確かに午後の試験全体における記述のウェイトが高まりますが、択一式試験での失点は依然として致命的です。司法書士試験は総合点で合否が決まるため、どのセクションでも高得点を目指す必要があります。特に午後の択一で正確な解答を導き出すことは、記述に充てる時間を増やすためにも不可欠です。全肢検討を怠ると、誤答が重なり、最終的な得点に悪影響を及ぼす可能性があります。
3. 全肢検討を行うべき理由

(1) 誤った選択肢を確実に排除するため
択一式試験では、複数の選択肢の中から正答を選ぶ形式です。一見正しそうに見える選択肢が複数含まれていることが多いため、全肢検討を行わないと誤答を選んでしまうリスクが高まります。全肢検討を行うことで、各選択肢の正誤を慎重に判断し、誤った選択肢を確実に排除することができます。これは特に午後の択一において、難易度が高くなってくる問題に対して有効です。
(2) 自己の知識の確認と補強
全肢検討を行うことで、自分の知識の確認ができ、理解の曖昧な部分を見直すきっかけにもなります。司法書士試験では、一問一問が重要であり、各問題が自身の知識の正確さを問うものとなります。全肢検討を通じて、自分の理解が正しいかどうかを確認することが、試験全体の正答率を高めるために欠かせません。
(3) 試験問題の作問傾向に対応するため
司法書士試験の択一式問題は、選択肢の作り方に特徴があります。特に、正解を導き出すためには細かい知識が必要な場合が多く、全肢を検討しないと誤解や見落としが発生しやすいです。また、選択肢の中には一部が正しいものや、微妙な違いで正誤が分かれるものもあり、こうした問題に対処するためには、全肢検討が必須です。
4. 時間管理の工夫
午後の択一試験では、記述式試験のための時間を確保する必要があるため、全肢検討を行いつつも効率的に時間を使う工夫が求められます。以下の方法が有効です。
(1) 優先度を決める
全肢検討を行うにあたっても、すべての問題に同じ時間をかける必要はありません。自分が得意とする分野や確実に解ける問題には短時間で取り組み、難しい問題や迷う問題には少し時間を割くというように、優先度を決めて取り組むことが大切です。これにより、時間を効率的に使いながら、全肢検討を行うことが可能になります。
(2) 問題をスキップして戻る戦略
どうしても迷う問題があった場合は、一度スキップして次に進むことも有効です。すべての問題を一通り解いた後、残った時間で改めて迷う問題に取り組むことで、時間を無駄にせずに全体をカバーできます。全肢検討を行う場合でも、まずは問題全体に目を通し、重要度の高い問題や確実に解ける問題から優先的に解答することで、時間を効率化できます。
(3) 時間配分の事前練習
全肢検討を行いつつ、記述試験の時間を確保するためには、日頃から模擬試験や過去問を使って時間配分を練習することが重要です。自分がどれくらいの時間で択一を解き終えることができるのかを把握し、その中で全肢検討を行う余裕があるかどうかを確認しましょう。実際の試験と同じ環境で何度も練習することで、当日も自信を持って取り組むことができます。
まとめ
司法書士試験の午後択一では、時間の制約が厳しくなるものの、全肢検討を行うことは依然として重要です。記述式試験の配点が増えたことで、時間配分のバランスは重要になりますが、択一でのミスを防ぐためにも全肢検討は必要です。確実な得点を狙い、総合点を高めるために、全肢検討を行いつつ効率的な時間配分を身につけることが、合格への近道となるでしょう。
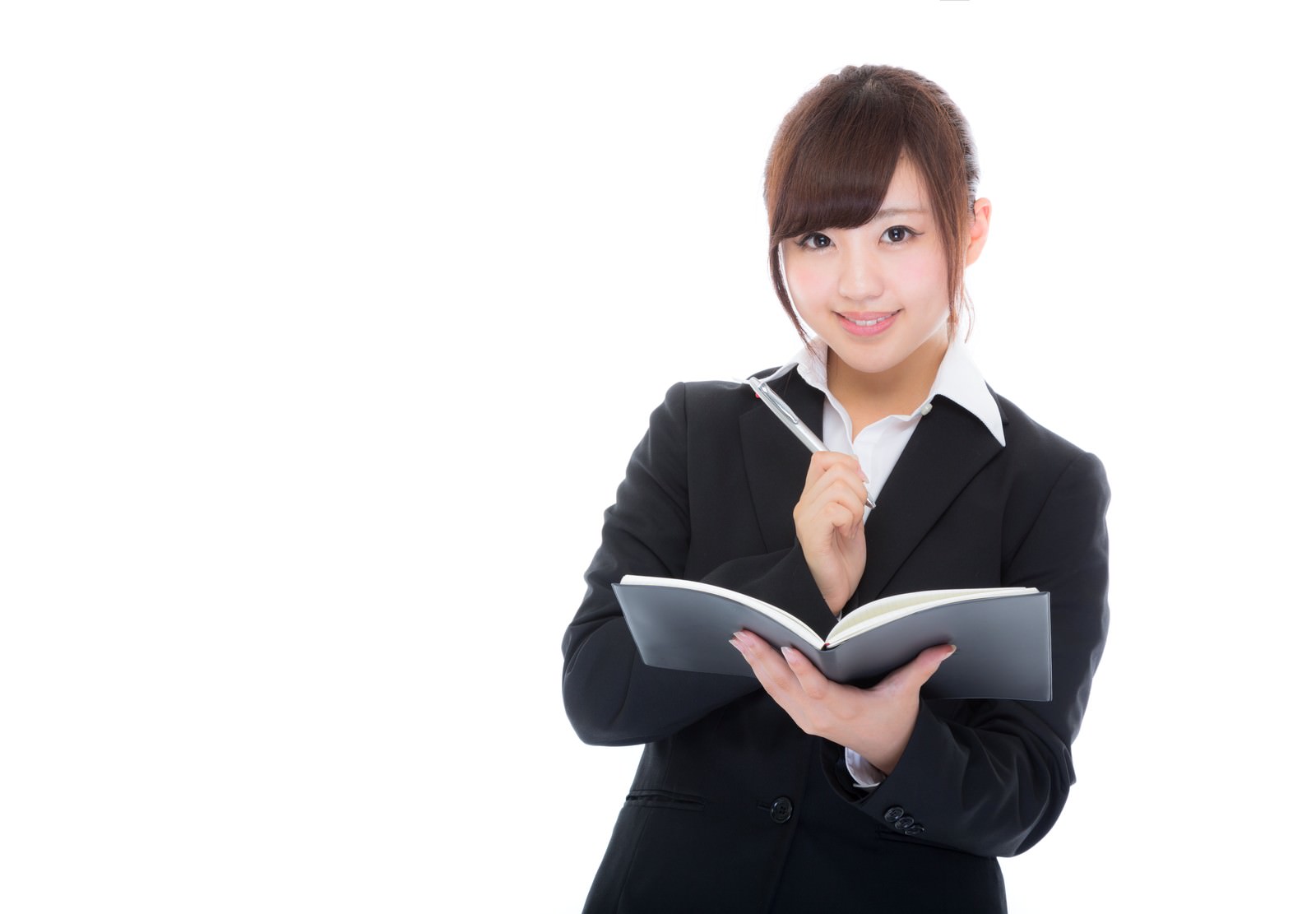
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



