【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。

2026年度末をもって、長年企業間の取引に用いられてきた手形・小切手の利用が廃止されることが決定しました。この変革は、デジタル化の進展と効率化を目指す金融業界の動きの一環として行われます。本記事では、全国銀行協会の情報を基に、手形・小切手の廃止の背景や影響、今後の課題について詳しく解説します。
目次
1. 背景と理由
2. 廃止のスケジュール
3. 影響
4. 電子決済の普及
5. メリット
6. デメリット・課題
7. 今後の展望
1. 背景と理由
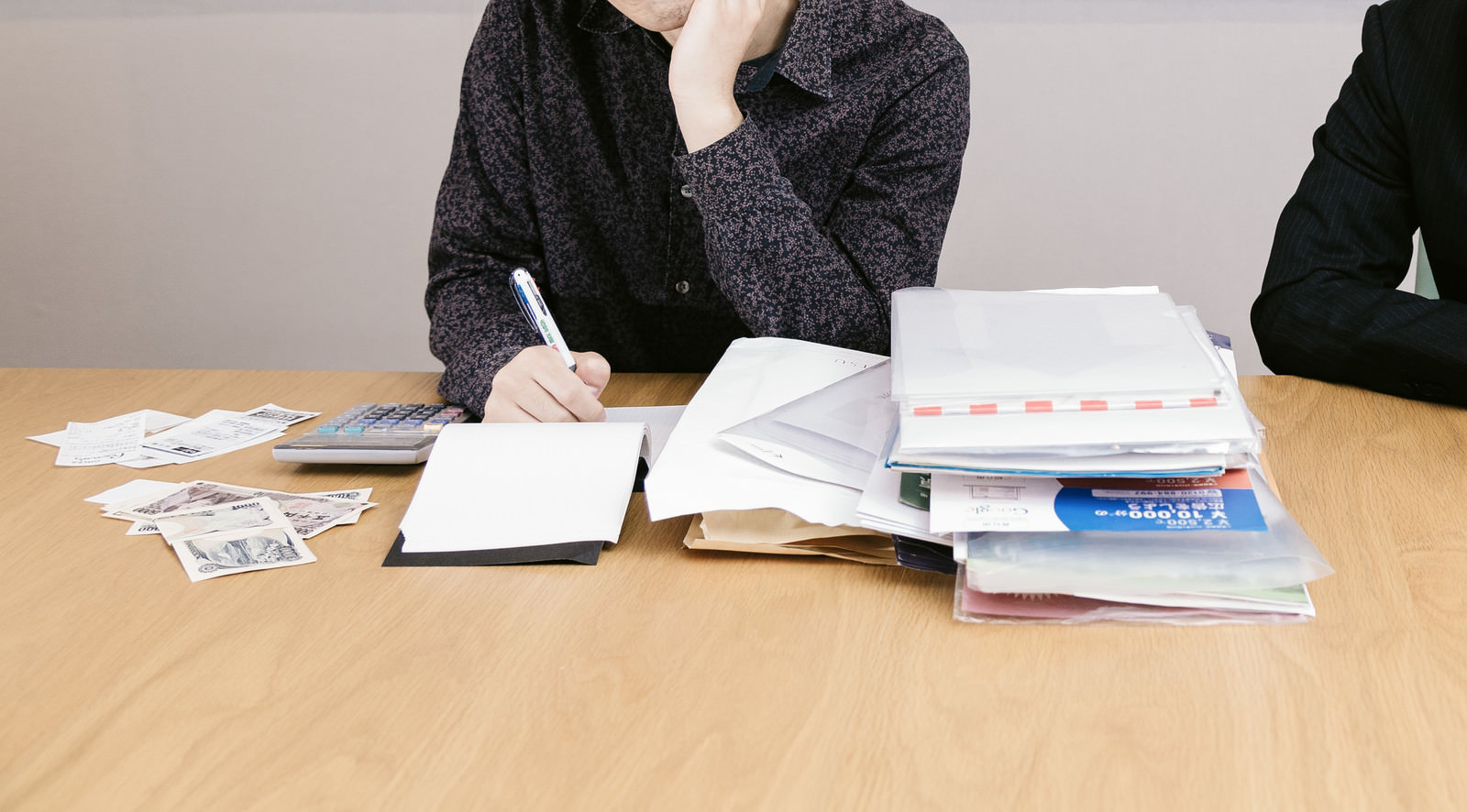
手形や小切手は長年、企業間の取引や支払い手段として広く利用されてきました。しかし、近年は次のような理由から、手形・小切手の利用が見直されています。
デジタル化の進展: 電子決済システムの普及により、インターネットバンキングやクレジットカードなどの即時決済が一般化しています。
手間とコストの増加: 手形や小切手は、発行や送付、交換所での取扱いなどに時間とコストがかかり、効率が悪いとされてきました。
トラブルの発生: 支払い期日が長く、トラブルや不正のリスクが高いことも廃止の背景にあります。
2. 廃止のスケジュール
全国銀行協会(全銀協)によれば、手形と小切手の利用は2026年度末を目途に完全廃止されます。これにより、手形や小切手を使用した取引は停止し、全ての取引が電子化された決済方法へと移行します。
2026年度末: 手形・小切手の完全廃止。
3. 影響
(1) 企業への影響
手形や小切手に依存していた企業は、以下のような影響を受ける可能性があります。
電子決済への移行: 企業間の決済手段として、振込やクレジットカード、オンライン決済システムを利用する必要があります。これに伴い、新たなシステムの導入や対応が求められます。
キャッシュフローの改善: 電子決済によって資金の移動が即時に行われるため、キャッシュフローの管理が容易になることが期待されます。
(2) 中小企業への課題
特に中小企業においては、手形や小切手の廃止に伴う対応が難航する可能性があります。従来の取引慣行に依存している企業では、次のような課題が考えられます。
システムの対応コスト: 電子決済システムへの移行にかかるコストや、従業員のトレーニングが必要となる場合があります。
取引先の影響: 取引先企業がまだ電子決済に対応していない場合、交渉や手続きに時間がかかることが考えられます。

4. 電子決済の普及
手形や小切手の廃止に伴い、電子決済の普及が一層進むことが予想されます。特に以下の決済手段が主流になると考えられます。
振込: 既に多くの企業が利用している振込は、即時決済が可能であるため、手形に代わる決済手段としてさらに重要な役割を果たします。
クレジットカード決済: 商品やサービスの購入時に迅速に決済が完了するため、利便性が高いです。
オンライン決済システム: PayPalやSquareなど、インターネットを介した決済手段がますます広がり、手形の代替手段として注目されています。
5. メリット
手形や小切手の廃止には、次のようなメリットがあります。
事務手続きの簡素化: 紙ベースの手形や小切手の処理が不要となり、書類管理や郵送コストが削減されます。
決済スピードの向上: 電子決済によって、取引が即時に処理されるため、資金の移動がスムーズになります。
不正のリスク低減: 紙の手形や小切手に伴う偽造や不正リスクが軽減されます。
6. デメリット・課題
一方で、手形や小切手の廃止にはデメリットや課題も存在します。
中小企業の対応負担: 手形取引に依存している企業にとって、システム対応や取引先との調整が大きな負担となる可能性があります。
電子決済への信頼性: 一部の企業や取引先が電子決済に不慣れであったり、信頼性を疑問視するケースもあり、新たなトラブルの発生も懸念されます。
7. 今後の展望
手形や小切手の廃止は、デジタル社会への移行を加速させる一方で、従来の取引慣行に依存していた企業にとっては大きな課題となります。特に中小企業は、電子決済への対応を早急に進める必要があります。また、政府や金融機関も、企業のスムーズな移行を支援するためのガイドラインやサポート体制を強化することが求められます。
全体として、2026年度末までに手形・小切手の廃止が実現すれば、日本の決済システムは大幅に効率化され、より安全かつ迅速な資金移動が可能となることが期待されています。
一方で、司法書士から見ると、不動産の担保設定で根抵当権が設定されている場合、登記簿謄本中の「債権の範囲」で「銀行取引 手形債権 小切手債権」となっているものも少なくありません。新規や変更で「銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権」としていますが、今までの設定はどうするのでしょうか?今後注目です。

「みなし解散」とは、会社法の規定に基づき、一定期間、事業を行っていない法人を法務局が解散したものとみなして登記を行う制度です。代表的なものは、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象となります。
「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。
法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。
一般社団法人の設立は、非営利法人として社会貢献活動や専門家団体の運営、業界組織の立ち上げなどを行いたい方にとって、有力な選択肢です。株式会社のような出資者がいなくても法人格を持てる点や、比較的簡易な設立手続きが魅力です。