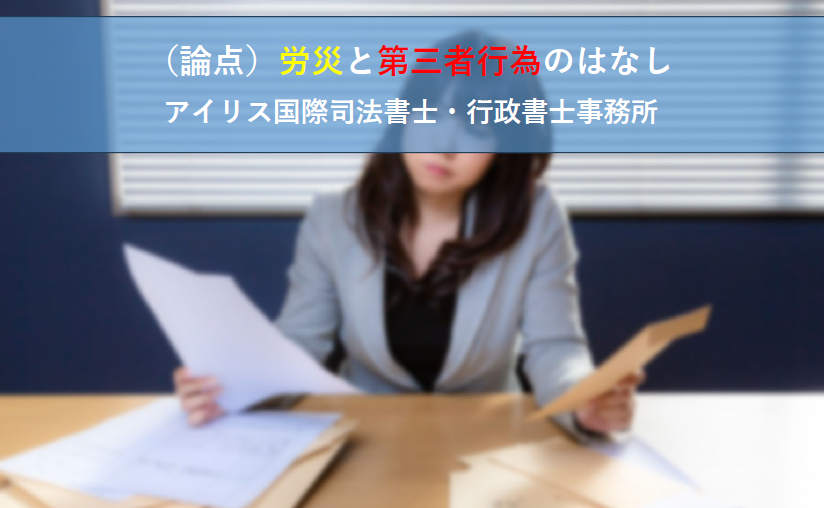(誰?)後見監督人について
後見監督人は、成年後見制度における重要な役割を担う人物であり、成年後見人の行為を監督し、適正な運用がなされるように支援する役割を果たします。この制度は、精神的な障害などにより判断能力が不十分な成人(被後見人)を保護するために設けられたもので、後見人は被後見人の財産管理や生活支援を行います。しかし、後見人が自己の利益を優先する場合などの不正を防止し、被後見人の利益を守るために、後見監督人の設置が必要とされることがあります。本稿では、後見監督人の役割、設置の要件、職務内容などについて詳述します。