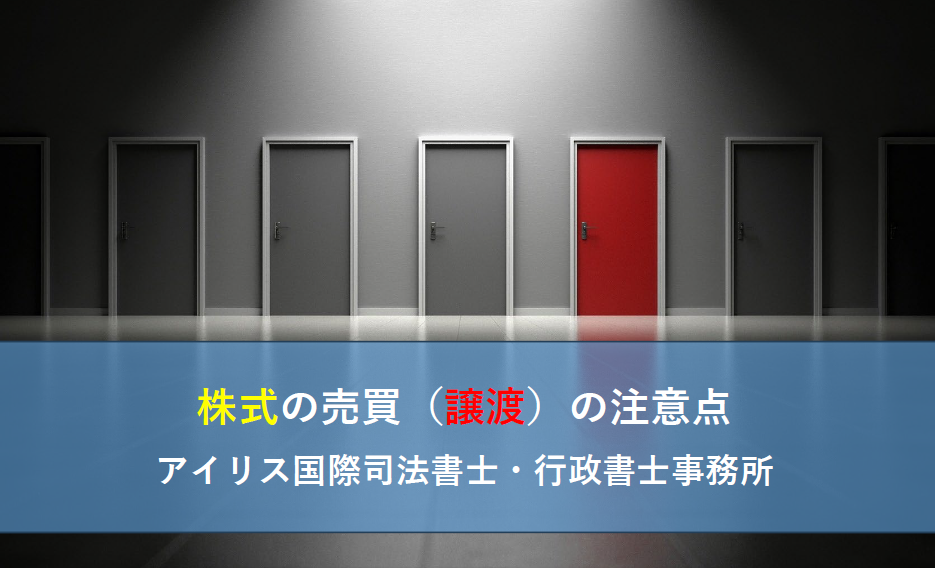公証人による定款認証について、日本公証人連合会において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をデジタルを用いてスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、利便性に配慮した「定款作成支援ツール」を法務省も関与して作成し、令和5年12月26日に公表されました。
また、令和6年1月10日から、東京都内及び福岡県内の公証役場において、この「定款作成支援ツール」を使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始することとされています。
2.対象となる法人について
法務省民事局総務課公証係からの事務連絡におきましては、「小規模でシンプルな形態の株式会社」とされています。
3.運用の開始時期
令和6年1月10日から、東京都内及び福岡県内の公証役場から始まる予定です。東京都内及び福島県内以外の地域につきましては、今後、運用が始まる予定です。
4.まとめ
以上、定款作成支援ツールについて解説をいたしました。公証人連合会のHPにおいて
「この定款作成支援ツールは、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいというニーズをお持ちの起業者の方の参考に供するために作成されたものです。
株式会社の定款は、事業を運営するに当たって従うべき根本的なルールとなり、それぞれの会社が自主的に定めるものです。定款に定めを置くべき事項は、例えば、商号、本店、会社の目的、会社の組織構成(取締役会、監査役等を設けるかどうか等)、発行可能株式総数及び株式の内容(株式の譲渡制限や議決権に関する事項等)、株券発行の有無、株主総会の手続、役員の責任に関する事項、事業年度及び剰余金の配当に関する事項など多岐にわたり、発起人は、どのような会社を設立したいかによって、どのような事項・内容の定めを置くかを考え、定款案を作成していきます。また、定款に定めを設けた場合には、その定款の内容に従って事業を運営することが求められ、定款に違反した場合には法的な責任が問われることもあります。なお、会社設立後に定款を変更することは可能ですが、その場合には株主総会の特別決議を必要とするなど所定の手続が必要になります。
このツールを利用して作成された定款案は、飽くまでも、小規模でシンプルな形態の会社のものとして想定される一つの例にとどまりますので、このツールを使って定款案を作成する前に、以下の「定款作成支援ツールを利用する場合の留意点・補足説明」をよくお読みいただくとともに、定款にどのような事項を定めれば良いかについてよく御検討いただくよう、お願いします。
定款の作成や具体的な内容についてご不明な点があれば、公証人や専門家に御相談ください。」(引用終わり)
とあります。つまり、すべて定款作成支援ツールを使用して完結できるのではなく、具体的な内容につきましては、公証人又は専門家にご相談いただくようになります。