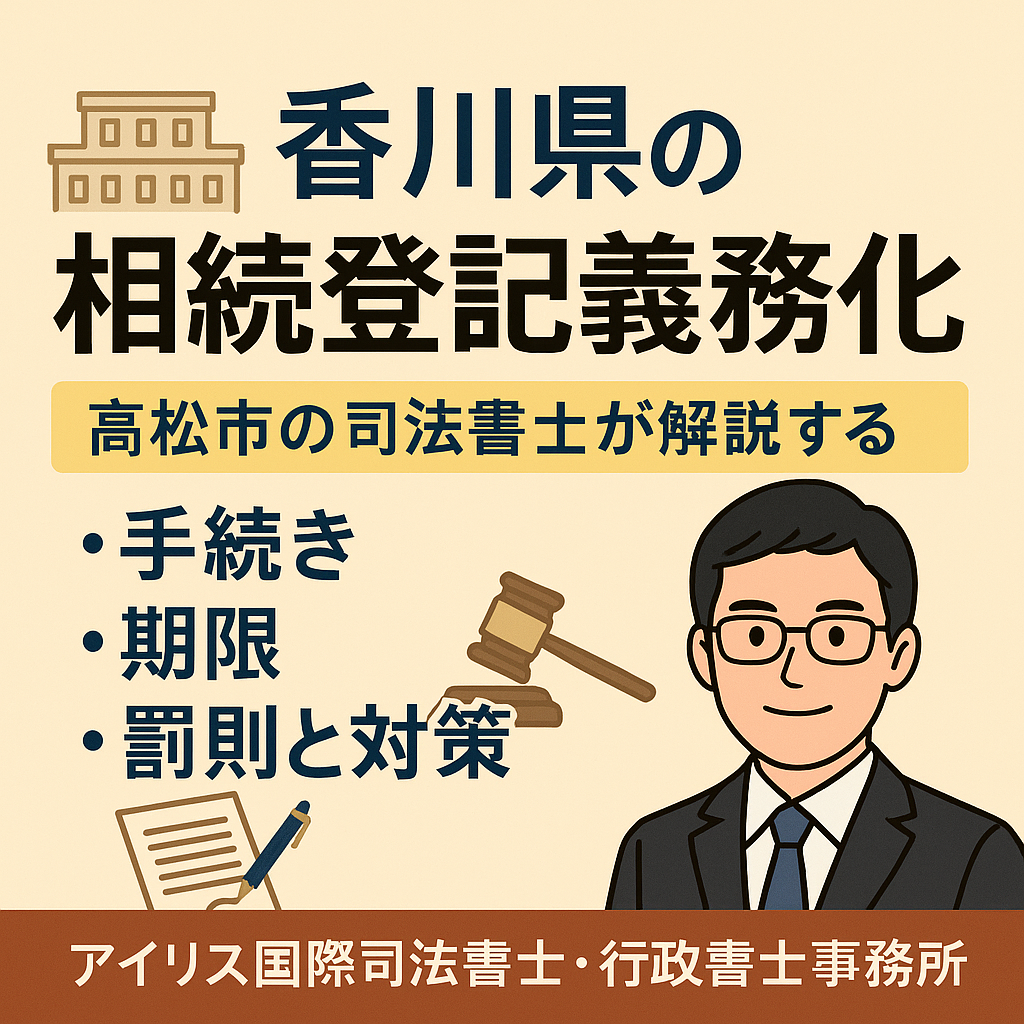第2回 坂出・宇多津 みんなのこども大食堂 ― 食べて・遊んで・つながる地域イベント ―
坂出町・宇多津町で地域ぐるみの子育て支援として開催される「第2回 みんなの子ども大食堂」。今回は、カレーやしっぽくうどんの無料ふるまい、体験ブース、学びブースなど、子どもたちが"安心して楽しめる時間"がたっぷり詰まったイベントになっています。家族での参加はもちろん、地域の居場所として誰もが気軽に立ち寄れる温かな催しです。