【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
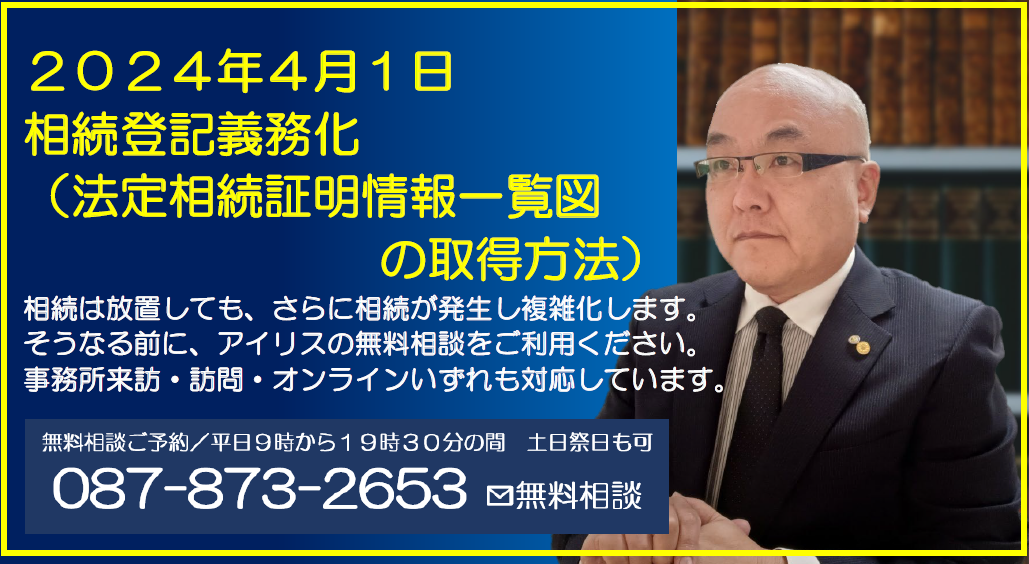
「法定相続情報証明制度」を活用し、預金の名義変更・解約、相続登記に添付する戸籍の代わりに提出することができます。すでに制度が始まり数年が経過していますが、改めて、取得方法についてまとめてみたいと思います。
目次
1.法定相続情報証明制度とは
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
3.申請書に添付する書類について
4.申請窓口
5.注意する点
1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、日本の相続手続きにおいて、相続人が相続財産についての情報を証明するための制度です。この制度は、相続人が法務局に提出する「法定相続情報証明書」に基づいています。
法定相続情報証明書は、相続人が相続財産の内容や詳細な情報を記載した文書であり、これによって相続手続きが円滑に進むことが期待されています。
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
①被相続人の表示(氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日)
➁申出人の表示(住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄)
③代理人の表示(住所(事務所)、氏名、連絡先、申出人との関係)
④利用目的(不動産登記、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金等手続、その他 から選択)
➄必要な写しの通数・交付方法
⑥被相続人名義の不動産の有無(有・無、有の場合には不動産の所在又は不動産番号)
※不動産は、申請書を提出する法務局の管轄内にある不動産であることが必要です。記載する不動産は、複数ある場合は、そのうちの一つの未記載で大丈夫です。
⑦申し出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを選択)
3.申請書に添付する書類について
(必ず用意する書類)
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
➁被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名。住所を確認することができる公的書類
(運転免許証の表裏面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し)
※これらのコピーには、「原本と相違ない旨」を記載し、申出人の記名をしなければなりません。
(必要となる場合がある書類)
➄法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意です)各相続人の住民票の写し
⑥委任による代理人が申し出の手続きをする場合
㋐委任状
㋑(親族が代理をする場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
㋒(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
⑦➁の住民票の除票を取得することができない場合の戸籍の附票
4.申請窓口
申請窓口は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかに該当する管轄法務局に提出をします。
申請後、法定相続情報一覧図の再発行を申請する場合、利用しやすい申出人の住所地の法務局に申請することをお勧めいたします。
5.注意する点
注意する点として2点あります。
まず一点目は、提出する相続情報一覧図(申請人もしくは代理人が作成するもの)で、相続人が縦に記載されている場合、一番下の相続人の下部に「以下余白」の文字を記載することが必要です。私が使っている作成ソフトでは、この「以下余白」の記載が出力されませんので、ワード出力後に編集をしています。
次に、相続人の情報に住所を記載するために「住民票の写し」を添付することになるのですが、申出人の氏名・住所を確認しることができる公的書類にも「住民票の写し」が含まれており、兼用することも可能なのですが、兼用した場合、申出人の住民票の写しが証明情報として法務局に取得されてしまい還付されません。この場合、申出人の住民票の写しのコピーを作成し、「原本と相違がない旨」を記載し、氏名、押印をして添付することで、原本の申出人の住民票の写しが還付されることになります。返却されなかった場合、せっかく取得した申出人の住民票の写しを再度市役所等で取得しなければならなくなりますので、注意が必要です。
アイリスでは、法定相続情報証明一覧図の申請代理を受け付けております。預金の名義変更、解約手続きなどにも利用できるため、戸籍の束を持ち込んで手続きをする必要がなくなります。作成を検討されている方で、なかなか時間が取れない等の事情のある方は、ぜひご利用ください。
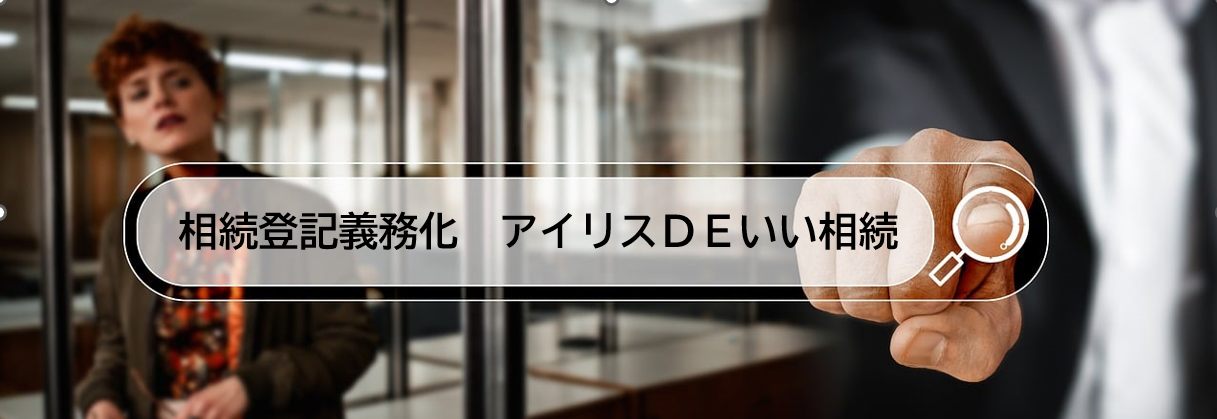

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
「相続登記の義務化って結局いつまでにやればいいの?」「過料って本当に取られるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続税の課税割合は全国平均9.4%。しかし地方では不動産割合が高く、現金が不足しがちです。香川県のような地域でこそ必要な、納税資金の準備と生前対策について司法書士が解説します。