【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
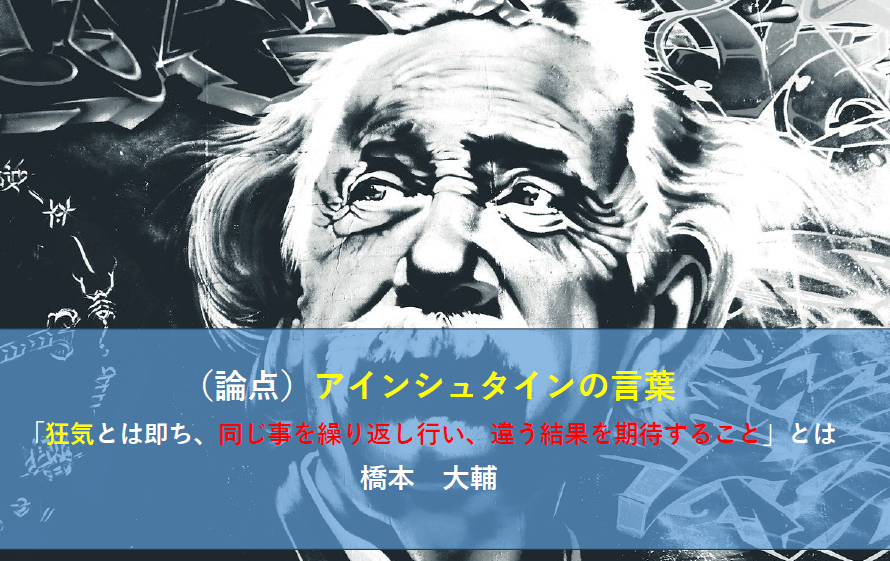
アインシュタインの言うところの「狂気(Insanity)」とは、「同じことを繰り返しながら、異なる結果を期待すること(Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results)」というものです。この言葉は、物理的な現象だけでなく、人間の行動や思考パターンにも適用される普遍的な真理を指摘しています。アインシュタインがこの表現を用いた意図には、いくつかの深い意味が含まれています。それでは、ご紹介いたします。
目次
1. 無駄な繰り返しの非合理性
2. 学習と適応の欠如
3. 科学的思考の強調
4. 柔軟な思考と創造性の必要性
5. パラダイムシフトの必要性
6. 自己反省の欠如
7. 変化の必要性
8. 結論
1. 無駄な繰り返しの非合理性

「同じことを繰り返しながら、異なる結果を期待する」という行為は、合理的な思考に反する行為です。もし何度試しても結果が変わらないのであれば、その行動は無意味であり、時間や資源の浪費に過ぎません。例えば、何度も同じ方法で失敗し続ける場合、その方法を変更せずに再度挑戦するのは非合理的です。アインシュタインは、そうした無駄な繰り返しを「狂気」と呼んでいるのです。
※自覚がなく陥っている方、結構多いと思います。
2. 学習と適応の欠如
この言葉は、学習や適応の欠如を指摘しています。成功するためには、過去の経験から学び、必要に応じて行動を変えることが重要です。何度も同じ失敗を繰り返しながら、その原因を分析せず、同じ方法で再挑戦することは、学習能力の欠如を示しています。アインシュタインの言葉は、学習し、適応することの重要性を強調しています。
3. 科学的思考の強調
科学においては、実験や観察を通じて得られた結果を基に仮説を検証します。何度も実験を繰り返し、同じ結果が得られる場合、その結果が正しいことを示します。しかし、同じ実験条件で異なる結果を期待することは、科学的に誤りです。アインシュタインは、この言葉を通じて、科学的な思考プロセスを強調しています。実験結果が予想と異なる場合、仮説や方法を修正することが必要です。
4. 柔軟な思考と創造性の必要性

アインシュタインは、柔軟な思考と創造性の重要性を説いています。同じ問題に対して同じアプローチを続けるのではなく、新しい視点や方法を試みることが求められます。これにより、予期しない結果や新しい発見が生まれる可能性があります。アインシュタイン自身も、従来の物理学の枠を超えて相対性理論を提唱するなど、創造的な思考の重要性を実践してきました。
5. パラダイムシフトの必要性
「狂気」という表現は、時にはパラダイムシフト(従来の枠組みを超えた新しい考え方)の必要性を示唆しています。従来の方法ではうまくいかない問題に直面したとき、新しい考え方や視点を採用することで、問題を解決する可能性が広がります。アインシュタイン自身も、ニュートン物理学の枠を超えた新しい理論を提唱し、物理学のパラダイムシフトを引き起こしました。
※自己の人生においてのパラダイムシフトを起こさせるためにも試行錯誤は必要です。
6. 自己反省の欠如

同じ行動を繰り返しながら異なる結果を期待することは、自己反省の欠如を示しています。自分の行動やその結果を客観的に評価し、必要に応じて行動を変えることが重要です。アインシュタインは、この言葉を通じて、自分の行動を省みることの重要性を説いていると考えられます。
7. 変化の必要性
最後に、この言葉は変化の必要性を強調しています。変化を恐れず、新しい方法を試すことで、問題解決の可能性を広げることができます。アインシュタインは、変化を受け入れ、新しい挑戦をすることの重要性をこの言葉で示しています。
8. 結論
アインシュタインの「狂気とはすなわち同じことを繰り返し、違う結果を期待することである」という言葉は、単なる諺や格言ではなく、深い意味を持つメッセージです。この言葉は、無駄な繰り返しの非合理性、学習と適応の欠如、科学的思考の重要性、柔軟な思考と創造性の必要性、パラダイムシフトの重要性、自己反省の欠如、そして変化の必要性を強調しています。アインシュタインはこの言葉を通じて、人々により合理的で創造的なアプローチを求め、自分の行動を見直し、新しい方法を模索することの重要性を訴えかけています。このメッセージは、現代においても変わらず、私たちの生活や仕事、科学において重要な指針となり続けています。
人生は有限です。今の自分より良い自分に変化を求めるなら、変化を求めるような行動をしてみるのもいいかもしれませんね。そうすれば、人生が好転するかもしれませんね。
また、変わらないと不満を言う前に、同じことを繰り返していませんか?一度自分自身を見直すのもいいかもしれませんね。

高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。