【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。

司法書士試験の学習で「焦り」は、誰しもが感じるところだと思います。しかし、現在進めている学習方法をこの時点から大きく変えるにはリスクが大きいです。そんな誘惑に負けないようにするために、少しアドバイスをしたいと思います。
目次
1.現時点で、どの程度学習できていれば合格圏内に行けるのか
2.学習方法を大きく変えるリスク
3.結局、薬局、郵便局
1.現時点で、どの程度学習できていれば合格圏内に行けるのか
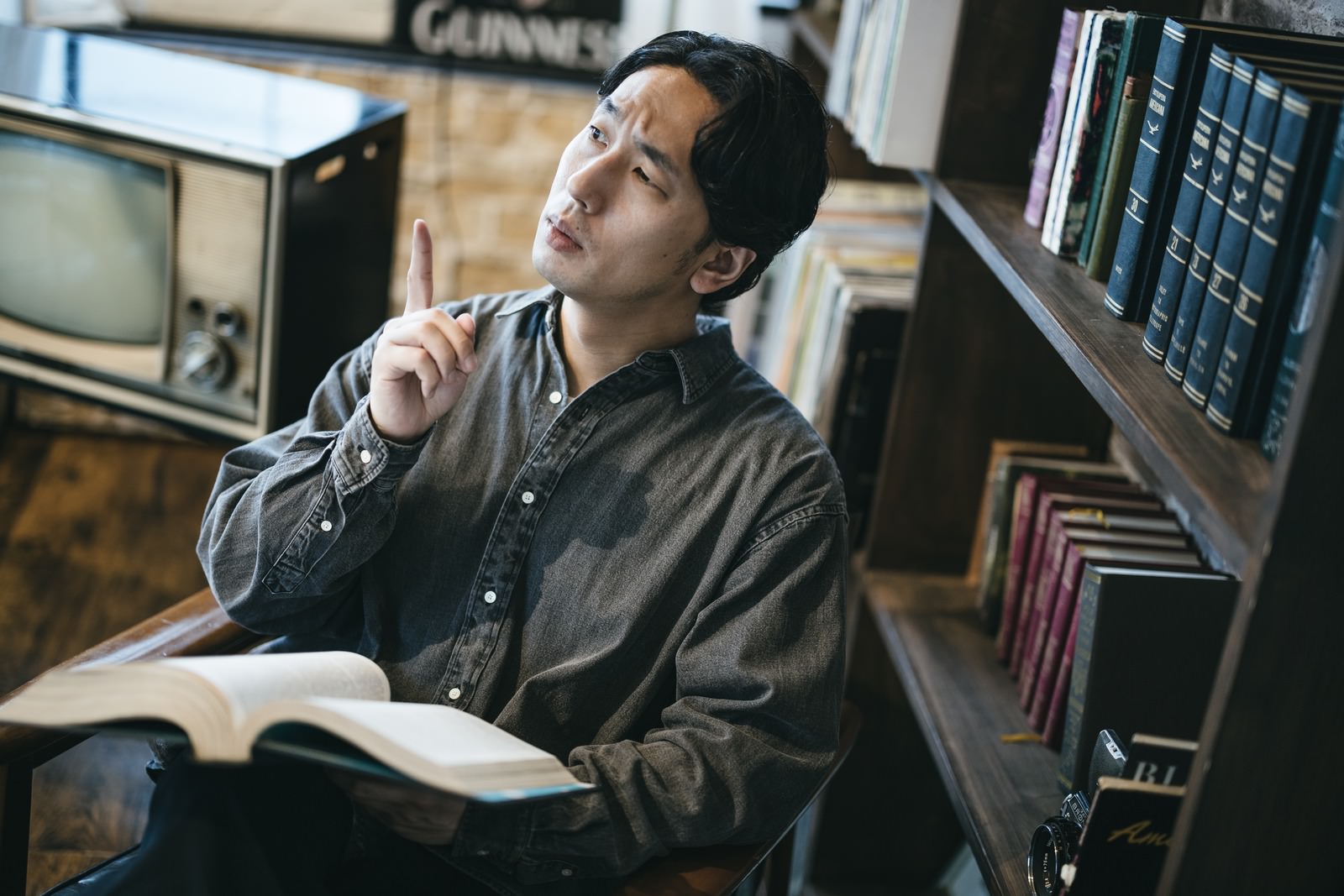
初学者と複数年受験生で、この辺りは大きく異なってきます。
(初学生の場合)
まず、主要4科目1周の方が多いのではないかと思います。理想は全範囲複数回終えているのが望ましのですが、この試験、範囲が膨大ですのでこの辺にとどまっていると思います。
しかし、予備校を受講されている方は、講義でマイナーまで終えている方もいると思います。定着をどのように進めていけばいいのかについては、過去問や予備校の模試で出てきた論点をひとつづつつぶしていけばいいと思います。不安な方は、肢別問題集で、毎日の学習に短時間見直す時間を作っていいかもしれません。大枠の今までの学習方法は変えずに包んでください。間違っても、民事執行法・民事保全法を学習しないという選択肢は取らないようにしてください。うまくいけば各1問で6点の差がつけられます。
マイナーに不安がある方は、午前午後含め、問題が解けるかどうかで見ていくのも一つの手段だと思います。論点の理解や、犯罪になるかならないか、特に午後は過去問題の焼き直しが多いですから、割り切ってしまうのも一つの手だと思います。
(複数年受験生の場合)
昨年と比べてどうでしょうか?進んでいるのか、後退しているのか。進んでいるのであれば、そのまま突き進んでください。後退しているように感じる方がいるかもしれませんが、おそらく、ペースの問題だと思います。記述を除き、択一の学習は、練度がものを言います。今の学習方法で、手間を惜しんでいないでしょうか。人間の脳は、永遠に一度触れた論点を覚えてはいられません。ペースが遅くなると、一度間違えて、次に触れるまでに忘れてしまうものです。これが積み重なると、ゴールが英会陰に見えてきます。だからと言って焦って学習方法を根底から変えてしまうのはダメです。とある予備校の先生が言っていましたが、問題集やテキストを使っている場合、「3ページ進んで翌日戻り、間違えた論点を振り返る」というアドバイスがありましたが、理にかなっていると思います。
2.学習方法を大きく変えるリスク

この時期に学習方法を大きく変えてしまうと、今まで習得した内容に触れるタイミングのペースが狂います。触れていない論点が長期放置されてしまう可能性があります。その知識が定着していない場合、再度学習しなおしということになります。4月からは、直前期に突入します。そこで、踏みとどまるようなことをしてはダメです。
「焦り」から、他の学習方法が、光輝いて見えるかもしれませんが、それはまやかしです。今の学習が苦しいのは、生みの苦しみ(定着の苦しみ)だと考えます。たとえ、今年がだめだったにしても、今やってる学習が正解か不正解かをはっきりさせておきたいじゃないですか?続けていきましょう。
今から学習方法を変えるということは、全く新しい場合ですと、3ケ月で合格、というとんでもない偉業を達成しなければ難しいでしょうね。6か月で合格した方は、何人か知っているのですが、さすがに3か月というのはお会いしたことがないです。それに、いたとしても、その方と同じ定着率を自分が実現できるかどうかなんて、だれにもわかりませんからね。
3.結局、薬局、郵便局
そもそも、学習の度合いや定着の度合いなどは、各個人差が大きく出ます。残りの時間を人それぞれに感じ方は異なると思います。「あと3か月しかない」と思う人もいるでしょうし、「まだ、3ケ月ある」と感じる方もいると思います。同じ時間なのに感じ方が異なるために、ここで「焦り」を過度に感じ取って、学習方法を変えてしまうのは愚の骨頂というものです。
あなたの手元に、まだまっさらなテキストと問題集がある状態では難しいですが、すでに今まで学習した痕跡やまとめたノート類があると思います。それらをブラッシュアップしていきましょう。

特に、予備校の講座を受講されている方は、講師が指示したこと以外のことは、極力せずに、まずは指示に従って学習を進めてください。結果が出るまでには、タイムラグがありますので、焦らずにじっくり行きましょう。
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。