【2026年3月28日開催】三幸まつり|高松市で子ども食事無料イベント(フードリボン活動)
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。

記述対策の論点について、択一対策も含め論点を提示します。今回も不動産登記法の記述問題についての論点について、確認していきたいと思います。今回も「(根)抵当権」関連になります。択一試験でも論点となる個所ですので、ひな形をしっかりと覚えてください。
目次
1.抵当権(債務者の更改)
2.根抵当権(債務者の変更)
1.抵当権(債務者の更改)

更改とは、当事者が従前の債務に代えて、
(1)従前の給付の内容について重要な変更をする(債権目的の更改)
(2)従前の債務者を第三者に交替する(債務者の更改)
(3)従前の債権者を第三者に交替する(債権者の更改)
いずれかの内容で新たな債務を発生させる契約を締結したときは、従前の債務は更改によって消滅します。(民法513条)
(2)の債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者の契約によってすることができます。そして、債権者が更改前の債務者に対して契約をした旨の通知したときのその効力が生じます。(民法514条1項)
(3)の債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後の債権者となる者及び債務者との契約によってすることになります。(民法515条1項)
さらに、この債権者の交替による更改は、確定日付ある証書によってしなければ、第三者に対抗することはできません。(民法515条2項)
※銀行から借り入れしたのに、債務者が知らない間にウシジマくんみたいな債権者に代わっていたというのでは困りますからね。
先にも言ったように、更改とは、従前の債務が消滅し新しい債務が生じることを言いますので、この内容を不動産の登記簿中に公示されている抵当権について、「更改前の債務の目的の限度において」当たらな債務を移転することができ、その登記をすることができます。
上記(1)から(3)までの抵当権について、更改の変更を登記する場合、登記の目的は同じで、「〇番抵当権変更」となりますが、その原因は、それぞれ異なります。
(1)(債権の目的の更改)
「年月日金銭消費貸借への債権目的の更改による新債務担保」
(2)(債務者の更改)
「年月日債務者更改による新債務担保」
(3)(債権者の更改)
「何月日債権者更改による新債務担保」
登記の目的が変更登記になるので、権利者は抵当権者であり、義務者は所有権の登記名義人となります。所有権の登記識別情報と印鑑証明書が必要となります。
2.根抵当権(債務者の変更)
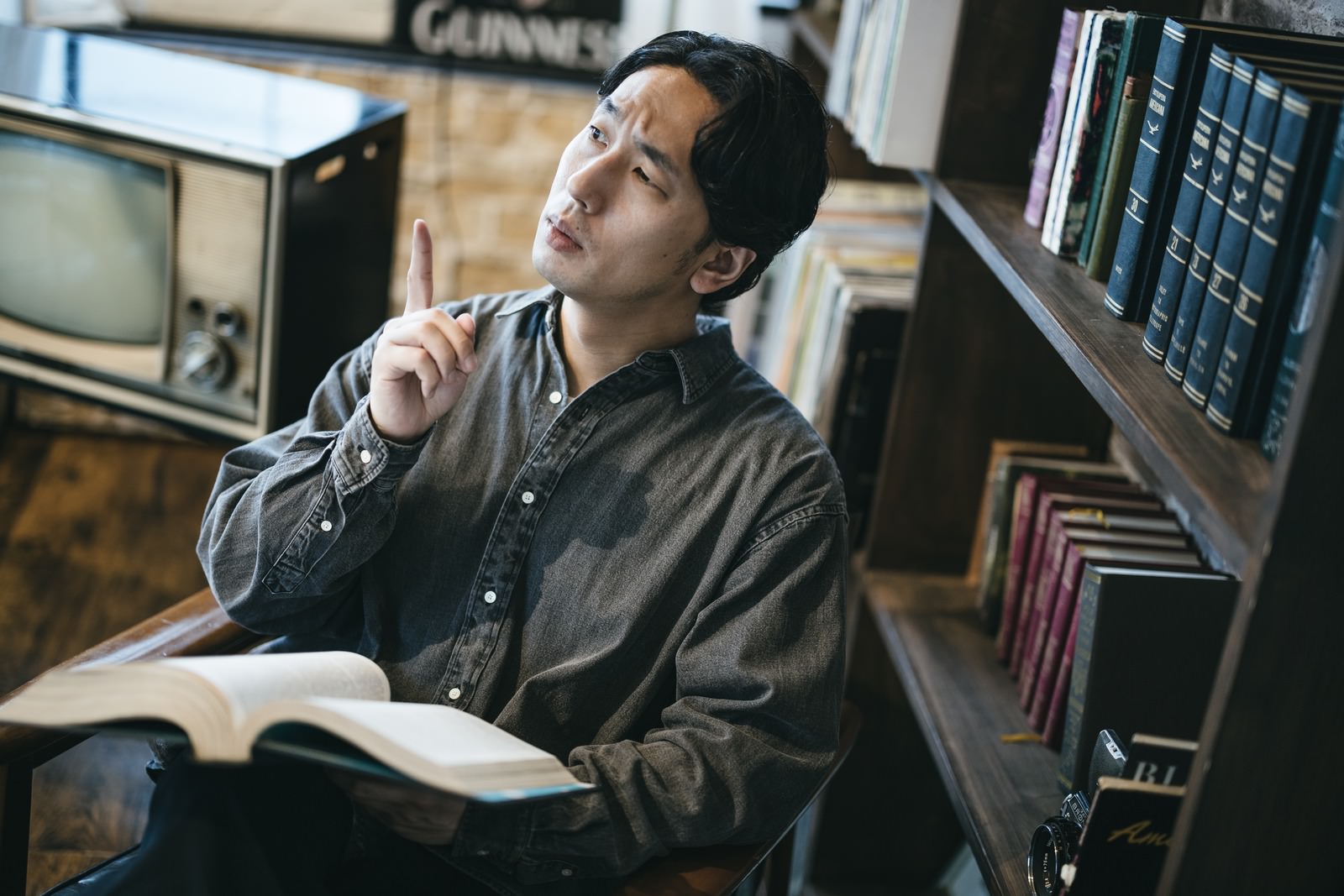
抵当権の場合ですと、債務者を変更する場合、「免責的債務引受」を原因として変更をします。または、上記のような更改により抵当権の変更登記を申請することになります。
しかし、根抵当権の場合は、少し勝手が異なります。「元本確定前」の根抵当権においては、根抵当権の債務者を変更することができます。(民法398条の4 1項)ただし、元本確定前にその登記をしなかった場合、変更をしなかったものとみなされます。(民法398条の4 3項)
また、根抵当権の債務者を変更する契約をする場合において、後順位の担保賢者の承諾を要しません。(民法398条の4 2項)
論点として「変更前の債務者の住所又は氏名に変更が生じている」場合に、前提として変更登記を要します。(登研452-112)省略する手続きは認められませんので注意が必要です。
(債務者の住所変更)
「登記の目的 〇番根抵当権変更
原因日付 年月日住所移転
変更後の事項 債務者 (新しい住所)(前の債務者)
権利者 根抵当権者
義務者 設定者(所有権の名義人)」
その後(債務者の変更)
「登記の目的 〇番根抵当権変更
原因日付 年月日変更
変更後の事項 債務者 (新しい債務者)
権利者 根抵当権者
義務者 設定者(所有権の名義人)」
根抵当権の変更の場合、設定者(所有権名義人)の変更には注意している方がほとんどだと思いますが、債務者の変更をする場合、債務者に変更が生じている場合にも、根抵当権の変更登記をする必要があります。
高松市で開催される地域イベント
**「三幸まつり」**のご案内です。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。