【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
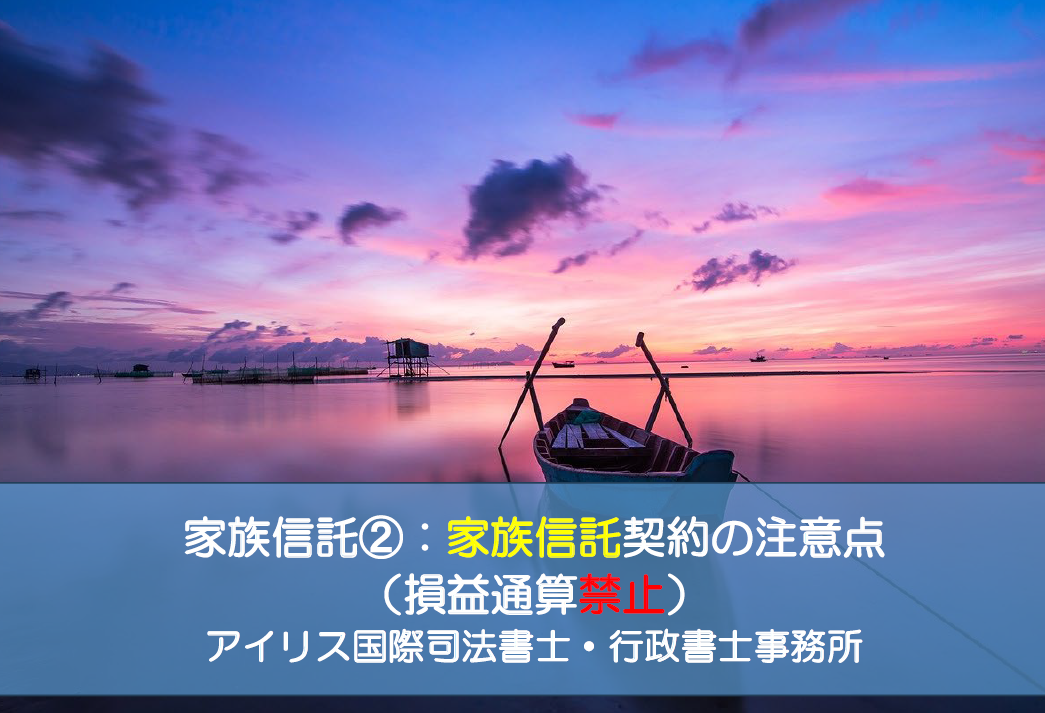
家族信託契約で注意しなければならない点は数多くあります。信頼できる人・管理してもらう財産・その運用などが挙げられますが、その中でも「損益通算禁止」について取り上げてみたいと思います。
目次
1.損益通算とは
2.信託財産になった場合の損益通算禁止
3.赤字の繰り越し控除ができない
4.複数の信託契約の損益通算はできない
5.回避方法はないのでしょうか?
6.家族会議で熟考を
1.損益通算とは
不動産所得などで赤字が出た場合に他の所得と相殺できる制度。相殺しきれなかった赤字は、翌年度に繰り越すこともできます。
2.信託財産になった場合の損益通算禁止
租税特別措置法第41条の4の2の規定により、「信託不動産で出た赤字は不動産所得の計算上なかったものとする」と規定されています。 つまり、自分の所得と家族信託による信託不動産から得た所得・損失は明確に分けられるようになっています。
信託財産となった不動産から出た赤字は、所得の計算上なかったものとされるので、委託者(親)の他の所得との損益通算ができなくなります。
例)①委託者名義財産 黒字
信託財産 黒字 問題なく合算できます。
➁委託者名義財産 赤字
信託財産 黒字 問題なく合算できます。
③委託者名義財産 黒字
信託財産 赤字 ※信託財産の赤字はなかったものとみなされるので損益通算できない。
3.赤字の繰り越し控除ができない
個人が青色申告している場合、ある年に発生した赤字を翌年以後発生した所得と相殺できる制度で「純損失の繰越控除」と呼ばれています。
信託不動産による不動産所得が赤字の場合にはなかったものとみなされるので、翌年以降への繰り越し控除ができない、といった問題が発生します。
4.複数の信託契約の損益通算はできない
「損益通算禁止」となる税務上の取扱いがもう一つあります。それは、不動産を信託財産とする信託契約が複数ある場合(受益者が同じことが前提)、年間収支の計算は信託契約ごとに完結しなければならず、契約をまたいだ損益通算はできないというものです。
実務では信託契約を目的別・承継者別で複数に分けることが少なくありません。信託契約を複数に分けることを検討する場合には、税務的な視点からの検討も必要になります。
5.回避方法はないのでしょうか?
それでは考えていきましょう。
①多額の経費が見込まれる大規模修繕計画を信託契約前に実施する。
信託契約前であれば、繰り越しの問題や損益通算の問題はありません。
➁全ての不動産を信託するか、一部の不動産のみを信託するのか検討する。
例えば、一部の大規模修繕予定の不動産については、あえて信託財産には入れず、赤字を無くしてから、まだ、親に判断能力があれば、信託契約することを検討する方法です。
③損益通算による節税を重視するなら、「任意後見」も検討する。
「任意後見制度」とは、あらかじめ自身の財産を管理してもらう者を任意後見人として契約を締結しておき、自身の判断能力が無くなったときに、その者に任意後見人として財産を管理してもらうという制度。租税特別措置法41条の4の2の規定は適用されません。
注意点として、任意後見制度では、効力発生のために裁判所に申し立てをして「任意後見監督人」を選任してもらい、定期的な報告義務と積極的な相続対策についても、後見監督人と相談しながら進めなければなりません。ですので、場合によっては、積極的な相続対策を勧められないケースもあります。「大きな資産」を対象にするのでなければ、任意後見制度でも対応できる場合があります。人後見監督人への報酬も発生するので、こちらも留意する必要があります。
6.家族会議で熟考を
このように、信託契約をする場合のデメリットも存在することを念頭に入れ、専門家の意見を交えながら検討していくことが必要になります。ですので、一部の家族間での契約はお勧めすることができません。「こんなはずではなかった」とならないためにも、必ず、相続人となりうる家族全員での検討をお願いいたします。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
現在、香川県外にお住まいで、宇多津町にあるご実家の不動産について相続のことでお悩みではありませんか?2024年4月からスタートした相続登記義務化により、放置していると過料のリスクも。宇多津町に精通した香川県内の司法書士が、名義変更や遺産分割、空き家・共有名義の問題を丁寧にサポート。まずは無料相談をご利用ください。予約制で土日祝も対応可能です。
香川県小豆郡小豆島町で相続登記や空き家問題、遺産分割でお困りの方へ。司法書士が地域の特性をふまえ、登記義務化・相続手続きを丁寧にサポート。無料相談は予約制で随時受付中。県外在住の相続人にも対応可能です。