【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
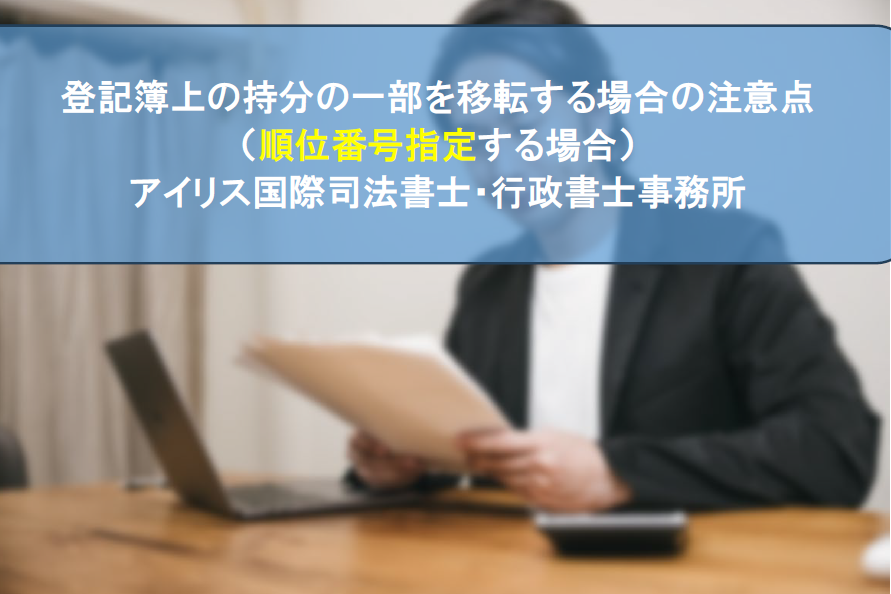
生前贈与の手法の一つである暦年贈与制度を使った「持分の一部移転」について、今回調査してわかった内容をまとめたいと思います。贈与者の持ち分が、一つの順位番号であった場合、その順位からしか一部移転ができないので、持分さえ特定しておけばいいのですが、順位番号が複数あり、特定の順位番号から一部移転してほしいとのリクエストがあった場合、登記の目的の記載をどのように書けばいいのか?この点について、お話をしたいと思います。
目次
1.1つの順位からの持ち分の一部移転
2.複数順位がある場合の持分一部移転
3.順位番号を指定しなかった場合の持分一部移転
4.まとめ
1.1つの順位からの持ち分の一部移転
そもそも、共有持分とは、不動産が1人の名義(単有)ではなく、2人以上の名義で登記されていることを「共有」といい、共有持分とは、それぞれが持っている所有権の割合のことを指します。複数人で、一つの不動産を所有していますので、それぞれの権利について名義を変更する場合、「共有者A持分全部移転」となります。
しかし、時には、その持分の全部ではなく、一部を移転したいという事情もあると思います。例えば、生前贈与の暦年贈与制度を利用する場合です。全部の持分を贈与したのでは、贈与税が基礎控除額を大きく超えてしまい、生前贈与のメリットが薄くなりますので、「持分の指定」のリクエストがある訳です。
その場合、登記簿謄本中、ある一つの順位番号で持分の記載がある場合の申請書の登記の目的は、「A持分一部移転」とし、受贈者(権利者)に渡る持分を記載することとなります。
2.複数順位がある場合の持分一部移転
(事例)以下、登記簿謄本の権利部の所有権について
権利部(甲区)
1番 所有権移転 持分2分の1 A,持分2分の1 B
2番 B持分全部移転 持分4分の1 A,持分4分の1 C
事例にて、Aが自信の持分のうち、4分の1をCに移転する場合、登記の目的は「A持分一部移転」でいいのでしょうか?
実は、この登記の目的では、1番の持分の一部を移転するのか、2番の持分を移転するのか判断が付きません。ですので、「A持分一部(順位1番で登記した持分一部)移転」と記載する必要があります。
実際に依頼のあった内容は、平成5年に登記した持分と平成25年に登記した持分を対象に、平成5年の持分を全部使ったうえで残りの持分から一部を移転してほしいとの内容でした。仮に平成5年の順位が1番、平成25年の順位が25番だっとすると、
「A持分一部(順位1番で登記した持分全部及び順位25番で登記した持分の一部)移転」
という記載になります。
※法務局に確認したところ、ある程度どの持分を移転するのかがわかれば、登記の目的はシステムに適合した形に修正して、入力していただけるみたいです。
気になるのが、システムに適合した登記の目的ですが、「A持分一部(順位1番で登記した持分全部)移転.A持分30分の6(順位25番で登記した持分の一部)移転」という表記が正しいようです。30分の6は実際に移転する持分になります。
なぜ、平成5年と平成25年に分けたのかと言いますと、平成17年から、添付資料として必要な権利証から登記識別情報に変わっています。権利証でも登記識別情報でも、いいのですが、暦年贈与のように何度も繰り返し利用する場合には、権利証の持分から処分していった方が、後の登記の際に、登記識別情報(パスワード入力)のみで申請ができますので、申請が楽になるといったことが挙げられます。勿論、次回も順位1番の平成5年の持分が残っていれば、次回も権利証が必要になりますが。
3.順位番号を指定しなかった場合の持分一部移転
おそらく、申請書提出時、若しくはオンライン申請後に「補正」の対象になるかもしれません。どの順位の持分を一部移転するのかの法務局側からヒアリングがあると思います。
4.まとめ
今回のように、複数順位に同一人物の持分がある場合の「登記の目的」の記載方法について、お話をしてきました。
どの順位の持分を処分したいのか「A持分一部移転」では、登記官の方たちには伝わりません。こちら側の意思を伝える方法として、「A持分一部(順位1番で登記した持分一部)移転」とすることが必要であると考えます。
※ただし、「公示」ということを考えますと、シンプルなほうがいいですので登記官の方と話をして、依頼者の方にも説明をして「A持分一部移転」と最終的には致しました。
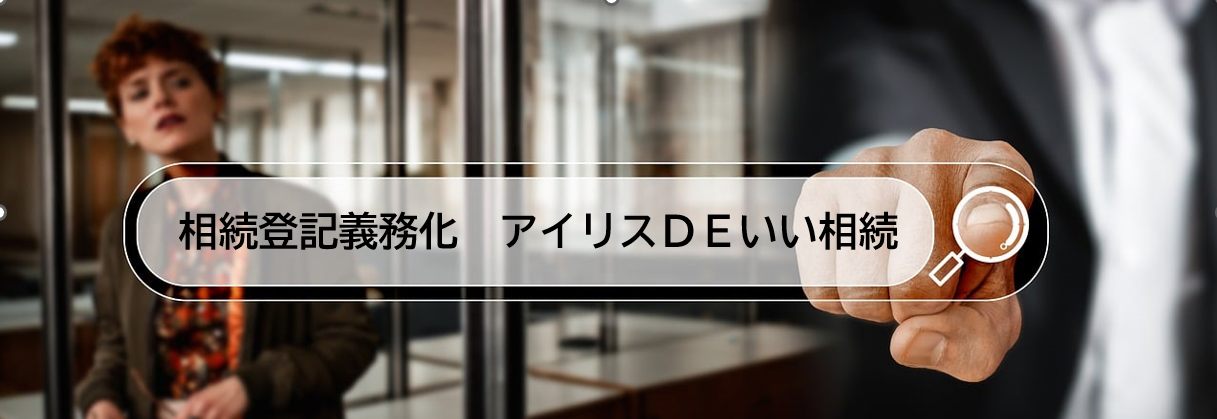

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
現在、香川県外にお住まいで、宇多津町にあるご実家の不動産について相続のことでお悩みではありませんか?2024年4月からスタートした相続登記義務化により、放置していると過料のリスクも。宇多津町に精通した香川県内の司法書士が、名義変更や遺産分割、空き家・共有名義の問題を丁寧にサポート。まずは無料相談をご利用ください。予約制で土日祝も対応可能です。
香川県小豆郡小豆島町で相続登記や空き家問題、遺産分割でお困りの方へ。司法書士が地域の特性をふまえ、登記義務化・相続手続きを丁寧にサポート。無料相談は予約制で随時受付中。県外在住の相続人にも対応可能です。