【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。

相続が発生した際、預貯金の取り扱いについては注意が必要です。特に、亡くなった方が生前に行った贈与が「みなし預金」とされる場合、相続税の課税対象となる可能性があります。みなし預金とは、亡くなった方が亡くなる前に贈与を行った場合であっても、特定の条件を満たすと、実質的には亡くなった後の遺産とみなされるものです。そのため、生前贈与を行う際には適切な計画と手続きが重要です。本稿では、みなし預金とされないための生前贈与のポイントを解説し、賢く財産を引き継ぐ方法について考察します。
目次
1.生前贈与とは?
2.みなし預金の定義とその仕組み
3.みなし預金とされるケース
4.みなし預金とされないための生前贈与のポイント
5.具体的な対策例
6.まとめ
1. 生前贈与とは?

生前贈与とは、個人が亡くなる前に自分の財産を家族や親族などに贈与することを指します。これにより、相続が発生した際に相続税の課税対象となる遺産の総額を減らすことが可能です。生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、贈与税がかかる場合もあるため、計画的に行う必要があります。
2. みなし預金の定義とその仕組み
みなし預金とは、被相続人が亡くなるまでの期間、被相続人から、相続人への贈与の際、預金通帳を被相続人が管理していた場合、それが実質的には親の財産として管理していたとみなされる制度です。国税庁は、被相続人の死亡前一定期間内に行われた贈与や預金の引き出しについて、相続税の逃れを防ぐために「みなし預金」として課税対象にしています。これにより、生前贈与があったとしても、贈与税や相続財産に含まれ、相続税が課されることがあります。
3. みなし預金とされるケース

みなし預金とされる代表的なケースには、以下のようなものがあります。
⑴毎月、子供名義の預金通帳に一定金額ずつ入金し親がその痛痒を管理している場合
⑵収入を得ていない専業主婦が、夫からもらった生活費の一部を内緒で自分名義の口座に入金する 場合
これらのケースでは、国税庁はその贈与を「贈与税や相続税の対象」として、当該預金をみなすことがあります。
4. みなし預金とされないための生前贈与のポイント
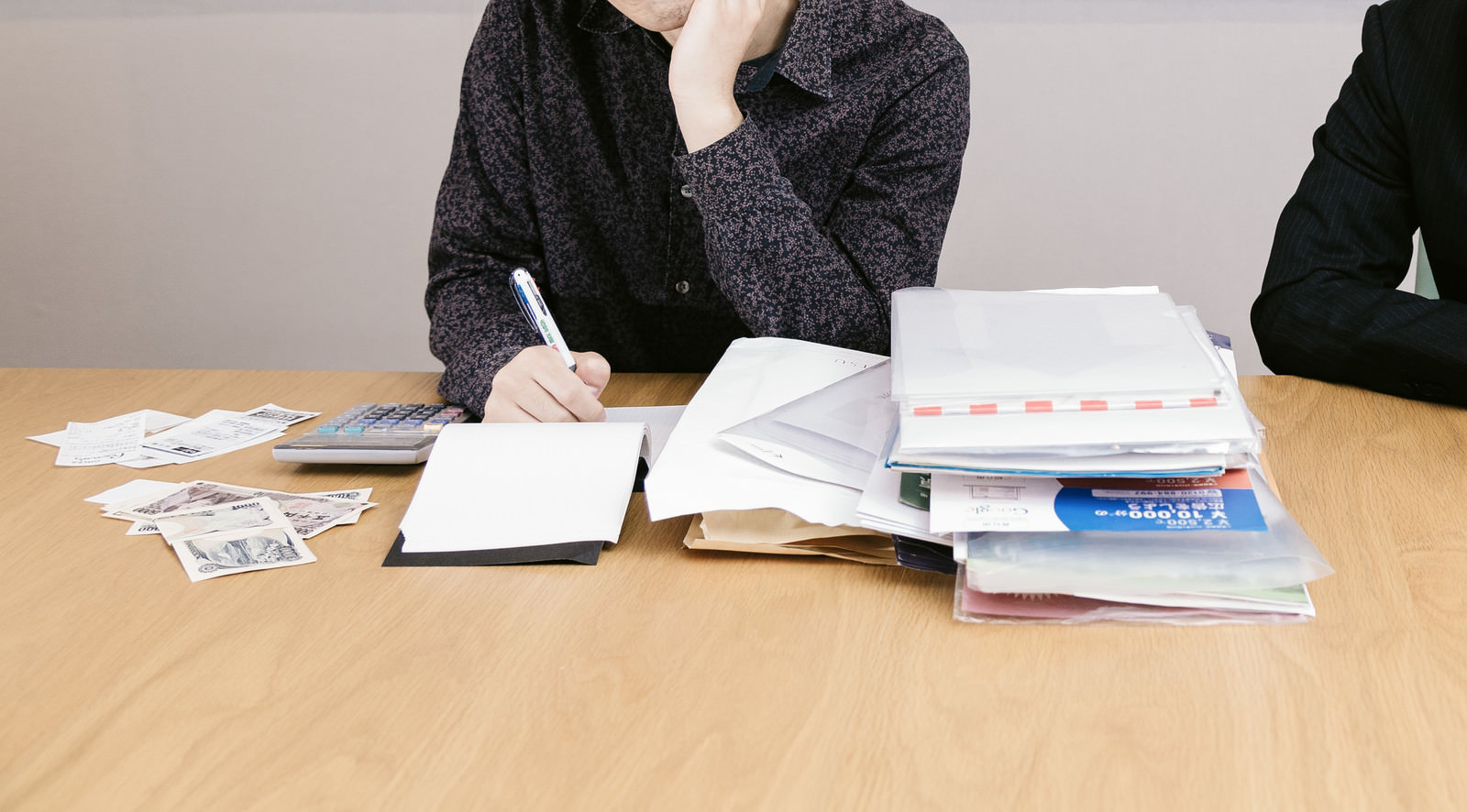
みなし預金とされないためには、いくつかの対策を講じることが重要です。
早めの計画的な贈与
生前贈与はできるだけ早期に計画的に行うことが大切です。死亡直前に行った贈与は、みなし預金とみなされる可能性が高くなります。定期的かつ小額ずつの贈与を行うことで、相続税の課税を避けやすくなります。
贈与契約書の作成
生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与が正式に行われたことを証明する書類を整備することが大切です。これにより、後に贈与が疑われる事態を避けられます。
贈与税の申告
贈与税がかかる場合は、適切に申告することが求められます。特に年間110万円を超える贈与には贈与税が課せられるため、贈与を行った際には税務署に対して申告を忘れずに行いましょう。
5. 具体的な対策例
以下は、みなし預金とされないための具体的な対策例です。
年間110万円の非課税枠を活用する
生前贈与には、年間110万円の非課税枠があります。この枠を毎年活用して、小額ずつの贈与を行うことで、相続税の課税対象を減らすことができます。
教育資金の一括贈与制度の利用
祖父母から孫への教育資金の一括贈与は、非課税となる特例があります。この制度を利用して、贈与を行うことが考えられます。
住宅取得資金の贈与特例
住宅購入資金を贈与する際には、特定の要件を満たす場合に非課税となる特例が適用されます。これにより、相続財産の一部を生前に移転することが可能です。
6. まとめ
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、みなし預金として相続税の課税対象になるリスクもあります。贈与を行う際には、早めに計画的に実施し、贈与契約書の作成や贈与税の適切な申告を怠らないことが重要です。また、非課税枠や特例を上手に活用することで、効果的な生前贈与を実現できます。みなし預金とされないよう、十分な準備をして、生前贈与を行うことが大切です。分からない場合には、必ず専門家に相談してください。

香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
共有名義の不動産は、時として想像を絶する相続トラブルを引き起こします。香川県高松市で実際にあった「名義人が知らない人」「相続人が70人以上」という事例をもとに、現実的な対応策と注意点を司法書士が解説します。
香川県・高松市で相続登記義務化に対応する司法書士事務所では、ネット集客の活用とそのリスクに直面しています。不当誘致や地面師との関与を防ぐため、信頼性の高い相続対策をどのように実現するか。実体験をもとに考察します。
相続放棄をした後、債権者から突然連絡が来て戸惑った経験はありませんか?「もう相続放棄したのに支払わないといけないの?」「何を説明すればいいのか分からない…」といった不安は多くの方が感じるものです。実際には、相続放棄によって法的な支払い義務は消滅しますが、債権者とのやり取りには一定の対応が必要です。本記事では、相続放棄後に債権者から連絡があった場合の対応フローを分かりやすく解説します。文例や注意点も紹介しますので、落ち着いて対処できるようになります。