【第3回】“養子縁組”で相続税の基礎控除を拡大する~法的に正しい活用法とは?~
「相続税が高くて困る…」「できるだけ税負担を軽くして財産を次世代に引き継ぎたい」――
こうした声に対し、"養子縁組"という法的手段を活用する方法があります。
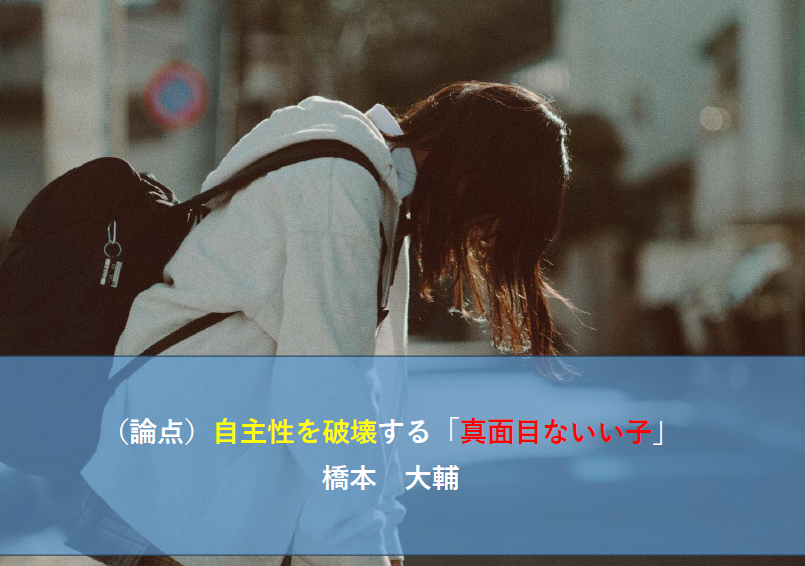
自主性を破壊する「真面目ないい子」について、深く考察してみましょう。日本社会では、子どもたちが「真面目ないい子」であることが求められることが多く、これは学校教育や家庭内でのしつけにおいて特に顕著です。しかし、こうした価値観が自主性の育成にどのような影響を与えるのか、問題点とその背景、さらに自主性を育むための提言について詳述します。
目次
1. 「真面目ないい子」とは何か
2. 「真面目ないい子」が自主性を破壊するメカニズム
3. 自主性を育むために必要な要素
4. 「真面目ないい子」への評価と社会的期待の影響
5. 自主性を育むための家庭と学校の役割
6. まとめと提言
1. 「真面目ないい子」とは何か

「真面目ないい子」とは、社会や親、教師の期待に沿って行動し、ルールを守り、反抗することなく従順である子どもを指します。日本の教育システムや文化において、このような子どもは「良い子」として評価され、称賛されることが多いです。これは、秩序や協調性を重んじる日本の文化背景から来ています。
(特徴)
ルールを守る: 規則や決まりごとに忠実で、ルールを破ることを極端に恐れます。
従順である: 親や教師などの権威に対して反抗せず、指示に従うことが求められます。
問題を起こさない: 集団の中で目立たず、問題行動を起こさないことが「良い子」の条件とされます。
2. 「真面目ないい子」が自主性を破壊するメカニズム
自主性の欠如: 自主性とは、自ら考え、判断し、行動する力です。しかし、「真面目ないい子」は、外部からの指示や期待に応じて行動することが重視され、自らの意思や判断を表現する機会が限られています。
依存的な行動: こうした子どもたちは、親や教師の期待に応えることが最重要であり、自分自身の意思や考えを表現する機会が少なくなります。その結果、自己決定力が育たず、他人に依存する傾向が強くなります。
創造力と批判的思考の欠如: 自主性を持つためには、創造的な思考や批判的な視点が必要ですが、指示やルールに従うことばかりが求められると、こうした能力が育まれにくくなります。これにより、新しいアイデアを生み出す力や物事を深く考える力が乏しくなります。

3. 自主性を育むために必要な要素
自己決定の機会: 自主性を育むためには、子どもたちに自己決定の機会を与えることが重要です。例えば、日常の小さな選択(食事のメニュー、遊びの内容など)を子ども自身に任せることで、自己決定力を育てることができます。
失敗を許容する環境: 子どもが自ら考え行動する中で、失敗を経験することは重要です。失敗から学び、次の行動に生かすことで、自己判断力や問題解決能力が養われます。過度に失敗を恐れず、失敗を成長の一環として捉える環境が必要です。
自由な発想を奨励する: 自主性を育むには、自由な発想や創造的な活動が不可欠です。これには、子どもが自由に考え、自分の興味を追求できる時間や空間を提供することが含まれます。例えば、自由に絵を描いたり、物語を作ったりする活動を奨励することが効果的です。
コミュニケーション能力の向上: 自主性は、自分の考えを他者に伝え、意見を交換する力とも深く関連しています。家庭や学校でのディスカッションや対話を通じて、子どもが自分の意見を表現し、他者と協力して物事を進める力を育てることが重要です。
4. 「真面目ないい子」への評価と社会的期待の影響
社会的期待のプレッシャー: 日本社会では、長年にわたって「真面目ないい子」が良しとされる風潮が強く、これが子どもたちに大きなプレッシャーを与えています。親や教師からの評価を気にするあまり、自分の考えを持つことや新しい挑戦を避け、無難な選択をするようになります。
評価基準の再考: 子どもたちを評価する際には、従順さや規則遵守だけでなく、創造力や独立した思考、問題解決力など、多様な観点から評価する必要があります。これにより、子どもたちが自主性を持ち、自分の考えや意見を尊重される環境を作ることができます。

5. 自主性を育むための家庭と学校の役割
家庭での役割: 家庭は、子どもが最も長い時間を過ごす場であり、そこでの教育やしつけが子どもの自主性に大きな影響を与えます。幼少期は仕方ないとしても、ある程度子供が成長した時、親は、子どもの意見や考えを尊重し、決定権を持たせることで、自主性を育む環境を作ることができます。
学校での役割: 学校では、従来の一方的な指導から、子どもたちが主体的に学び、考え、発言する機会を増やすことが求められます。プロジェクトベースの学習やグループディスカッションを通じて、子どもたちが主体的に取り組む力を育てることが重要です。
6. まとめと提言
「真面目ないい子」は、社会や親の期待に応えるために自主性を抑え、外部の指示に従うことが多くなります。しかし、これでは自主性が育ちにくく、自己決定力や創造力が欠如する可能性があります。自主性に乏しい人は、主体性がなく、一度社会で挫折した場合、取り返しがつかないことになります。これを防ぐためには、子どもたちが自分で考え、判断し、行動できる機会を増やし、失敗を許容する環境を整えることが重要です。また、家庭や学校での評価基準を多様化し、子どもたちが自由に発想し、自主的に行動できる環境を整えることが、これからの社会で必要とされる力を育むために不可欠です。
そして、なぜ私がこの話を取り上げたのかといいますと、私も「真面目ないい子」だった時期があるからです。幸運にも周りの仲間に恵まれて気が付きましたが、私は「真面目ないい子」の習慣を断ち切る目的もあり、それまでの生活を一変させるために留学という選択をしました。自覚はできていたので、相当無茶なことをしながら、自主的に何かをすることを続けました。相当苦労して今に至ります。その呪縛が取れてからは、人生はうまく回り始めたと思います。

「相続税が高くて困る…」「できるだけ税負担を軽くして財産を次世代に引き継ぎたい」――
こうした声に対し、"養子縁組"という法的手段を活用する方法があります。
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
生前贈与は相続税対策になる一方、制度を誤解すると損をする可能性も。暦年贈与や相続時精算課税制度の違い、贈与税の注意点、2024年の制度改正を司法書士が解説します。