相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

先日、遺産分割協議書を作成し署名と実印による押印を実施したのですが、印鑑証明書と照合すると、明らかに印影がかけた状態のものがありました。他の書類も確認したのですが、すべて印影の丸枠のほとんどが出ていない状態でしたので、実印の現物を確認すると、完全に欠けている状態でした。このような場合、どのような対応をすればいいのか、実体験をもとにお話をいたします。
目次
1.登録する印鑑の印影の制限(香川県高松市役所)
2.印鑑がかけている場合の対応
3.まとめ
1.登録する印鑑の印影の制限(香川県高松市役所)

これは、私が香川県の高松市役所HPの内容と、今回の事案の問い合わせについての話をしたいと思います。
香川県高松市役所での取り扱い
まずは印鑑を登録できるのは、高松市に住民登録がある15歳以上の方
※意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
※成年被後見人の方は、本人が窓口にお越しになり、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請することができます。
そして、登録できる印鑑は一人1つです。
住民票に旧姓(旧氏)併記を申請し、記載された方は、旧姓(旧氏)でも印鑑登録ができます。
一方で、登録できない印鑑については、
①住民登録している氏名と異なるもの
➁職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
③自己流のくずし文字、極端な図案化などで、本人の氏名を表してないもの
④印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる小さなもの
➄印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない大きなもの
⑥ゴム印など変形しやすいもの
⑦輪郭がないもの又は30%以上欠損しているもの
⑧竜紋や唐草模様等を外郭としたもの
⑨押印すると文字が白くなるもの(逆さ彫り印)
⑩同一世帯内の方が既に登録しているもの
※⑦輪郭が仮に20%あれば登録できるのかと言いますと、高松市役所では、登録を控えていただくように話をしているようです。(問い合わせで確認)
2.印鑑がかけている場合の対応
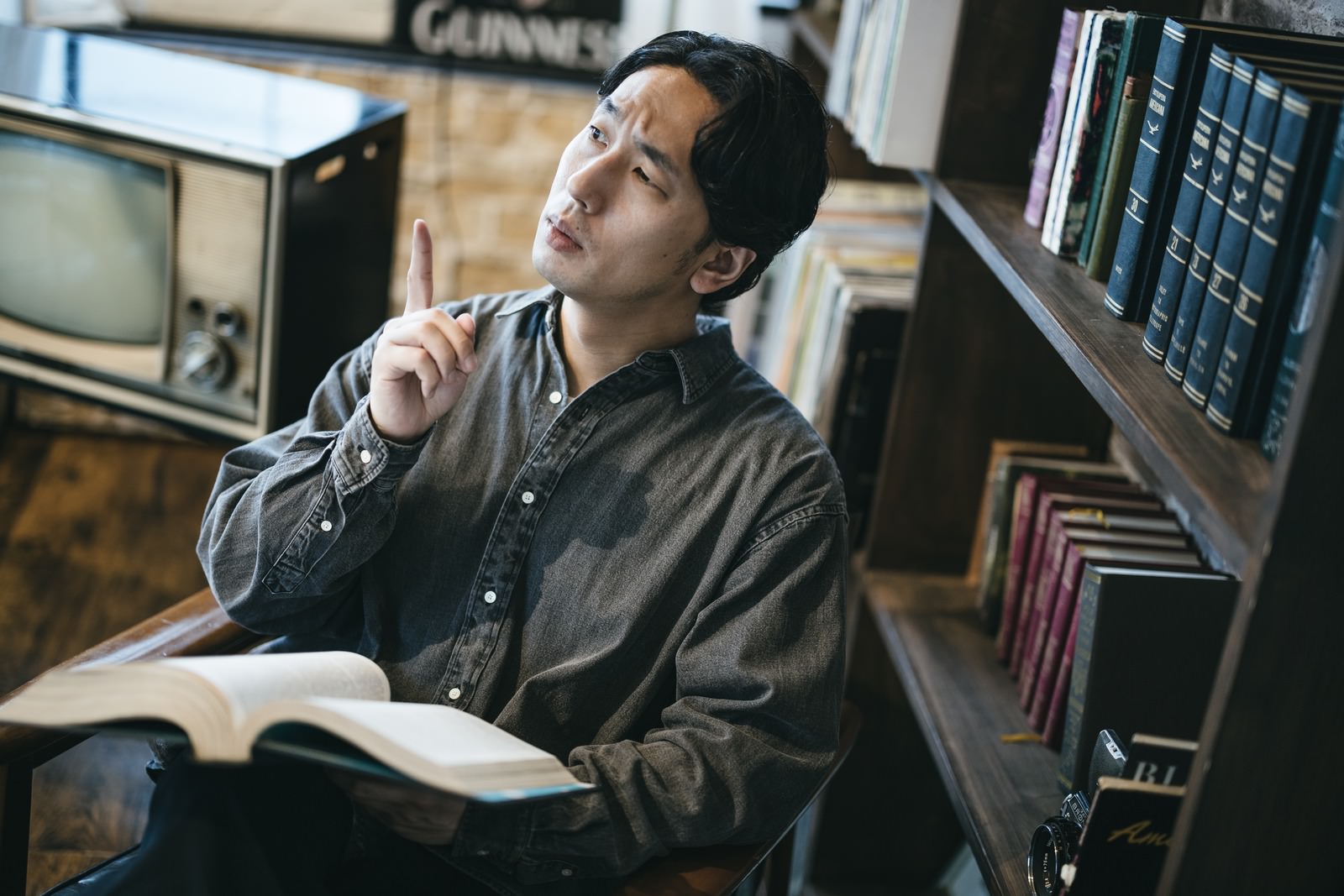
高松市への問い合わせで、輪郭部分がかなりかけた印鑑でしたので、かけた状態での登録はできないと言われました。そこで、印鑑屋に同行し、新たに印鑑を購入いただき、その足で市役所窓口に行き、買った印鑑を登録し印鑑証明書を取得しました。
本人が行った場合、数十分で印鑑証明書まで発行されますが、本人以外の代理人の場合、
「登録者ご本人宛に郵送による照会をしますので、登録までに1週間程度かかります。
窓口には、申請時と回答書持参時の2回、お越しいただくことになります。」とのことで、すぐに印鑑証明書を取得することはできません。注意が必要です。
3.まとめ
相続で必要となる添付書類である遺産分割協議書には、実印で押印の上、印鑑証明書を添付します。もちろん、印影と実印が異なる場合には、相続登記はできません。
ご高齢になられ、「もう必要ないだろう」と、実印がかけたままにされている方もいらっしゃるようですが、相続は、いつ発生するかわかりません。かけた実印を所有されている方は、お元気なうちに印鑑登録のやり直しをすることをお勧めいたします。高松市では、ご本人以外の方が印鑑の登録をやり直す場合、1回の来訪ではできなくなっております。

令和6年8月21日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ランサムウェアは、コンピュータシステムを人質に取り、復旧のための身代金を要求するサイバー攻撃です。最近では、その手口が高度化・多様化し、企業や個人に対する脅威が増しています。以下に、最近のランサムウェアの事例と、それに対する対策方法をまとめます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き残す形式の遺言書で、作成や変更が比較的容易であるため、多くの人に利用されています。しかし、その一方で法的効力を持たせるためには一定の要件を満たす必要があります。以下に、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるべきポイントを詳しく説明します。
不動産は、生前対策として非常に有効な手段です。相続税の負担を軽減し、遺産分割をスムーズに行うために不動産を活用することは、多くのメリットがあります。以下に、不動産を利用した生前対策のメリットを詳しく説明します。