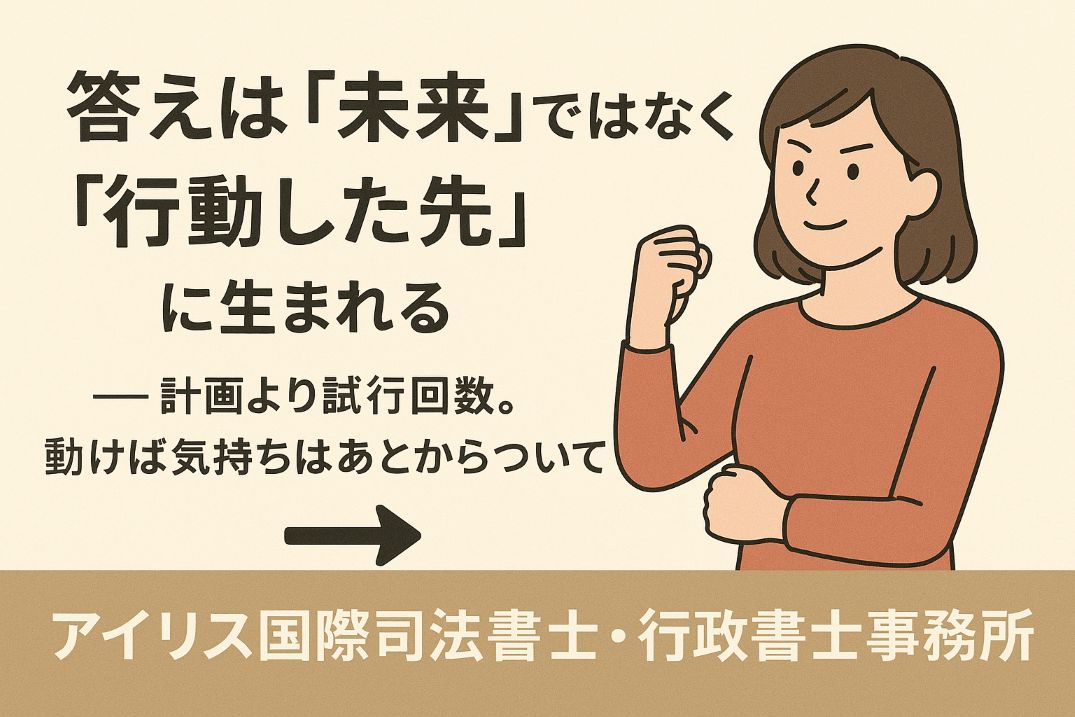相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
70歳以上の方、急いだほうがいいかもしれません(遺言)
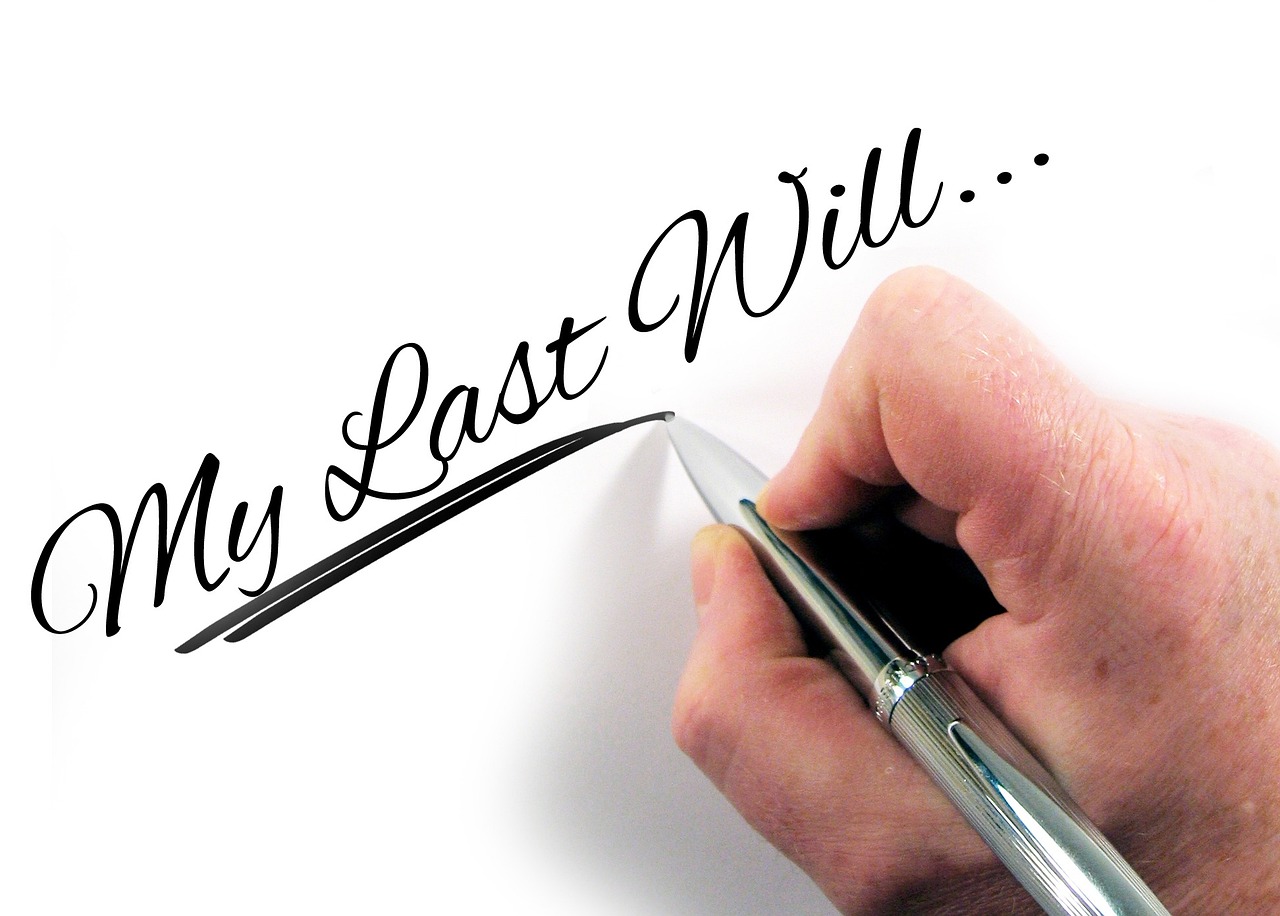
先日、ご相談で電話をかけてこられた方からヒアリングをしていると、遺言書の作成がしたいということがわかり、手続きなどの内容を話すと、「そんなに手続きが面倒なんだったら、もういいや。」と電話を切られてしまいました。年齢は80歳半ばでした。遺言書を作成するにも、ある程度「元気」でないと、どうしても「面倒」と感じてしまわれるようです。早めの遺言書作成をして、あなたの「想い」を形にしておきましょう。
目次
1.遺言書がなぜ必要
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
3.まとめ
1.遺言書がなぜ必要
2024年(令和6年)の相続登記義務化により、今後、相続登記に関する問題が浮上する可能性が非常に高くなっています。現に、私が市役所の無料相談会に参加した際に、相談件数は通常の倍、しかもその9割以上が相続に関連するものでした。
それでは、遺言書を作成するメリットについて解説いたします。
相続登記をする際に、遺言書がない場合、「遺産分割協議」を相続人全員で行い、その内容をまとめた遺産分割協議書に相続人全員が記名・実印で押印し全員分の印鑑証明書の添付が要求されます。生前、離婚した妻の子供や疎遠になった親族が相続人になることがあります。遺産分割協議自体が困難になるケースも多くの相談者の方で見てきました。
この遺産分割協議は、遺言書があればその遺言書の内容に応じて相続登記が可能なんです。残されたご家族の負担が大きく軽減されるといっても過言ではありません。
2.なぜ70歳になったら遺言書なのか
遺言書の作成するのは、もちろん親になります。日本人の平均寿命からすると、男性81.47歳、女性87.57歳(2021年厚生労働省)です。まだまだ大丈夫なんじゃないのと思われるかもしれません。
しかし、ご高齢者になると、司法書士や公証役場に出向くことは、それなりに負担が大きいのです。元気なうちに遺言書の作成をする必要性があるのです。
支障なく日常生活ができるとされる健康寿命は、男性72.68歳、女性75.38歳(2019年厚生労働省)です。意外と短いということがわかります。
※健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(厚生労働省)
さらに年齢が進むと認知症発症のリスクが増加します。グラフを見ますと70歳代後半から認知症発症の割合が、それまでと比べて増加していることがわかります。

3.まとめ
このように、遺言をするにも健康状態や認知症のリスクといったことを考慮する必要性が出てきます。相談者の中にも90歳で遺言を書きたいと言って来訪される方もいますが、公正証書遺言をするにも労力と公証人の質問に的確に答えられなければ、難しいと思います。自筆証書遺言ですと、相続発生後、相続人間でもめた場合、その遺言書が判断能力を理由に無効にされるかもしれません。
全ての方が、必要かと言われると、そうでない方もいらっしゃいます。しかし、再婚されている方やご兄弟で不仲など、相続人間で争いが起きそうな方は、早めの遺言書対策が、残されたご家族の負担を軽減いたします。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。
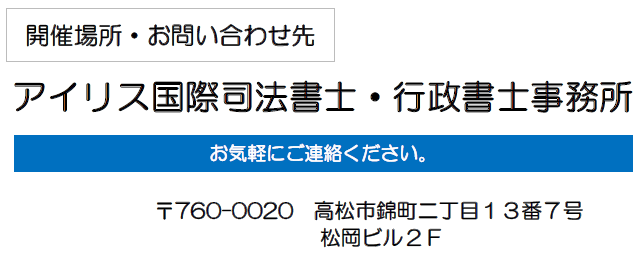


最新のブログ記事
【第4回】新年から一気に伸ばす!年内に整える環境・習慣・心構え
年が明けると「追い込み期」に突入します。その前に整えるべきは、環境・ルーティン・メンタルの3点。年内に準備しておけば、1月からスムーズにギアを上げられます。12月は"走り出す前の助走期間"。焦らず、でも確実に、自分の足場を固めましょう。
私たちは「もっと計画を立ててから」「もう少し気持ちが整ってから」と、行動を先送りにしてしまいがちです。しかし、心理学の研究でも明らかになっているのは、"やってみる"という小さな行動こそが、やる気や自信を呼び起こすという事実です。本稿では、未来を完璧に予測しようとするのではなく、「行動した先に答えが生まれる」という視点の大切さを、日常生活・仕事・学びの場面からひも解いていきます。
これからの生前対策で最も重要なのは、専門家だけで完結させないことです。
相続・終活・生活支援を「地域」とつなぐことで、実行性と安心感は大きく高まります。
2026年以降の生前対策は、「制度+人+地域」をセットで考える時代に入っています。