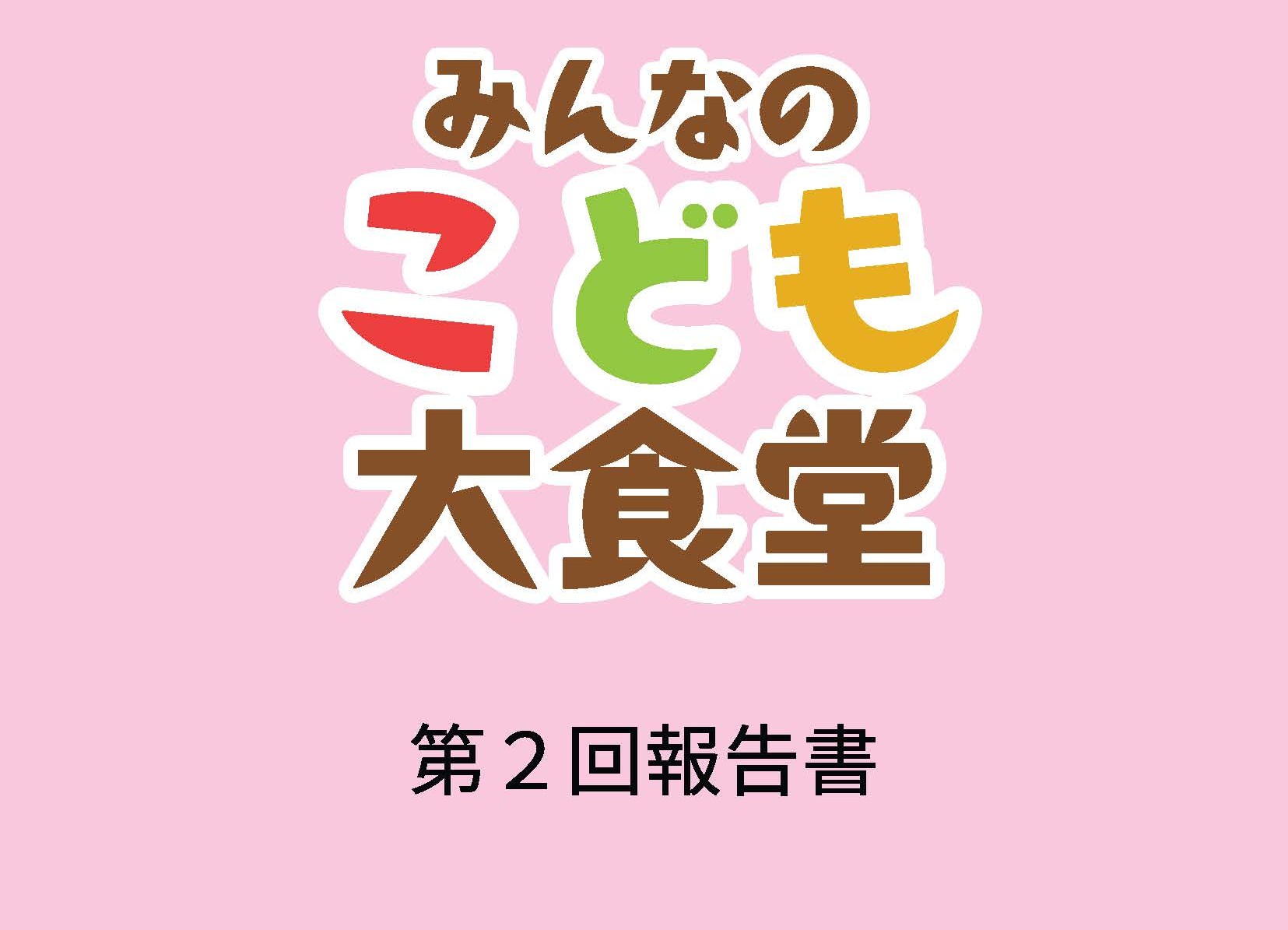相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
問題解決能力とは。

先日、電話が入り、「火災保険に入れないから、建物の種類を変えてほしい。」との問い合わせがありました。建物の種類を変えるのは、不動産登記簿の表題部の変更となります。つまり、司法書士業務ではなく土地家屋調査士の範疇となります。これだけの情報で、どのように対応すべきでしょうか?
知識はよく知っているのに、この問題解決能力が薄い方はよく見かけます。司法書士業務じゃないとわかると、無関心になってしまうのかどうかはわかりませんが、責任を負わずに、できるだけの解決への方向性を話してあげることぐらいはできると思うのですが・・・忙しいのも要因なのかもしれませんね。問題解決能力なんですが、どうやって鍛錬していけばいいのでしょうか。やっぱり場数を踏まないといけないんでしょうね。私はまだ、開発途中です。
目次
1.電話での問い合わせ内容
2.問題の根本原因
3.解決方法に導くには
4.まとめ
1.電話での問い合わせ内容
はじめは、本当に表題の情報のみでしたが、短い時間でしたが「火災保険に入れないから、建物の種類を変えてほしい。現状倉庫の中に、商売で使っている機械類があるから、どうしても火災保険に入りたい。しかし、〇〇共済の火災保険は住宅しかダメなんです。」との情報まで引き出せました。電話の問い合わせ内容通りにの対応は、土地家屋調査士に取り次ぐ、だと思います。
この時、相手側も時間がないとのことで、少しの情報だけしかいただけませんでした。今回の問い合わせ、いったい何が問題で、何が根本原因なのかを次の電話までに調査し始めました。
2.問題の根本原因
まずは、ネットで「火災保険の種類」を検索し、どのような種類の火災保険が世の中にあるのかを見ていきました。現状の倉庫でも、火災保険に加入することが可能であることを見つけました。勿論その火災保険で、倉庫内の什器や商品まで補償の対象とできる旨が説明されていました。
それでは、問い合わせされた方のご要望である「居宅への種類変更」なのですが、なぜ、そのような話になってしまったのかを考えていきました。その説明文の中で、店舗兼住宅で住宅用の火災保険に入った場合の問題点を見つけました。それは、住宅用保険だと家財道具は補償の対象となるが、什器や商品は保証の対象外になってしまうという点です。これでは、建物の種類を変更して居宅に変えたところで、「什器や商品を火災保険の対象にすること」という目的を達成することはできません。
土地家屋調査士への取次をするにも、この問題点を残したまま引き継ぐのは失礼にあたると思い、次の電話があるまで、いくつかの解決に向けた方向性を模索しました。
㋐○〇共済の取り扱っている火災保険で現行の建物種類ではダメな理由を知る。
㋑倉庫対応火災保険もあるのに○〇共済の火災保険にこだわるのはなぜか?
㋒建物の中にある什器・商品を火災保険の対象にしたいということがゴール?
しかしこれは、先方の連絡を待たないとわかりませんので次回までペンディング。
㋓建物種類を変更するとして、どのくらいのコストがかかるのか?
土地家屋調査士の方に聞けばわかります。
㋔あてはまる保険があるとして、一般的にどのくらいの保険料がかかるのか?
以上、考えて、取り揃えられる情報を収集していきました。土地家屋調査士への問い合わせは、建物種類を変える必要性がない可能性もあるため控えました。
3.解決方法に導くには
同日の夕方、再度連絡があり、上記内容で検討した情報をお伝えしました。一番優先したいポイントが、建物内の什器・商品を補償の対象にしたいとのことでしたので、登記簿上の建物の種類を挙げて、〇〇共済の担当者にどの種類のであれば、目的が達成できるのかを聞いてみるようにお話いたしました。
後日連絡があり、〇〇共済の火災保険には住宅用しかないために、居宅への種類変更を言っていたそうです。そこで、今の種類のままで、什器・商品を補償してくれる民間保険会社に何社か聞いてみるようにアドバイスをいたしました。
4.まとめ
以前の「いくら払ってもいいから隣地が欲しい」という案件もそうだったのですが、相談者の意図はどこにあるのか、本当に実現できるだけの解決策が用意できるのか、ということを常に念頭に置いて取り組まないと、相談者が言っている内容だけで行動すると、本来の解決策から遠ざかってしまうことがあるということが、よくわかりました。
相談者の声に耳を傾け、その中から解決策に向けての適切な情報を抽出し、具体的な手続きに落とし込むという作業、いうのは簡単ですが、なかなか骨が折れますね。
(情報共有:土地家屋調査士の方からの情報)
建物の種類の変更は、単に変更すればいいというのではなく、増築や建物内部の構造の変更なども反映する必要性があります。居宅にする要件は、少なくとも玄関、キッチン、風呂、トイレなど一般の生活に必要な設備が整っていないと、その先生は居宅への変更はしないと言っておりました。また、吹き抜け部分に床が設置され、床面積が変わっていたなんて事例もあるそうです。
そもそも、登記簿と保険は全く連動しておらず、未登記物件でも保険には加入することができるように、倉庫でも保険には入れるはずとのことでした。それはその通りだと思いました。
今回の事案は、全くお金にはなりませんが、相談者の方にはとても感謝されました。この積み重ねが信用に繋がっていくのだと感じました。

最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。
Q. 坂出・宇多津みんなの子ども大食堂とは?
→ 坂出市・宇多津町の子ども食堂が連携して開催する地域イベントです。