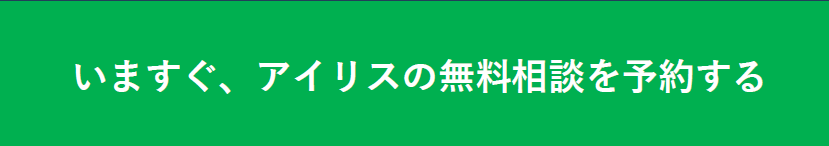宇多津町で生前対策を成功させる最短ルートは、
①財産把握 → ②名義確認 → ③遺言書 → ④認知症対策 → ⑤専門家相談
この5つを順番に進めることです。
まんのう町で始める生前対策:司法書士が解説する空き家・相続登記・町の補助を活かす実務ガイド
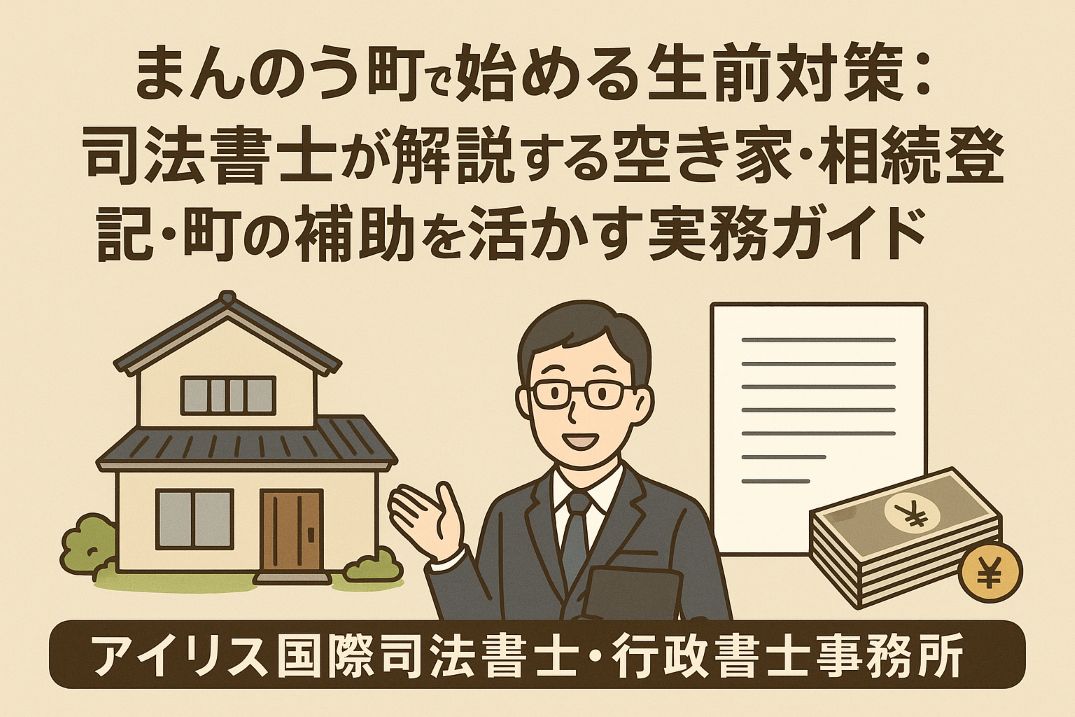
高齢化と空き家率の上昇が進む香川県まんのう町では、生前からの準備が地域の安心につながります。司法書士として、相続登記・遺言・不動産名義整理・空き家対策など、まんのう町ならではの制度や補助と実務のポイントをわかりやすく整理しました。将来のトラブルを防ぎながら、家族にも町にも優しい対策を始めましょう。
目次
- なぜまんのう町で生前対策が重要か
- 生前対策の基本ステップ
- 不動産(実家・別荘)の整理:相続登記と名義整理
- 空き家対策:利活用・除却・改修
- まんのう町の支援制度を活かす(補助・定住)
- ケース別シミュレーション
- よくあるトラブルと司法書士の支援方法
- 生前対策相談の流れと当事務所の支援メニュー
1. なぜまんのう町で生前対策が重要か

まんのう町は、美しい自然に恵まれ、満濃池などの観光資源を持つ地域ですが、一方で
空き家率が上昇中 という深刻な課題があります。令和4年度の町の実態調査では、空き家件数が 775件、空き家率が
10.1% に達しており、5年前(平成29年)の同調査と比べて 2.2ポイント の増加となっています。(まんのう町HP参照)
この背景には、人口減少や高齢化、相続未整理の住宅がそのまま空き家となる傾向があります。特に所有者間で名義が明確でない不動産は、その後の活用や売却が進みにくくなり、放置されがちです。
また高齢化の進行も顕著で、今後「要介護・要支援」と認定される方の増加が見込まれており、先手を取った対策が不可欠です。
生前対策を通じて、家族間のトラブルを未然に防ぎつつ、まんのう町における空き家問題の解消にも貢献できる可能性があります。
2. 生前対策の基本ステップ

生前対策を始めるには、以下のステップがおすすめです。
- 財産リストと家系図を作成
まずは自分の財産(不動産、預貯金、保険など)を整理し、誰が相続人になる可能性があるかを家系図で明示します。 - 遺言書の作成
遺言があれば、後の相続をスムーズにできます。公正証書遺言を活用するか、専門家(司法書士・弁護士)と相談して決めましょう。 - 家族会議の実施
相続人となる家族と話し合い、何をどう残すか、誰がどの役割を担うかを共有します。 - 名義整理・登記
不動産は登記名義の確認・整理を行い、将来的な相続登記を見据えて手続きを整備します。 - 空き家対策・利活用検討
使っていない家があれば、貸す・売る・改修するなどの手段を検討。まんのう町の補助制度も視野に入れます。
3. 不動産(実家・別荘)の整理:相続登記と名義整理

まず重要なのは、不動産の 登記事項証明書 を取得し、名義・権利関係を明確にすることです。名義が古く、相続人不在や共有者がある場合、将来の相続登記が複雑になる可能性があります。
相続登記の基本的な流れは以下の通りです:
- 相続人の確定(戸籍・除籍・住民票などで家系を整理)
- 財産評価(不動産の評価額を確認し、相続税・贈与税の可能性を検討)
- 遺産分割(共有名義にするか、分割または売却かを合意)
- 登記申請(法務局で相続登記を行う)
司法書士が関与すれば、書類作成・申請・名義変更をスムーズに進められます。
4. 空き家対策:利活用・除却・改修
まんのう町には
空き家等情報登録制度(空き家バンク) があり、空き家所有者と利用希望者をマッチングする仕組みがあります。
また、町は 空き家リフォーム補助金事業 を設けており、リフォーム費用の 50%(上限100万円)を補助しています。
これを活用して、空き家を貸す、移住者に貸す、売却しやすくするなどの選択肢を具体化することが実務的には非常に有効です。
さらに、空き家をそのまま放置するだけでなく、老朽化・危険性が高い場合は、除却も検討すべきです。まんのう町議会資料でも、危険な空き家を除却する制度が運営されていることが報告されています。
5. まんのう町の支援制度を活かす(補助・定住)

まんのう町には、生前対策や空き家対策を支える実用的な支援制度があります。
- 空き家リフォーム補助金:リフォーム費用の 50% を補助。町内業者利用が条件。
- 若者住宅取得補助事業:満 40歳以下が町内で住宅を取得した場合、上限150万円の補助。
- 東京圏からの移住補助:東京圏からまんのう町に移住する際の支援金制度。
- 空き家バンク登録制度:空き家を町のバンクに登録し、利活用希望者とマッチング可能。
これらを組み合わせて、生前のうちに名義整理や補修を進めることで、家族負担を軽くしながら地域資源として活かす道が開けます。
6. ケース別シミュレーション

以下は、典型的なまんのう町の実家/空き家を巡るケースを想定したシミュレーションです。
- ケースA:高齢の親が亡くなり、実家がそのまま空き家に
→ 登記名義が親のまま。遺言がなく共有名義者が遠方。
→ 司法書士が家系図を作成し、相続人を確定。遺産分割協議後、相続登記を実施。
→ 空き家バンクに登録 → 利活用(賃貸)を検討 → リフォーム補助を活用。 - ケースB:移住を考える子世代が40歳以下で町内に住宅を取得
→ 若者住宅取得補助を活用 → 取得資金の軽減 → 将来的な相続対策のスキームも事前に設計。 - ケースC:古くて老朽化した実家を取り壊すかどうか迷っている
→ 危険空き家認定の可能性を確認 → 除却制度の活用 →将来的な管理コストを削減。
7. よくあるトラブルと司法書士の支援方法
- 共有名義で相続人間に意見がまとまらない → 遺産分割協議を支援
- 遠方在住の相続人が多くて連絡調整が難しい → 委任状・オンライン相談の活用
- 名義が古くて調査が大変 → 履歴調査と戸籍収集を司法書士が代行
- 空き家の老朽化・危険性 → 危険性評価、除却の提案、補助申請支援

📞生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中
(完全予約制)
📞 電話予約:087-873-2653
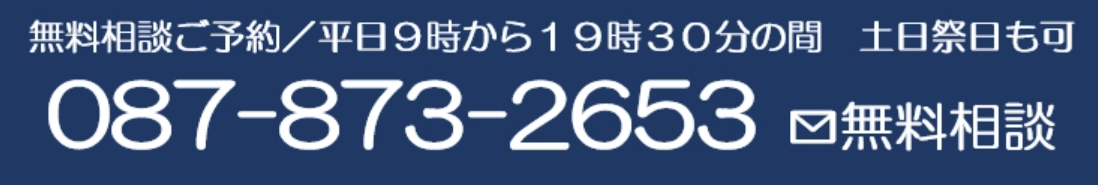
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


アイリスあんしん終活相談所
高松市で生前対策を始めるなら、
「遺言書・認知症対策・相続登記」この3つを早めに準備することが最重要です。
結論から言うと、丸亀市の生前対策は「いきなり専門家に依頼する」のではなく、行政の無料相談窓口+司法書士を併用する方法が最も失敗が少なく、費用も抑えられる進め方です。
認知症対策で最も大切なのは、実は「医療」ではありません。
生活費を止めないこと=お金の対策 です。