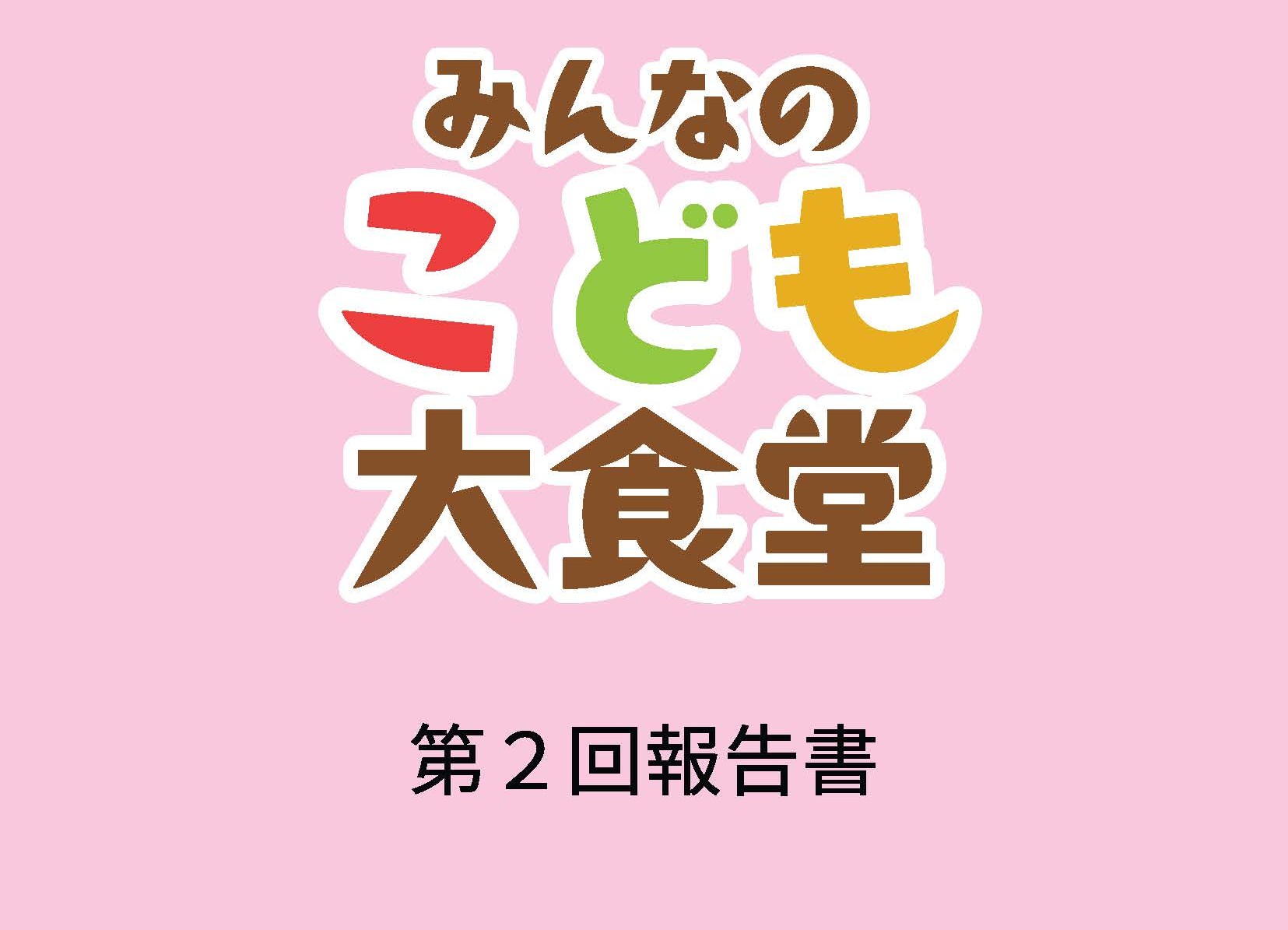相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
司法書士を目指されている方へ(人と異なる人生を歩むということ)
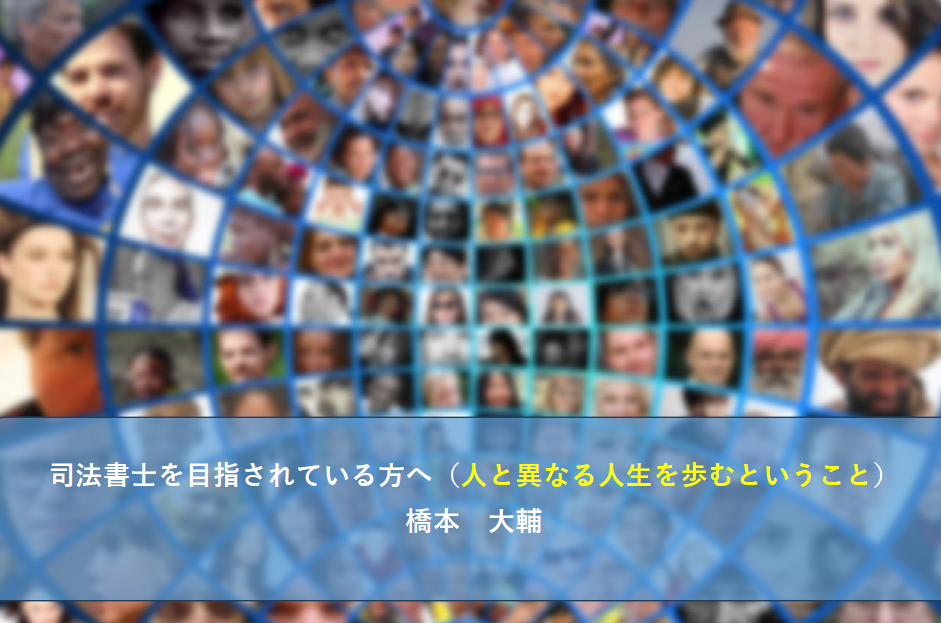
先日、とある会での一幕で、同時期位に開業した方と話をしている中で、開業後、元の同僚と話をする機会があったそうです。その中で、「今どのくらい稼いでいるのか?」という話になり、あまり稼げていないという話をすると、本人がどう思っているかはわからないのですが、皆の顔が少し安心したような顔になったことを話されていました。私もこれ経験あります。どういった心境で、このようになるのかを少し考察してみたいと思います。
目次
1.人間の本質的な部分
2.自分と異なる人生を歩む人に対する嫉妬?
3.司法書士事務所の経営
4.まとめ
1.人間の本質的な部分
人間の本質について、以前岡田斗司夫ゼミで興味深い話をされていました。最近のSNSで写真をアップする方について、巷では「承認欲求」が原因として話をされることが多いのですが、実はそうではなく、もともと人間が群れとして集団生活をしていた時代に、いかに自分がその群れで優秀で必要な人間なのかということをアピールしなければ、殺されてしまうかもしれないため、彼らは本能的に自身の所属する群れでの優位性を一生懸命アピールしているということを言っていました。人にマウントを取ってくる人も同じだと思います。しかし、相手を選んでやらないと、群れを飛び出して生活をしている人種にとっては、滑稽にしか見えません。また、相手を見下しすぎると必要な情報や裏事情など、業務に必要な情報を取り損ねる結果にもなりかねません。
わたしは、このような人の習性を逆に利用して人を見ていますので、あまり薄い人生経験しかない方の話は時間の無駄ですので、聞かないようにしています。聞いたところで同じ話しかできませんしね。勿論態度には出しませんよ、大人ですから。でも、何度も同じ話を聞くのって苦痛以外の何物でもないですからね。
群れを成すのが好きな方も、この集団生活の時代から抜け切れていないのだと考えます。人を蹴落としたり、声の大きさで優位性を図ることができるのは、「集団」の中にいるからにほかなりません。
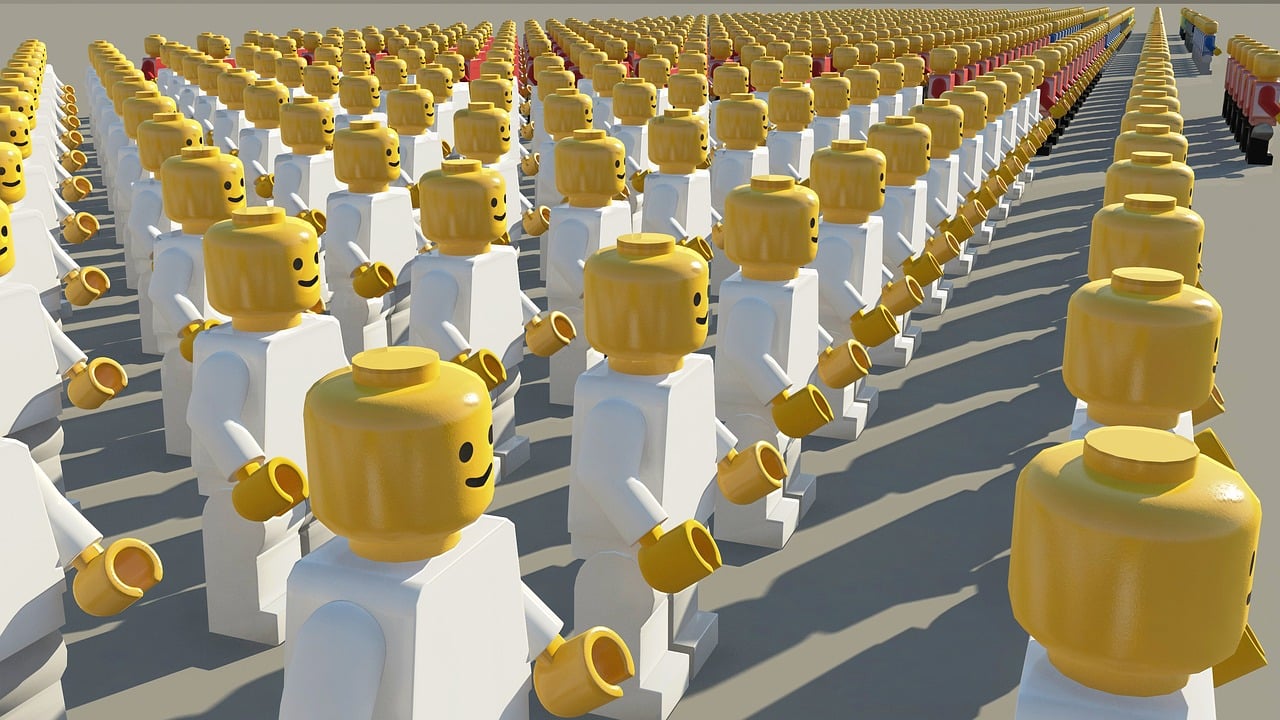
2.自分と異なる人生を歩む人に対する嫉妬?
司法書士試験を受けるということは、群れに属しながら受験する方もいれば、群れから外れて行動する方もいらっしゃいます。私は、完全に群れから離れて、試験勉強をしていましたから、蹴落とす人も声を大にしても聞いてくれる人はいませんでしたから、必然的に、「敵は自分」ということになり、他責からはいち早く抜け出していました。これがのちの独立開業には役立ったと思います。
私に話をしてくれた方も、群れから抜け出した一人でした。群れという組織に属する安心感は確かにありますが、群れから抜け出して、独立して事業をしている人の動向は、やはり気になるのだと思います。ですので、近況を確認して、彼らの予想の範囲内の状況だと、「ああ、やっぱり組織に属していてよかった。」みたいな安心感を感じるからこそ、顔にその表情が生まれるのだと考えます。このような感情のことを「シャーデンフロイデ」(ドイツ語)というみたいですね。
また、せっかく群れから抜け出せたのに、自分で群れをつくろうと躍起になる方もいらっしゃいますし、私からすれば、理解できません。

3.司法書士事務所の経営
事務所の経営は、サラリーマンの給料のように固定した収入がある訳ではありません。1から収益を作る事業をやっていかなければ、事業そのものが継続できない結果になってしまいます。サラリーマンの生き方を否定する気は毛頭ありません。私は、その立ち位置で20年以上やってきたわけですからね。しかし、事務所経営をするにあたり、その考え方を改めなければなりませんでした。全く異なる考えで取り組まなければ、収益なんて望めるわけはありませんから。事務所の立ち上げから、営業に至るまで、自分の頭で考えて構築していきました。幸運にも、私の場合、1年と少しで、その結果が出てきましたので、他の人と比べるとラッキーだったと思います。
他の先生に「もう給料は稼げるようになったの?」という質問を受けましたが、内心「??」でした。経営者に給料なんてものはありませんからね。まだ、この方は、抜け切れていないのでしょう。

4.まとめ
やとわれの司法書士を目指している方には、あまり参考にならないかもしれませんが、今後独立開業を目指されている方で、司法書士試験を受けている方は、覚悟しておいてください。経営者になるということは、今までとは異なる人生を歩み始めるということです。しかし、安心してください。サラリーマンをやっていたのでは、決してみることができない景色を見ることができます。また、自分の工夫次第では、売上だって大きく伸ばすことができます。少なくとも私は、司法書士を楽しんでできています。
最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
香川県でも「うちは大丈夫」と思っていたご家庭が、
遺言書がないことで手続停止や家族対立に発展するケースは珍しくありません。
Q. 坂出・宇多津みんなの子ども大食堂とは?
→ 坂出市・宇多津町の子ども食堂が連携して開催する地域イベントです。