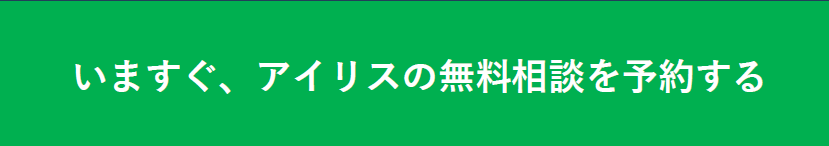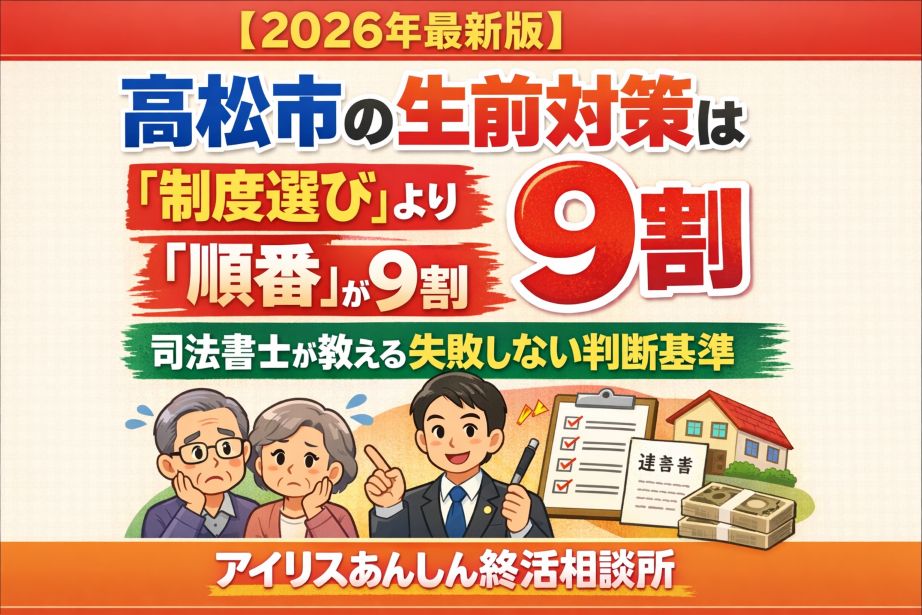高松市で生前対策を始めるなら、
「遺言書・認知症対策・相続登記」この3つを早めに準備することが最重要です。
香川県で始める生前対策|司法書士が教える安心の準備と相続対策

「実家の空き家が遠方にあって管理が大変」「親が認知症になったら財産を誰がどう管理するか不安」「相続登記を放置してはいけないと聞いたけれど、手続きが煩雑でよく分からない」――そんな不安を抱える香川県・高松市在住の方へ。相続登記義務化の開始により、3年以内に登記をしなければ過料も。 今ならまだ手遅れではありません。遺言書・生前贈与・家族信託などを使った具体的な対策を、司法書士が丁寧にサポートします。
目次
- なぜ香川県で「生前対策」が注目されているのか
- 生前対策の基本|家族を守るための準備とは
- 香川県に多い相続・財産の特徴
- 遺言書作成の重要性と種類
- 生前贈与の活用方法と注意点
- 家族信託と任意後見のちがい
- 相続登記義務化と放置リスク
- 香川県での実例|もめない相続への取り組み
- よくある質問(FAQ)
- まとめと司法書士への相談のすすめ
1. なぜ香川県で「生前対策」が注目されているのか

少子高齢化が進む香川県では、相続に関するトラブルが年々増加しています。特に高松市や丸亀市では、土地や空き家を巡る相続問題が顕著です。
2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続が発生してから3年以内に登記を行わなければ**過料(最大10万円)**の対象となります。
こうした背景から「まだ元気なうちに準備を進めたい」という相談が急増しています。
2. 生前対策の基本|家族を守るための準備とは

生前対策とは、**「自分に万一のことがあった時に、家族が困らないように備えること」**を意味します。
具体的には以下のような準備を指します。
- 遺言書の作成
- 生前贈与の活用
- 家族信託や任意後見制度の利用
- エンディングノートによる意思の整理
- 相続登記の早期対応
「まだ元気だから大丈夫」と思っている方ほど、早めの準備が重要です。
3. 香川県に多い相続・財産の特徴

香川県の相続では、次のような傾向が目立ちます。
- 農地や山林:相続後に管理が難しく、放置されやすい。
- 実家の空き家:相続人が県外に住んでいる場合、維持費・固定資産税の負担が問題化。
- 中小企業・個人事業の承継:後継者不足から「事業承継」が重要課題。
これらは遺言や生前贈与、信託などを組み合わせることで、円滑に引き継ぐことができます。
4. 遺言書作成の重要性と種類

相続対策の第一歩は「遺言書」です。
遺言書があるだけで、遺産分割協議のトラブルを大幅に防げます。
- 自筆証書遺言:手軽だが不備のリスクあり
- 公正証書遺言:公証人が関与するため安心度が高い
- 秘密証書遺言:利用は少ないが、内容秘匿性あり
香川県では特に「公正証書遺言」の利用が増えており、家族全員の安心につながっています。
5. 生前贈与の活用方法と注意点

「相続税対策」として注目されるのが生前贈与です。
特に香川県では、住宅資金援助や農地の承継に利用されるケースが多いです。
- 暦年贈与:毎年110万円まで非課税
- 相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税(将来精算)
- おしどり贈与:婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産2,000万円まで非課税
ただし、形式不備や契約書不足で無効になる例もあるため、司法書士・税理士のサポートが不可欠です。
6. 家族信託と任意後見のちがい

認知症リスクが高まる中、「財産管理をどうするか」は大きなテーマです。
- 家族信託:柔軟に資産を管理できる。空き家・事業承継に有効。
- 任意後見:本人が元気なうちに契約し、判断能力が低下したら後見人が財産管理を行う。
香川県でも、最近は「家族信託」を利用して事業承継や不動産管理を行うケースが増加しています。
7. 相続登記義務化と放置リスク
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続発生から3年以内に登記をしないと、**過料(10万円以下)**を科される可能性があります。
香川県内でも、農地や空き家が放置されたままの事例が多く、トラブルの火種になっています。
相続登記を怠ると…
- 売却・担保設定ができない
- 固定資産税の通知が届かない
- 共有者が増え、手続きが複雑化
➡ 早めの登記手続きが安心です。
8. 香川県での実例|もめない相続への取り組み
- 高松市の事例:公正証書遺言を作成し、長男に自宅を相続、他の相続人には預金を分ける形で合意。
- 丸亀市の事例:農地を家族信託により管理。相続人が県外に住んでいても円滑に引き継げた。
- 小豆島の事例:相続登記を放置し数十人の共有者が発生、売却が困難に。司法書士介入で解決。
地域ごとの事情に合わせた対策が必要です。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書がないとどうなりますか?
👉 遺産分割協議が必要となり、相続人間でもめる原因となります。今の現状の家族関係でもめる要素があれば、遺言書の作成は有効です。もめてなくても、遺産を承継したい先が決まっているなら書いた方がいいでしょう。
Q2. 相続登記はいつまでにしないといけない?
👉 相続開始したことを知ったときから3年以内に登記申請が義務化されています。
Q3. 家族信託と遺言はどちらが良いですか?
👉 遺言は「死後の財産承継」、家族信託は「生前からの財産管理」(認知症になった後の財産管理)に向いています。両方を併用するケースもあります。
10. まとめと司法書士への相談のすすめ
生前対策は「元気なうちに始めること」が成功の秘訣です。
遺言・贈与・信託・登記を早めに準備すれば、家族が安心して暮らせます。
特に香川県では、農地や空き家の問題、相続登記義務化への対応が喫緊の課題です。
トラブルになる前に、司法書士へお気軽にご相談ください。

(無料相談のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653
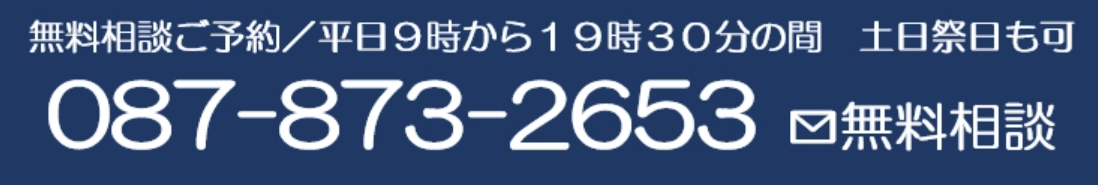
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


アイリスあんしん終活相談所
結論から言うと、丸亀市の生前対策は「いきなり専門家に依頼する」のではなく、行政の無料相談窓口+司法書士を併用する方法が最も失敗が少なく、費用も抑えられる進め方です。
認知症対策で最も大切なのは、実は「医療」ではありません。
生活費を止めないこと=お金の対策 です。
高松市で生前対策を考える方の多くが、最初にこう質問されます。
「遺言と家族信託、どっちがいいですか?」